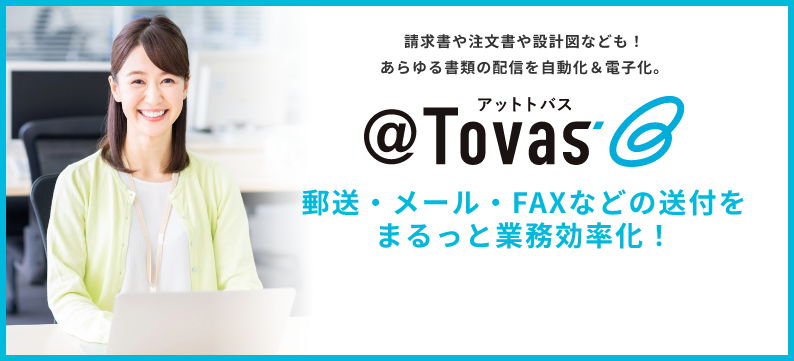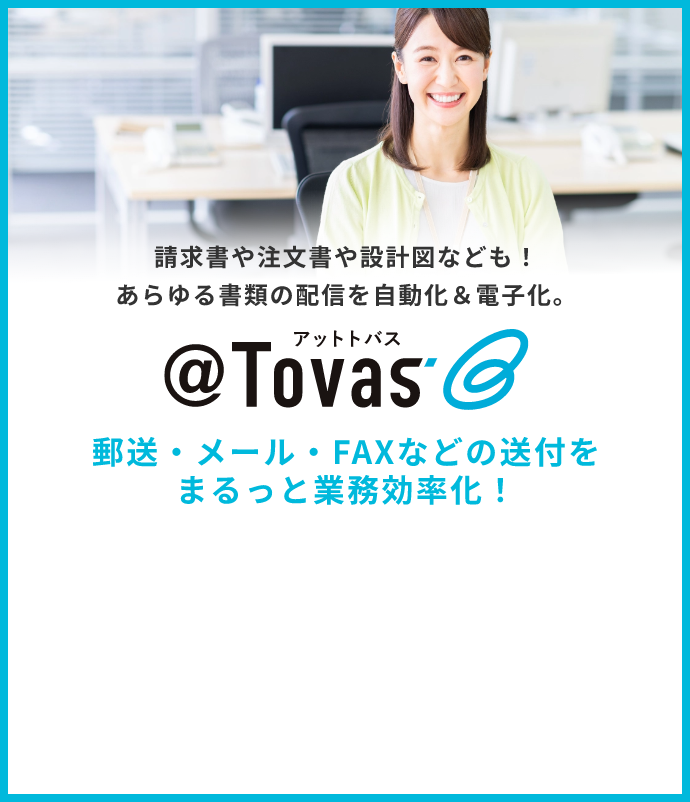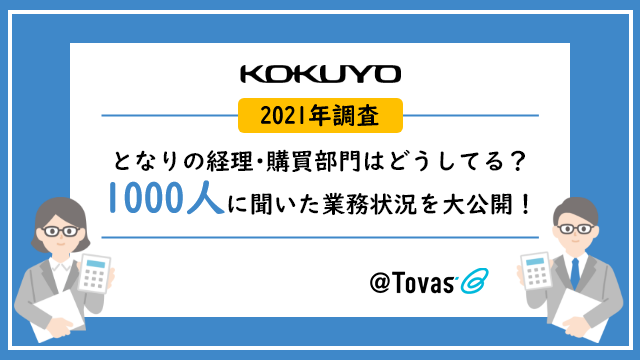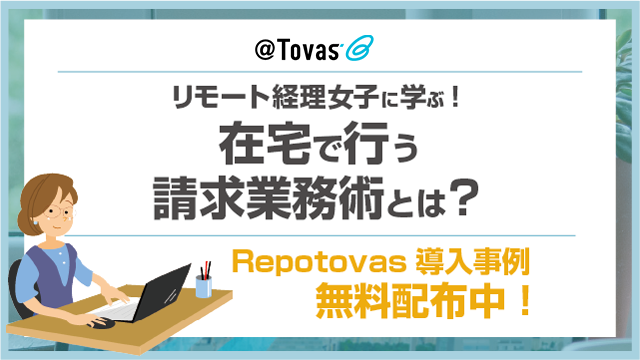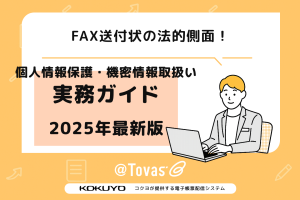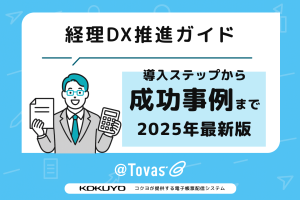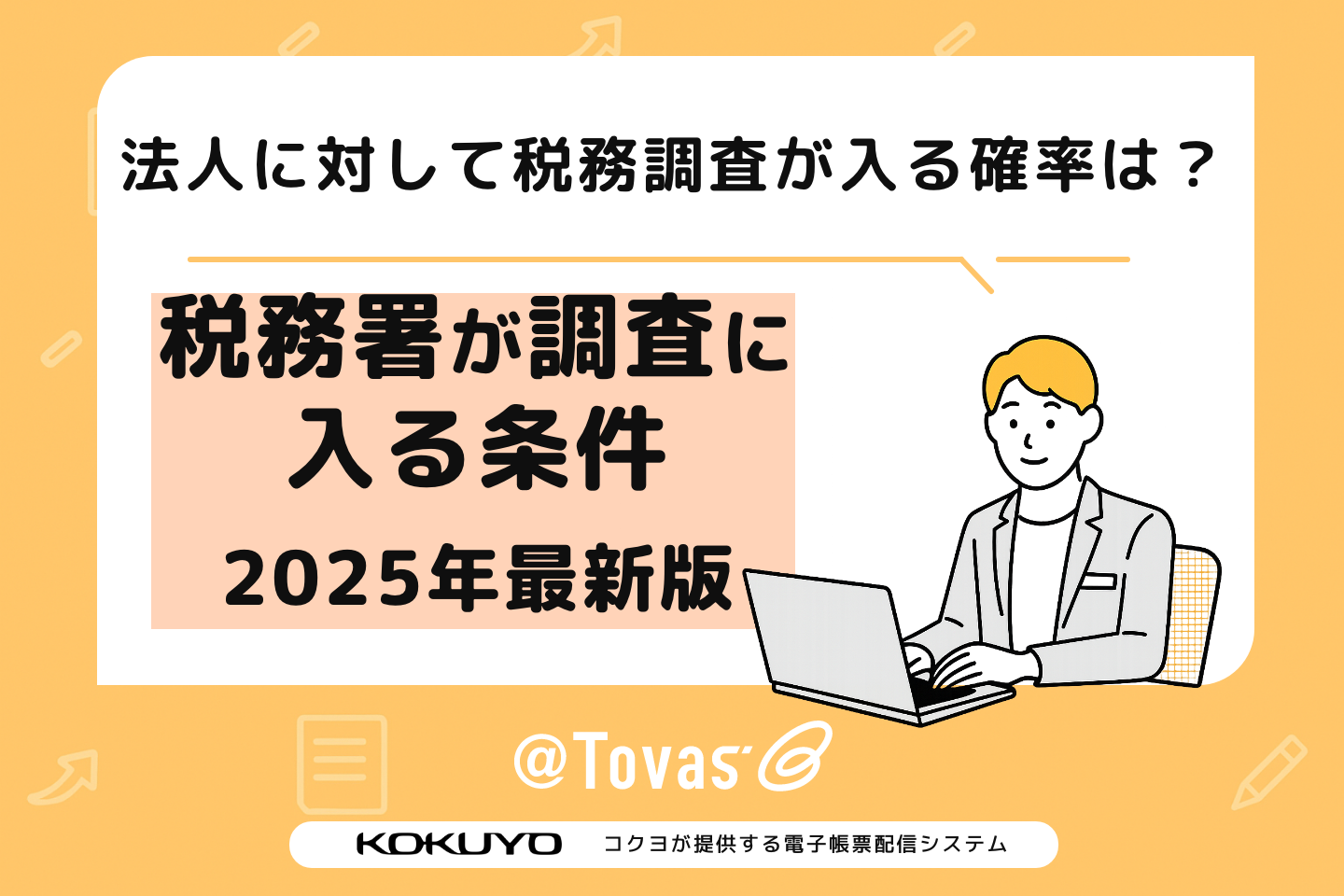
法人に対して税務調査が入る確率は?税務署が調査に入る条件とは【2025年最新版】
公開日:2025年4月16日 更新日:2025年7月28日
「税務調査が入るかもしれない」という不安は、多くの法人経営者や経理担当者を悩ませています。税務調査は税務署が法人の申告内容を確認するために行う調査ですが、いつ、どのような条件で行われるのかを正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、法人に対する税務調査の確率や、税務署が調査に入る条件について、2025年の最新情報をもとに詳しく解説します。また、税務調査に備えるための対策や、調査が入った場合の適切な対応方法についても紹介します。
ご利用件数6,000件以上!コクヨの@Tovasは帳票発行業務の改善・効率化・コスト削減を実現!
目次
税務調査とは?基本的な理解
税務調査とは、税務署や国税局が法人や個人事業主の申告内容を確認し、適正な納税が行われているかを調査する制度です。税務調査は、申告内容の正確性を確認するだけでなく、税務上の誤りを是正し、適正な納税を促進する役割も担っています。
税務調査の種類
税務調査には主に以下の2種類があります。
任意調査
任意調査は、税務署が行う一般的な税務調査で、納税者の同意と協力のもとで実施されます。事前に税務署から連絡があり、調査の日程や必要書類などについての通知があります。多くの法人が経験する税務調査は、この任意調査です。
任意調査は、法人税、消費税、源泉所得税などの申告内容を確認するために行われます。調査官は帳簿や請求書、領収書などの証憑書類を確認し、申告内容との整合性をチェックします。
強制調査(査察)
強制調査(査察)は、重大な脱税の疑いがある場合に国税局の査察部が実施する調査です。一般に「マルサ」と呼ばれることもあります。強制調査は裁判所の許可を得て行われ、事前通知なしに突然訪問することが特徴です。
強制調査は、悪質な脱税が疑われる場合に限って行われる特別な調査であり、一般の法人が経験することは稀です。
税務調査の実施機関
税務調査を実施する機関は、調査の規模や内容によって異なります。
税務署
一般的な任意調査は、各地域を管轄する税務署が実施します。中小企業や個人事業主に対する調査は、主に税務署が担当します。
国税局
大企業や複雑な税務問題を抱える法人に対しては、国税局が調査を行うことがあります。また、前述の強制調査(査察)は国税局の査察部が担当します。
法人に対する税務調査の確率
法人に対する税務調査の確率は、年度や業種、法人の規模などによって異なりますが、2025年の最新データによると、以下のような傾向があります。
法人税務調査の実施確率の統計データ
国税庁が公表している最新の統計データによると、法人に対する税務調査の実施確率は約1.5%~3%程度とされています。これは、法人全体で見ると、30年~70年に1度の頻度で税務調査が行われる計算になります。
ただし、この確率はあくまで平均値であり、業種や法人の特性によって大きく異なることに注意が必要です。
個人事業主との確率比較
個人事業主に対する税務調査の確率は約0.5%~1.0%程度で、法人と比較すると低い傾向にあります。これは、個人事業主の数が法人よりも多いことや、一般的に取引規模が小さいことが理由として考えられます。
しかし、個人事業主であっても、特定の条件に該当する場合は税務調査の対象になる確率が高まります。
業種別の税務調査確率の違い
国税庁が毎年発表している「不正発見割合が高い業種」や「申告漏れ所得金額が大きい業種」は、税務調査の対象になりやすいとされています。2025年の最新データによると、以下の業種は税務調査の確率が高い傾向にあります。
不正発見割合の高い業種(法人税)
1. バー・クラブ
2. その他の飲食
3. 外国料理
4. 土木工事
5. 美容
6. 一般土木建築工事
7. 職別土木建築工事
8. 廃棄物処理
9. 船舶
10. その他の道路貨物運送
不正所得金額の大きな業種(法人税)
1. その他の化学工業製造
2. 化粧品小売
3. 物品賃貸
4. 精密機械器具卸売
5. 映画サービス
6. 採石、砂・砂利採取
7. 広告
8. その他の卸売
9. 外国料理
10. 金属打抜き・プレス加工
これらの業種に該当する法人は、税務調査の対象になる確率が平均よりも高いと考えられます。
2025年の最新動向と傾向
2025年の税務調査に関する最新の動向としては、以下のような傾向が見られます。
1. デジタル化の進展税務署のデジタル化が進み、AIを活用した申告内容の分析が強化されています。これにより、不自然な申告内容を持つ法人が効率的に抽出されるようになっています。
2. インボイス制度の定着2023年10月から導入されたインボイス制度が定着し、取引の透明性が高まったことで、消費税に関する調査が強化されています。
3. 国際取引の監視強化国際的な税務情報の交換が進み、海外との取引がある法人に対する調査が強化されています。
4. テレワーク対応新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、リモートでの税務調査や、オンライン提出による書面調査が増加しています。
税務調査の対象になりやすい法人の特徴
税務調査はランダムに行われるわけではなく、特定の特徴を持つ法人が優先的に選ばれる傾向があります。以下に、税務調査の対象になりやすい法人の特徴を紹介します。
売上や利益の急激な変動がある法人
前年度と比較して売上や利益に大きな変動がある法人は、税務調査の対象になりやすいです。特に、以下のような場合は注意が必要です。
・ 売上が急激に増加している
・ 売上が急激に減少している
・ 利益率が大きく変動している
・ 経費が急激に増加している
これらの変動は、申告内容に不審な点がある可能性を示唆するため、税務署の注目を集めやすくなります。
同業他社と比較して利益率が低い法人
同業他社と比較して利益率が著しく低い法人は、売上の計上漏れや経費の過大計上の可能性があるとみなされ、税務調査の対象になりやすくなります。
国税庁は業種ごとの平均的な利益率のデータを持っており、それと大きく乖離している場合は、調査対象として選定される可能性が高まります。
長期間赤字が続いている法人
複数年にわたって赤字が続いている法人も、税務調査の対象になりやすい傾向があります。特に、以下のような場合は注意が必要です。
・ 3年以上連続して赤字決算を計上している
・ 事業実態に比べて不自然な赤字が続いている
・ 役員報酬は支払われているのに会社は赤字である
長期間の赤字にもかかわらず事業を継続している場合、税務署は売上の計上漏れや個人的な経費の混入などを疑う可能性があります。
過去に税務調査で指摘を受けた法人
過去の税務調査で重大な指摘を受けた法人は、その後の改善状況を確認するために再度調査される可能性が高くなります。特に、以下のような場合は注意が必要です。
・ 過去の調査で多額の申告漏れが発見された
・ 過去の調査での指摘事項が改善されていない可能性がある
・ 過去の調査から一定期間(通常3~5年)が経過している
過去の調査結果は税務署に記録されているため、問題があった法人は継続的に監視される傾向があります。
申告内容に不審点がある法人
申告内容に不自然な点や不審な点がある法人も、税務調査の対象になりやすくなります。例えば、以下のような場合です。
・ 売上高が1,000万円にやや足りない(消費税の課税事業者になる基準を意図的に回避している疑い)
・ 経費の内訳が不自然(個人的な経費を混入している疑い)
・ 資産の増加と収入が見合っていない
・ 決算書と申告書の内容に不一致がある
税務署はAIなどを活用して申告内容を分析し、不自然な点を抽出する能力を高めています。
投書やタレコミがある法人
従業員や取引先、競合他社などからの投書やタレコミがある法人も、税務調査の対象になりやすくなります。特に、以下のような情報が寄せられた場合は注意が必要です。
・ 売上の一部を計上していない(裏金の存在)
・ 架空経費を計上している
・ 従業員に給与を現金で支払っている(給与の一部を申告していない)
・ 個人的な支出を会社の経費として計上している
税務署は匿名の情報提供も受け付けており、具体的かつ信頼性の高い情報が寄せられた場合は、調査に着手する可能性が高くなります。
税務調査が行われる時期と頻度
税務調査がいつ行われるのかを知ることは、適切な準備をするために重要です。ここでは、税務調査が行われる一般的な時期と頻度について解説します。
決算申告後の一般的なタイミング
法人に対する税務調査は、一般的に決算申告後から数か月~1年以内に行われることが多いです。これは、申告内容を確認するのに十分な時間を確保するためです。
具体的には、3月決算の法人の場合、5月末までに法人税の申告を行い、その後の7月~翌年3月頃に税務調査が行われることが多いとされています。
税務調査の周期性
税務調査には一定の周期性があり、前回の調査から一定期間が経過すると再び調査の対象になる可能性が高まります。一般的には、以下のような周期で調査が行われる傾向があります。
・ 大企業3~5年に1回
・ 中小企業5~7年に1回
・ 小規模法人7~10年に1回、または調査なし
ただし、これはあくまで目安であり、前述の「税務調査の対象になりやすい法人の特徴」に該当する場合は、この周期よりも短い間隔で調査が行われる可能性があります。
事業開始からの経過年数と調査確率の関係
法人や個人事業主は、開業から3年以上が経過すると税務調査を受けやすくなります。これは、税務調査で確認される帳簿が通常3年分であることや、開業直後は事業が安定していないことが理由として考えられます。
特に、開業後3~5年目の法人は、事業が軌道に乗り始め、売上や利益が増加する時期であるため、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
税務署の事務年度と調査時期の関連性
税務署の事務は7月1日~翌年6月30日を1事務年度として運営されています。これは、一般的な会計年度(4月1日~翌年3月31日)とは異なります。
税務調査は、事務年度の前半(7月~12月)に集中して行われる傾向があります。これは、事務年度の後半になると確定申告の対応などで税務署が忙しくなるためです。
また、税務署の事務年度末である6月に近づくと、調査件数の目標達成のために調査が増える傾向もあります。
税務調査の流れと対応方法
税務調査が決まった場合、どのような流れで進み、どのように対応すべきかを理解しておくことは重要です。ここでは、税務調査の一般的な流れと適切な対応方法について解説します。
事前通知から調査終了までの流れ
1. 事前通知
任意調査の場合、税務署から事前に電話や文書で通知があります。通常、調査の1週間~10日前に連絡があり、以下の内容が伝えられます。
・ 調査の日時と場所
・ 調査の対象となる税目と期間
・ 準備すべき書類や資料
・ 調査担当者の氏名と連絡先
2. 事前準備
事前通知を受けたら、指定された書類や資料を準備します。一般的に準備が必要な書類は以下の通りです。
・ 帳簿類(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など)
・ 決算書類(貸借対照表、損益計算書など)
・ 申告書類(法人税申告書、消費税申告書など)
・ 証憑書類(請求書、領収書、契約書など)
・ 預金通帳や銀行取引明細
・ 固定資産台帳
・ 給与台帳や源泉徴収票
3. 調査当日
調査当日は、税務調査官が会社を訪問し、以下のような流れで調査が進みます。
・ 挨拶と身分証明書の提示
・ 会社の概要や事業内容についてのヒアリング
・ 帳簿や証憑書類の確認
・ 疑問点や不明点についての質問
・ その日の調査内容のまとめ
4. 追加調査
1日で調査が終わらない場合は、追加の調査日が設定されます。大企業の場合は数週間~数か月、中小企業でも数日~1週間程度の調査期間が必要になることがあります。
5. 調査結果の説明
調査が終了すると、税務調査官から調査結果の説明があります。申告内容に問題がなければその旨が伝えられ、問題があれば指摘事項と追加納税額が示されます。
6. 修正申告または更正処分
指摘事項に同意する場合は修正申告を行い、同意しない場合は税務署長による更正処分が行われます。修正申告の場合は、追加納税額に加えて延滞税や過少申告加算税などが課されることがあります。
税務調査官の訪問時の対応ポイント
税務調査官が訪問した際の適切な対応は、調査をスムーズに進めるために重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 誠実な対応を心がける
税務調査官に対しては、誠実かつ協力的な態度で接することが重要です。敵対的な態度や非協力的な姿勢は、調査の長期化や詳細な調査につながる可能性があります。
2. 質問には正確に答える
税務調査官からの質問には、正確かつ簡潔に答えるよう心がけましょう。わからないことは「わからない」と正直に伝え、後で確認して回答するようにします。
3. 必要以上の情報は提供しない
質問されたことに対してのみ回答し、必要以上の情報を自発的に提供することは避けましょう。余計な情報が新たな調査項目につながる可能性があります。
4. メモを取る
調査の内容や質問事項、回答内容などはメモを取っておくことをおすすめします。後で確認が必要になった場合や、税理士との打ち合わせの際に役立ちます。
5. 無理な回答や虚偽の説明は避ける
わからないことや説明が難しいことについて、無理に回答したり虚偽の説明をしたりすることは絶対に避けましょう。後で矛盾が発覚すると、より詳細な調査の対象になる可能性があります。
必要書類の準備と整理方法
税務調査に備えて、日頃から書類を適切に準備・整理しておくことが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 書類の保存期間を守る
法定保存期間は以下の通りです。これらの期間を守って書類を保存しましょう。
・ 帳簿類7年間(青色申告の場合)
・ 証憑書類7年間
・ 決算書類永久保存が望ましい
2. 書類を整理して保管する
書類は種類ごと、年度ごとに整理して保管しましょう。特に以下の点に注意します。
・ 請求書や領収書は日付順に整理する
・ 電子データと紙の書類の整合性を確保する
・ 重要な契約書や稟議書は別途保管する
3. 電子帳簿保存法に対応する
電子帳簿保存法に基づいて電子データを保存する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
・ タイムスタンプの付与
・ 検索機能の確保
・ 改ざん防止措置
・ 可視性の確保
税理士の同席と役割
税務調査には、可能であれば税理士の同席を依頼することをおすすめします。税理士は以下のような役割を果たします。
1. 専門的な質問への対応
税法や会計に関する専門的な質問に対して、適切に回答することができます。
2. 調査官とのコミュニケーション
税理士は税務調査官と同じ専門知識を持っているため、円滑なコミュニケーションが可能です。
3. 指摘事項の妥当性の判断
調査官からの指摘事項が税法上妥当かどうかを判断し、必要に応じて反論することができます。
4. 修正申告の検討と対応
修正申告が必要な場合、その内容や金額の妥当性を検討し、適切な対応を助言します。
税務調査で指摘されやすい項目
税務調査では、特定の項目が重点的にチェックされる傾向があります。ここでは、税務調査で指摘されやすい主な項目について解説します。
経費計上の妥当性に関する指摘
経費の計上に関しては、以下のような点が指摘されやすいです。
1. 交際費の過大計上
交際費は、その性質上、個人的な支出との区別が難しい場合があります。以下のような点がチェックされます。
・ 接待の相手や目的が明確か
・ 金額が社会通念上妥当か
・ 領収書や明細書が保存されているか
・ 交際費等の損金不算入額が正しく計算されているか
2. 役員や従業員の個人的経費の混入
役員や従業員の個人的な経費を会社の経費として計上していないかがチェックされます。特に以下の項目は注意が必要です。
・ 旅費交通費(プライベートな旅行を出張として計上)
・ 飲食費(私的な飲食を会議費や交際費として計上)
・ 自動車関連費用(私用車の経費を会社負担にしている)
・ 家賃や光熱費(役員の自宅の費用を会社負担にしている)
3. 減価償却費の計算誤り
固定資産の減価償却に関しては、以下のような点がチェックされます。
・ 耐用年数の適用誤り
・ 償却方法の適用誤り
・ 少額減価償却資産の取扱いの誤り
・ 資本的支出と修繕費の区分の誤り
売上の計上漏れに関する指摘
売上の計上に関しては、以下のような点が指摘されやすいです。
1. 現金売上の計上漏れ
現金で受け取った売上が適切に計上されているかがチェックされます。特に以下の点に注意が必要です。
・ レジの売上と帳簿の整合性
・ 現金出納帳と預金入金の整合性
・ 棚卸資産の減少と売上の整合性
2. 売上の繰延べや前倒し
決算対策として売上の計上時期を操作していないかがチェックされます。以下のような点が注目されます。
・ 期末近くの売上や返品の処理
・ 翌期の売上を当期に計上していないか
・ 当期の売上を翌期に繰り延べていないか
3. 役員や関連会社との取引
役員や関連会社との取引が適正な価格で行われているかがチェックされます。特に以下の点に注意が必要です。
・ 役員への資産の低額譲渡
・ 関連会社との取引価格の妥当性
・ 役員からの借入金や貸付金の金利の妥当性
在庫評価に関する指摘
在庫(棚卸資産)の評価に関しては、以下のような点が指摘されやすいです。
1. 在庫の過大評価や過小評価
在庫の評価額が適正かどうかがチェックされます。特に以下の点に注意が必要です。
・ 評価方法(原価法、低価法)の適用誤り
・ 長期滞留在庫の評価減の未処理
・ 実地棚卸と帳簿の不一致
2. 仕掛品の評価誤り
製造業などでは、仕掛品の評価が適正かどうかがチェックされます。以下のような点が注目されます。
・ 原価計算の方法の妥当性
・ 仕掛品に含める費用の範囲の妥当性
・ 仕掛品の進捗度の妥当性
役員報酬や交際費に関する指摘
役員報酬や交際費は、税務調査で特に注目される項目です。
1. 役員報酬の損金算入
役員報酬が適正に処理されているかがチェックされます。特に以下の点に注意が必要です。
・ 事前確定届出給与の手続きの適正性
・ 利益連動給与の計算の適正性
・ 役員賞与の処理の適正性
・ 役員退職金の妥当性
2. 交際費の区分
交際費と他の経費の区分が適正かどうかがチェックされます。以下のような点が注目されます。
・ 会議費と交際費の区分
・ 福利厚生費と交際費の区分
・ 広告宣伝費と交際費の区分
・ 交際費の相手先や目的の明確性
消費税の処理に関する指摘
消費税の処理に関しては、以下のような点が指摘されやすいです。
1. 課税売上割合の計算誤り
課税売上割合の計算が適正かどうかがチェックされます。特に以下の点に注意が必要です。
・ 非課税売上の範囲の誤り
・ 課税売上割合の計算方法の誤り
・ 課税売上割合に基づく仕入税額控除の計算誤り
2. インボイス制度への対応
2023年10月から導入されたインボイス制度に関して、以下のような点がチェックされます。
・ 適格請求書発行事業者の登録の有無
・ 適格請求書の保存状況
・ 適格請求書に基づく仕入税額控除の計算の適正性
3. 非課税取引や不課税取引の処理
非課税取引や不課税取引の処理が適正かどうかがチェックされます。以下のような点が注目されます。
・ 非課税取引(金融取引、土地の譲渡など)の区分の適正性
・ 不課税取引(寄付金、補助金など)の区分の適正性
・ 輸出免税の適用の適正性
税務調査に備えるための日常的な対策
税務調査に備えるためには、日常的な対策が重要です。ここでは、税務調査に備えるための具体的な対策について解説します。
適切な帳簿管理と証憑書類の保存
適切な帳簿管理と証憑書類の保存は、税務調査に備えるための基本です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 日次・月次の記帳を徹底する
取引が発生したら速やかに記帳し、月次で帳簿を締めることで、記帳漏れや誤りを防ぎます。特に以下の点に注意しましょう。
・ 現金出納帳の日次記帳
・ 売掛金・買掛金の管理
・ 月次試算表の作成と確認
2. 証憑書類を適切に保存する
取引の証拠となる証憑書類は、適切に保存することが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
・ 請求書や領収書は日付順に整理する
・ 電子データの場合は電子帳簿保存法の要件を満たす
・ 重要な契約書や稟議書は別途保管する
3. 現金取引を最小限にする
現金取引は証拠が残りにくいため、可能な限り銀行振込やクレジットカードなどの記録が残る方法で取引を行いましょう。やむを得ず現金取引を行う場合は、以下の点に注意します。
・ 領収書を必ず受け取る
・ 現金出納帳に詳細を記録する
・ 定期的に現金残高を確認する
決算・申告の正確性の確保
決算・申告の正確性を確保することは、税務調査のリスクを低減するために重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 決算前の自主点検を行う
決算前に以下のような自主点検を行い、誤りや漏れがないかを確認しましょう。
・ 売上や仕入の計上漏れがないか
・ 経費の計上に誤りがないか
・ 在庫の評価は適正か
・ 減価償却の計算は正確か
2. 税理士のチェックを受ける
可能であれば、決算・申告前に税理士のチェックを受けることをおすすめします。税理士は以下のような点をチェックします。
・ 会計処理の適正性
・ 税法上の取扱いの適正性
・ 申告書の記載内容の正確性
・ 税額計算の正確性
3. 申告内容の一貫性を保つ
毎年の申告内容に一貫性を持たせることも重要です。以下のような点に注意しましょう。
・ 会計処理の方法を安易に変更しない
・ 経費の計上基準を一貫させる
・ 特殊な取引の処理方法を文書化しておく
税務上のグレーゾーンを避ける
税務上のグレーゾーンは、税務調査のリスクを高める要因となります。以下のポイントに注意しましょう。
1. 過度な節税策を避ける
法的に問題はなくても、過度な節税策は税務署の注目を集めやすくなります。以下のような点に注意しましょう。
・ 租税回避と思われる取引を避ける
・ 実態のない取引や名義借りを行わない
・ 過度な役員報酬の操作を避ける
2. 個人と法人の区分を明確にする
個人と法人の区分が曖昧だと、税務調査のリスクが高まります。以下のような点に注意しましょう。
・ 役員の個人的な経費を会社で負担しない
・ 役員への貸付金や借入金は適正な金利を設定する
・ 役員との資産の売買は適正な価格で行う
3. 関連会社との取引を適正に行う
関連会社との取引は、税務調査で特に注目される項目です。以下のような点に注意しましょう。
・ 取引価格は市場価格を基準にする
・ 取引の経済的合理性を確保する
・ 取引の証憑書類を適切に保存する
税理士との連携強化
税理士との連携を強化することで、税務調査のリスクを低減することができます。以下のポイントに注意しましょう。
1. 定期的な相談を行う
税理士との定期的な相談を通じて、税務上の問題点を早期に発見・解決することが重要です。以下のような点について相談しましょう。
・ 会計処理や税務処理の適正性
・ 税制改正への対応
・ 特殊な取引の処理方法
・ 税務リスクの評価と対策
2. 税務上の判断を文書化する
税務上の判断が必要な場合は、その根拠や経緯を文書化しておくことをおすすめします。以下のような点に注意しましょう。
・ 税理士の見解を文書で残す
・ 税務署への事前相談の内容を記録する
・ 特殊な取引の処理方法を文書化する
3. 税務調査の経験を共有する
過去の税務調査の経験を税理士と共有し、今後の対策に活かすことも重要です。以下のような点について共有しましょう。
・ 指摘された項目とその対応
・ 調査官の注目点や質問内容
・ 調査結果と修正申告の内容
税務関連の最新情報の収集
税法や税務行政は常に変化しているため、最新情報を収集することが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 税制改正の情報を収集する
毎年行われる税制改正の情報を収集し、自社への影響を把握しましょう。以下のような情報源を活用します。
・ 国税庁のウェブサイト
・ 税理士からの情報提供
・ 税務関連の専門誌や書籍
・ セミナーや研修会
2. 税務通達や裁判例を確認する
税法の解釈や適用に関する税務通達や裁判例を確認することも重要です。以下のような点に注意しましょう。
・ 自社の事業に関連する税務通達の確認
・ 類似の事例に関する裁判例の確認
・ 税務当局の見解の変化の把握
3. 業界団体の情報を活用する
業界団体が提供する税務関連の情報を活用することも有効です。以下のような情報を収集しましょう。
・ 業界特有の税務上の取扱い
・ 業界内での税務調査の傾向
・ 業界標準の会計処理や税務処理
税務調査が入った場合の対処法
税務調査が実際に入った場合、適切に対処することが重要です。ここでは、税務調査が入った場合の具体的な対処法について解説します。
冷静な対応と協力姿勢の重要性
税務調査官に対しては、冷静な対応と協力姿勢を示すことが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 礼儀正しく対応する
税務調査官に対しては、礼儀正しく対応することが基本です。敵対的な態度や非協力的な姿勢は、調査の長期化や詳細な調査につながる可能性があります。
2. 質問には正確に答える
税務調査官からの質問には、正確かつ簡潔に答えるよう心がけましょう。わからないことは「わからない」と正直に伝え、後で確認して回答するようにします。
3. 必要な書類を速やかに提出する
税務調査官から求められた書類は、速やかに提出するよう心がけましょう。書類の提出が遅れると、調査の長期化や不信感を招く可能性があります。
4. 調査の進行状況を把握する
調査の進行状況を把握し、どのような点が注目されているかを理解することも重要です。調査官の質問内容や確認している書類から、調査の焦点を推測しましょう。
追徴課税が発生した場合の対応
税務調査の結果、追徴課税が発生した場合は、以下のように対応しましょう。
1. 指摘内容を正確に理解する
税務調査官からの指摘内容を正確に理解することが重要です。不明な点があれば、遠慮なく質問して明確にしましょう。
2. 修正申告の内容を確認する
修正申告を行う場合は、その内容を十分に確認しましょう。特に以下の点に注意します。
・ 追加納税額の計算が正確か
・ 加算税や延滞税の計算が正確か
・ 修正の対象となる期間が適切か
3. 今後の対策を検討する
同様の指摘を受けないよう、今後の対策を検討することも重要です。以下のような点について検討しましょう。
・ 会計処理や税務処理の見直し
・ 内部統制の強化
・ 社内教育の実施
不服申立ての方法と流れ
税務調査の結果に納得できない場合は、不服申立てを行うことができます。以下の流れで対応しましょう。
1. 再調査の請求
更正処分などを受けた日の翌日から3か月以内に、処分を行った税務署長に対して再調査の請求を行うことができます。
2. 審査請求
再調査の請求の結果に納得できない場合、または再調査の請求をせずに直接審査請求を行う場合は、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができます。
3. 訴訟
審査請求の結果に納得できない場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、慎重に判断する必要があります。
再調査を避けるための改善策
税務調査後は、再調査を避けるための改善策を実施することが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
1. 指摘事項の改善
税務調査で指摘された事項については、速やかに改善することが重要です。以下のような点に注意しましょう。
・ 会計処理や税務処理の見直し
・ 帳簿管理や証憑書類の保存方法の改善
・ 内部統制の強化
2. 社内教育の実施
税務調査で指摘された事項について、社内教育を実施することも重要です。以下のような点について教育を行いましょう。
・ 正しい会計処理や税務処理の方法
・ 証憑書類の重要性と保存方法
・ 税法の基本的な知識
3. 税理士との連携強化
税務調査後は、税理士との連携をさらに強化することをおすすめします。以下のような点について相談しましょう。
・ 指摘事項の改善方法
・ 今後の税務リスクの評価と対策
・ 定期的なチェック体制の構築
よくある質問と回答
税務調査に関するよくある質問とその回答をまとめました。
税務調査の通知はどのくらい前に来るのか?
任意調査の場合、通常は調査の1週間~10日前に税務署から電話や文書で通知があります。ただし、強制調査(査察)の場合は事前通知なしに突然訪問することがあります。
税務調査の所要時間はどのくらいか?
税務調査の所要時間は、法人の規模や調査の内容によって異なります。一般的には以下のような目安があります。
・ 小規模法人1~2日
・ 中規模法人3~5日
・ 大規模法人1週間~数か月
ただし、調査の過程で問題が発見された場合は、調査期間が延長されることがあります。
税務調査の範囲はどこまでか?
税務調査の範囲は、調査の種類や目的によって異なります。一般的には以下のような範囲が対象となります。
・ 法人税原則として直近3事業年度分
・ 消費税原則として直近3事業年度分
・ 源泉所得税原則として直近3年分
ただし、重大な問題が発見された場合は、最大7年前までさかのぼって調査される可能性があります。
税務調査を拒否することはできるのか?
任意調査の場合、法的には拒否することも可能ですが、実務上はあまり推奨されません。調査を拒否すると、以下のようなリスクがあります。
・ 強制調査(査察)に移行する可能性がある
・ 税務署との関係が悪化する
・ より詳細な調査の対象になる可能性がある
特別な理由がない限り、調査に協力することが望ましいでしょう。
税務調査で追徴課税された場合の加算税は?
追徴課税された場合、以下のような加算税が課される可能性があります。
・ 過少申告加算税申告漏れが単純なミスによるもので、期限内に申告している場合に課される加算税。税額の10%(期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)。
・ 無申告加算税申告書を提出していない場合に課される加算税。税額の15%(50万円を超える部分については20%)。
・ 重加算税故意に所得を隠ぺいしたり、虚偽の申告をしたりした場合に課される加算税。過少申告の場合は税額の35%、無申告の場合は税額の40%。
これらの加算税に加えて、本来納付すべき期限から実際に納付する日までの期間に応じて、延滞税も課されます。
まとめ
本記事では、法人に対する税務調査の確率や、税務署が調査に入る条件について詳しく解説しました。以下に、重要なポイントをまとめます。
税務調査に対する適切な心構え
税務調査は、法人にとって避けて通れないものです。しかし、適切な心構えを持つことで、調査をスムーズに進め、余計なトラブルを回避することができます。
・ 税務調査は敵対するものではなく、適正な納税を確認するためのものと捉える
・ 誠実かつ協力的な態度で対応する
・ 必要な書類や資料を適切に準備する
・ 税理士のサポートを受ける
日常的な税務管理の重要性
税務調査に備えるためには、日常的な税務管理が重要です。以下のポイントに注意しましょう。
・ 適切な帳簿管理と証憑書類の保存
・ 決算・申告の正確性の確保
・ 税務上のグレーゾーンを避ける
・ 税務関連の最新情報の収集
専門家との連携の必要性
税務調査に適切に対応するためには、税理士などの専門家との連携が不可欠です。以下のポイントに注意しましょう。
・ 税理士との定期的な相談
・ 税務上の判断の文書化
・ 税務調査時の税理士の同席
・ 税務調査後の改善策の検討
税務調査は、適切な準備と対応を行うことで、そのリスクを最小限に抑えることができます。本記事が、皆様の税務調査対策の一助となれば幸いです。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、帳票書類を電子化してWeb上で送付できるシステムです。Web上だけでなく、状況に応じて郵送やFAXで送付することもできます。送付済みの帳票書類は電子帳簿保存法に対応した形での保存が可能です。