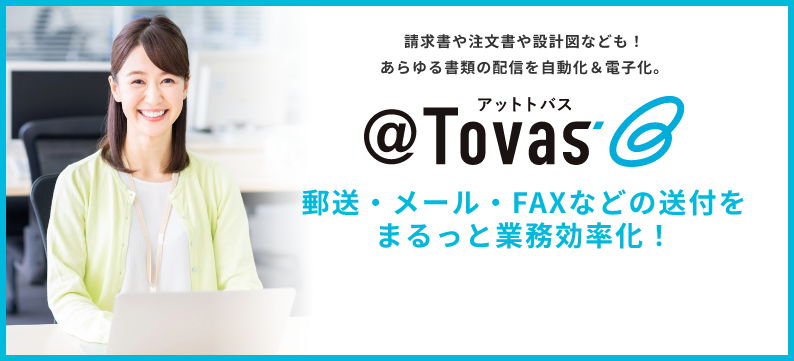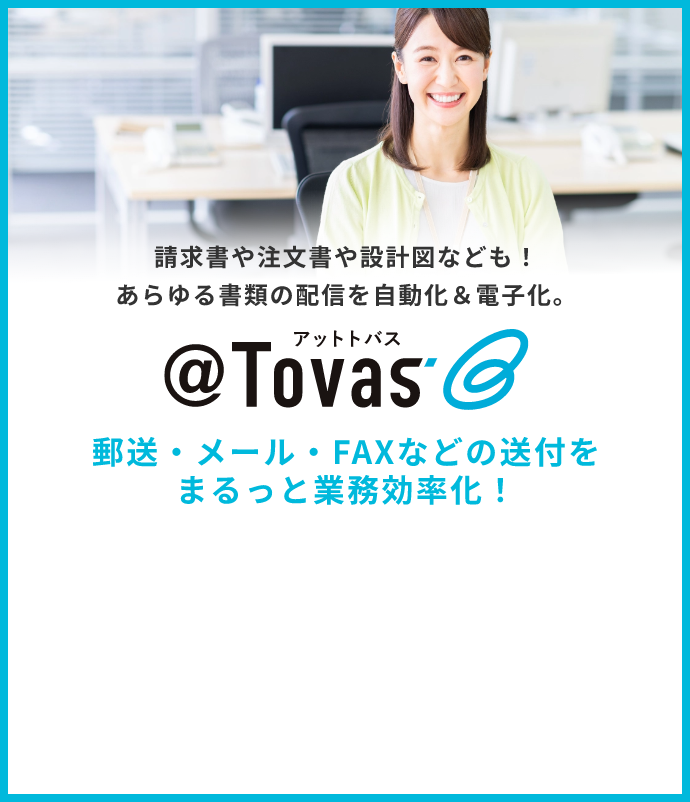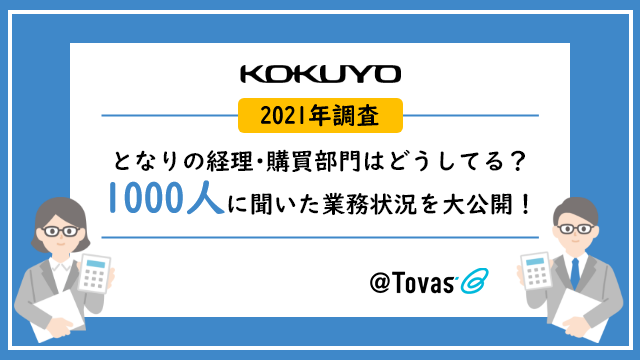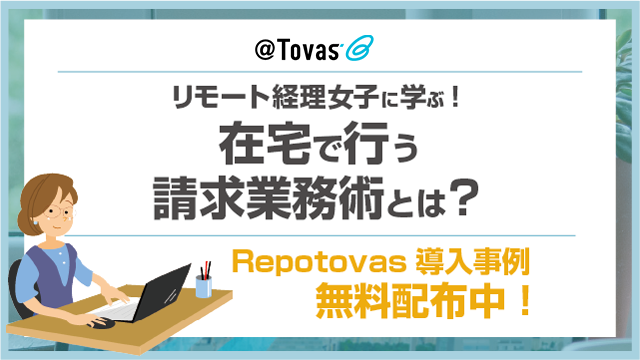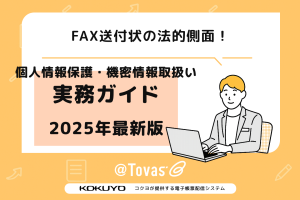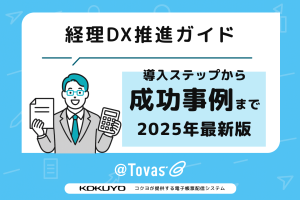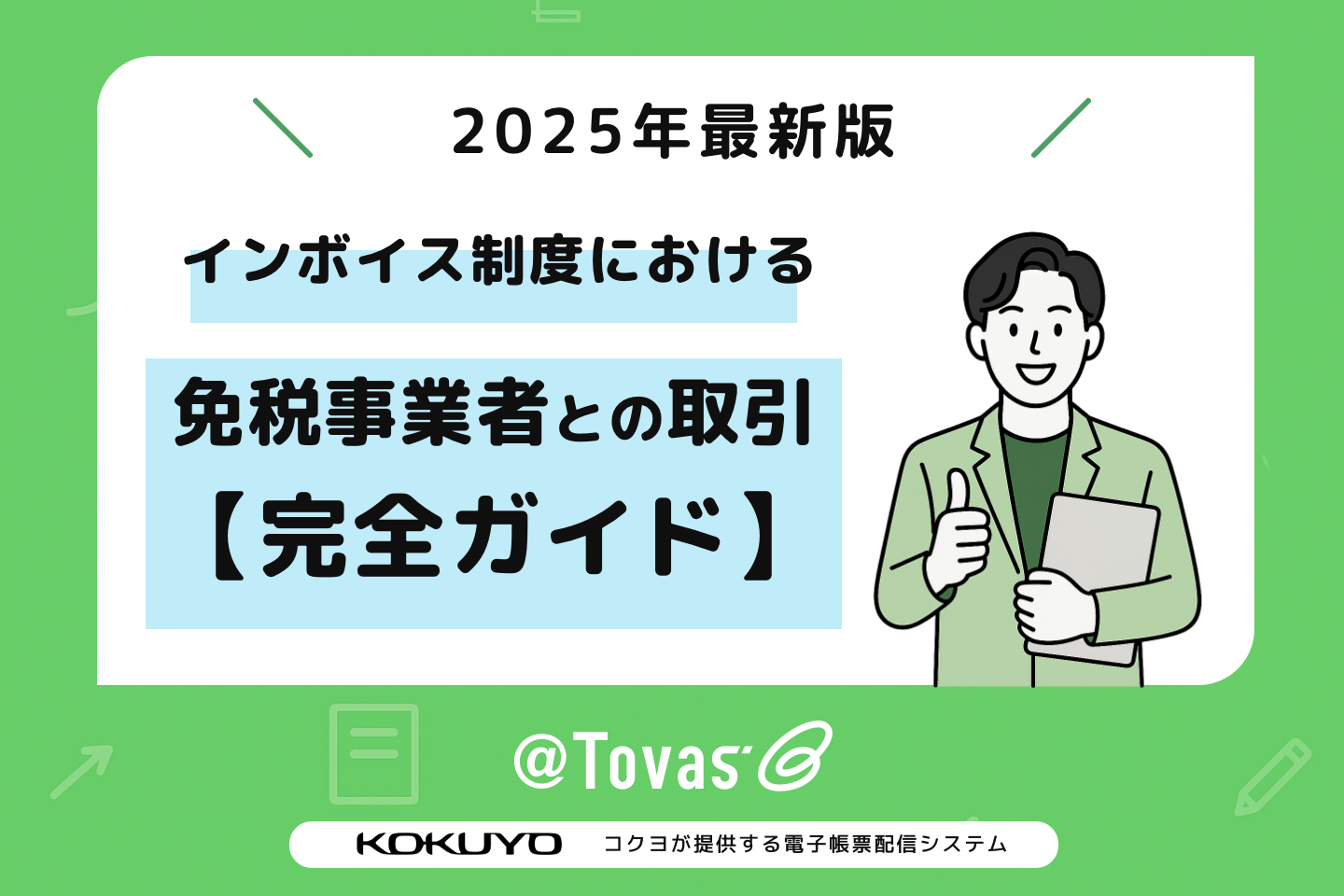
【実務ガイド】インボイス制度における免税事業者との取引完全ガイド(2025年最新版)
公開日:2025年4月22日 更新日:2026年1月6日
目次
はじめに
2023年10月1日に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、日本の消費税制度において大きな変革をもたらしました。この制度により、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。
この制度変更は、特に免税事業者(年間売上高1,000万円以下の事業者)とその取引先に大きな影響を与えています。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先である課税事業者は原則として仕入税額控除を受けられなくなります。これにより、免税事業者との取引継続や価格交渉など、様々な実務上の課題が生じています。
本記事では、インボイス制度における免税事業者との取引について、法的側面、実務対応、取引環境の整備など、多角的な視点から解説します。2025年時点での最新情報に基づき、課税事業者と免税事業者の双方にとって有益な情報を提供します。
インボイス制度と免税事業者の関係
免税事業者とは
免税事業者とは、基準期間(原則として前々年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者のことを指します。免税事業者は、消費税の納税義務が免除される一方で、課税仕入れに係る消費税額を控除することもできません。
インボイス制度導入前は、免税事業者からの仕入れであっても、一定の要件を満たす請求書等を保存することで、課税事業者は仕入税額控除を適用できました。しかし、インボイス制度の導入により、原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ、仕入税額控除を受けられなくなりました。
インボイス制度における免税事業者の位置づけ
インボイス制度において、免税事業者は以下のような位置づけとなります
1. インボイス発行事業者になれない免税事業者は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けることができません。ただし、課税事業者を選択することで、インボイス発行事業者になることは可能です。
2. インボイスを発行できない免税事業者は、適格請求書(インボイス)を発行することができません。ただし、これまでと同様に、インボイスに該当しない請求書や領収書等の発行は可能です。
3. 取引先が仕入税額控除を受けられない免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除を適用できません。ただし、経過措置により、2029年9月30日までは一定割合の控除が認められています。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先は原則として仕入税額控除を受けられませんが、経過措置により一定期間は部分的な控除が可能です。
免税事業者との取引における経過措置
経過措置の内容と期間
インボイス制度の導入による影響を緩和するため、免税事業者等からの仕入れについても、一定期間は仕入税額控除を部分的に認める経過措置が設けられています。
経過措置の内容は以下のとおりです
この経過措置により、免税事業者との取引を急に見直す必要はなく、段階的に対応を検討することが可能となっています。
経過措置適用の要件
経過措置を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります
1. 帳簿への記載事項
・ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
・ 課税仕入れを行った年月日
・ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
・ 課税仕入れに係る支払対価の額
・ 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(「80%控除対象」「50%控除対象」など)
2. 請求書等の保存要件
・ 区分記載請求書等と同様の記載事項を満たす書類の保存
・ 具体的には、以下の事項が記載された書類が必要
・ 書類の作成者の氏名または名称
・ 課税資産の譲渡等を行った年月日
・ 課税資産の譲渡等の内容
・ 税率ごとに区分して合計した対価の額
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
帳簿への記載事項と請求書等の保存要件を満たす必要があります。
経過措置の計算例
経過措置を適用した場合の仕入税額控除の計算例を示します。
【例1】2025年4月に免税事業者から10万円(税込)の商品を購入した場合
課税仕入れに係る消費税額 = 100,000円 ÷ 1.1 × 0.1 = 9,090円
控除可能額(80%控除) = 9,090円 × 80% = 7,272円
控除できない額 = 9,090円 – 7,272円 = 1,818円
【例2】2027年4月に免税事業者から10万円(税込)の商品を購入した場合
課税仕入れに係る消費税額 = 100,000円 ÷ 1.1 × 0.1 = 9,090円
控除可能額(50%控除) = 9,090円 × 50% = 4,545円
控除できない額 = 9,090円 – 4,545円 = 4,545円
同じ10万円(税込)の仕入れでも、経過措置の期間によって控除できる金額が異なります。
免税事業者との取引における法的留意点
独占禁止法・下請法上の留意点
インボイス制度の導入に伴い、課税事業者が免税事業者との取引を見直す際には、独占禁止法や下請法に抵触しないよう注意が必要です。公正取引委員会は、「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」を公表し、問題となり得る行為を明示しています。
独占禁止法上、問題となり得る行為
1. 取引拒絶単に免税事業者であることを理由として取引を拒絶すること
2. 対価の引下げ免税事業者であることを理由として、一方的に取引価格の引下げを行うこと
3. 買いたたき免税事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由として、通常支払われる対価より著しく低い対価での取引を要請すること
下請法上、問題となり得る行為
1. 買いたたき免税事業者である下請事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由として、通常支払われる対価より低い下請代金を不当に定めること
2. 減額免税事業者である下請事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由として、下請代金の額を減ずること
3. 取引条件の変更免税事業者である下請事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由として、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じること
取引拒絶、対価の引下げ、買いたたきなどの行為は法的問題となる可能性があります。
適正な価格交渉の進め方
免税事業者との取引価格の見直しを行う場合、以下のような点に留意して適正な価格交渉を進めることが重要です
1. 十分な協議の実施一方的な通知ではなく、十分な協議を行うこと
2. 合理的な根拠の提示価格見直しの必要性や根拠を明確に説明すること
3. 段階的な対応急激な価格変更ではなく、段階的に対応すること
4. 代替措置の検討価格以外の取引条件(納期、支払条件など)の見直しも含めて検討すること
5. 書面による合意協議の結果を書面で残し、双方が合意した内容を明確にすること
十分な協議、合理的な根拠の提示、段階的な対応などが重要です。
課税事業者側の実務対応
免税事業者の特定と管理
課税事業者は、取引先が免税事業者かどうかを特定し、適切に管理する必要があります。以下のような対応が考えられます
1. 取引先の登録状況の確認
・ 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録状況を確認
・ 取引先に登録番号の有無を直接確認
2. 取引先マスタの整備
・ 取引先マスタにインボイス発行事業者か否かの区分を追加
・ 経過措置の適用期間に応じた控除率(80%、50%)の管理
3. 定期的な更新
・ 取引先の登録状況を定期的に確認し、マスタ情報を更新
・ 新規取引先の登録時に確認プロセスを組み込む
取引先の登録状況の確認、取引先マスタの整備、定期的な更新が重要です。
仕入税額控除の計算と経理処理
免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の計算と経理処理は、以下のように行います
1. 仕入税額控除の計算
・ 適格請求書等がある課税仕入れ通常どおり全額控除
・ 適格請求書等がない課税仕入れ(免税事業者からの仕入れ)
・ 2023年10月~2026年9月仕入税額相当額 × 80%
・ 2026年10月~2029年9月仕入税額相当額 × 50%
2. 帳簿記載の例
・ 日付2025年4月1日
・ 取引先○○商事(免税事業者)
・ 取引内容事務用品購入
・ 金額110,000円(税込)
・ 税率10%
・ 消費税額10,000円
・ 控除区分80%控除対象
・ 控除額8,000円
3. 会計システムの設定
・ 免税事業者からの仕入れを識別するための勘定科目または補助科目の設定
・ 経過措置に対応した自動計算機能の活用
仕入税額控除の計算、帳簿記載、会計システムの設定が重要です。
取引先との関係維持のための対応策
免税事業者との取引関係を維持しながら、インボイス制度に対応するための対応策として、以下のような方法が考えられます
1. 価格調整の検討
・ 控除できない消費税分を考慮した価格調整
・ 段階的な価格調整による急激な変化の回避
2. 取引形態の見直し
・ 委託契約から請負契約への変更
・ 取引単位の見直し(少額特例の活用)
3. 発注方法の工夫
・ 少額特例(1取引あたり税込1万円未満)を活用した発注の分割
・ 経過措置期間中の発注の前倒しや集中
4. インボイス発行事業者への登録サポート
・ 登録手続きのサポート
・ 課税事業者になることのメリット・デメリットの説明
価格調整の検討、取引形態の見直し、発注方法の工夫、登録サポートなどが考えられます。
免税事業者側の実務対応
インボイス発行事業者になるかどうかの判断基準
免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかの判断は、以下のような要素を考慮して行うことが重要です
1. 取引先の状況
・ 主な取引先が課税事業者か消費者か
・ 取引先からの要請の有無
・ 取引先の業種・規模
2. 事業への影響
・ 売上への影響(取引継続の可能性)
・ 価格交渉の余地
・ 競合他社の動向
3. 税負担の変化
・ 課税事業者になった場合の納税額の試算
・ 簡易課税制度の適用可能性
・ 2割特例の適用可能性
4. 事務負担の増加
・ 消費税申告の事務負担
・ 帳簿・請求書等の保存義務
・ 会計ソフト導入などのコスト
取引先の状況、事業への影響、税負担の変化、事務負担の増加などを総合的に考慮して判断することが重要です。
免税事業者のままでいる場合の対応策
免税事業者のままでいる場合の対応策として、以下のような方法が考えられます
1. 取引先との関係強化
・ 自社の強み(品質、納期、専門性など)のアピール
・ 付加価値の向上による差別化
・ 長期的な取引関係の構築
2. 価格交渉の準備
・ 適正な価格交渉のための資料準備
・ 経過措置を踏まえた段階的な価格調整の提案
・ 価格以外の取引条件(納期短縮、品質向上など)の提案
3. 取引先の多様化
・ 消費者向けビジネスの強化
・ 新規取引先の開拓
・ 事業モデルの見直し
4. 相談窓口の活用
・ 公正取引委員会等の相談窓口の活用
・ 商工会議所や税理士などの専門家への相談
・ 業界団体等を通じた情報収集
取引先との関係強化、価格交渉の準備、取引先の多様化、相談窓口の活用などが考えられます。
インボイス発行事業者になる場合の手続きと留意点
免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の手続きと留意点は以下のとおりです
1. 登録申請手続き
・ 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出
・ 必要書類登録申請書、本人確認書類の写し
・ 申請方法e-Tax、郵送、税務署窓口
・ 登録申請から登録までの期間原則として1か月程度
2. 課税事業者選択届出書の提出
・ 免税事業者が課税事業者を選択する場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要
・ 提出期限課税事業者となる課税期間の初日の前日まで
3. 適格請求書(インボイス)の発行
・ 記載事項:登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額、消費税額等
・ 発行方法:紙、電子データ(PDFなど)
・ 発行時期:取引の都度または一定期間分をまとめて
4. 消費税申告の義務
・ 申告期限:個人事業者は翌年3月31日まで、法人は事業年度終了後2か月以内
・ 納税方法:現金納付、振替納税、振替納税
なお、振替納税(口座振替方式)は個人事業者のみ利用可能で、法人は利用できません。
・ 簡易課税制度の検討売上税額に一定のみなし仕入率を乗じて計算する簡易な方法
登録申請手続き、課税事業者選択届出書の提出、適格請求書の発行、消費税申告の義務などが発生します。
取引環境の整備に向けた取り組み
政府の取り組み
インボイス制度の導入に伴う免税事業者への影響を緩和するため、政府は以下のような取り組みを行っています
1. 経過措置の設定
・ 2023年10月~2026年9月仕入税額相当額の80%控除
・ 2026年10月~2029年9月仕入税額相当額の50%控除
2. 2割特例の創設
・ 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者が、インボイス発行事業者となった場合に、売上税額の2割を控除できる特例
・ 適用期間2023年10月~2026年9月
3. 相談窓口の設置
・ インボイスコールセンター 0120-205-553
・ 公正取引委員会相談窓口 03-3581-5471
・ 中小企業庁相談窓口 0570-028-045
4. 取引適正化に向けた取り組み
・ 公正取引委員会による「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」の公表
・ 国土交通省による「インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例」の公表
・ 経済産業省・中小企業庁による「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」の公表
経過措置の設定、2割特例の創設、相談窓口の設置、取引適正化に向けた取り組みなどが行われています。
業界団体の取り組み
インボイス制度に対応するため、各業界団体も以下のような取り組みを行っています
1. 情報提供・啓発活動
・ セミナー・説明会の開催
・ ガイドライン・マニュアルの作成
・ 会報誌等での情報発信
2. 相談窓口の設置
・ 会員企業からの相談対応
・ 専門家による個別相談会の実施
・ Q&A集の作成・公開
3. 取引適正化の推進
・ 業界内での取引ルールの整備
・ 適正な価格交渉のためのガイドライン策定
・ 優良事例の収集・共有
4. 行政との連携
・ 行政機関との意見交換
・ 業界の実情に応じた対応策の提言
・ 会員企業への情報伝達
情報提供・啓発活動、相談窓口の設置、取引適正化の推進、行政との連携などが行われています。
企業の社会的責任(CSR)の観点からの対応
インボイス制度への対応は、企業の社会的責任(CSR)の観点からも重要です。以下のような対応が考えられます
1. 取引先との共存共栄
・ 長期的な取引関係の維持・発展
・ 取引先の成長支援
・ 公正な取引慣行の確立
2. 中小企業・小規模事業者への配慮
・ 免税事業者への一方的な負担転嫁の回避
・ 段階的な対応による急激な変化の緩和
・ 取引条件の見直しにおける丁寧な協議
3. 透明性の確保
・ 取引条件の明確化
・ 価格交渉プロセスの透明化
・ 取引実態の適切な記録・保存
4. 社内体制の整備
・ 従業員への教育・啓発
・ 相談窓口の設置
・ コンプライアンス体制の強化
取引先との共存共栄、中小企業・小規模事業者への配慮、透明性の確保、社内体制の整備などが重要です。
インボイス制度と免税事業者に関するよくある質問(FAQ)
Q1 免税事業者との取引を継続する場合、どのような対応が必要ですか?
A1免税事業者との取引を継続する場合、以下の対応が必要です
・ 経過措置の適用(2026年9月までは80%、2029年9月までは50%の仕入税額控除)
・ 帳簿への「80%控除対象」「50%控除対象」などの記載
・ 区分記載請求書等と同様の記載事項を満たす請求書等の保存
・ 会計システムでの経過措置対応(控除率の設定など)
・ 取引先マスタでの免税事業者の識別・管理
Q2 免税事業者との価格交渉を行う際の留意点は何ですか?
A2免税事業者との価格交渉を行う際は、以下の点に留意することが重要です
・ 一方的な通知ではなく、十分な協議を行うこと
・ 価格見直しの必要性や根拠を明確に説明すること
・ 急激な価格変更ではなく、段階的に対応すること
・ 価格以外の取引条件(納期、支払条件など)の見直しも含めて検討すること
・ 協議の結果を書面で残し、双方が合意した内容を明確にすること
・ 独占禁止法・下請法に抵触しないよう注意すること
Q3 免税事業者がインボイス発行事業者になるメリット・デメリットは何ですか?
A3免税事業者がインボイス発行事業者になるメリット・デメリットは以下のとおりです
メリット
・ 取引先が仕入税額控除を受けられるため、取引継続・拡大の可能性が高まる
・ 価格交渉において不利な立場に立たされるリスクが軽減される
・ 2割特例の適用により、一定期間は税負担が軽減される(2026年9月まで)
・ 簡易課税制度を選択することで、事務負担を軽減できる可能性がある
デメリット
・ 消費税の納税義務が生じる
・ 消費税申告の事務負担が増加する
・ 帳簿・請求書等の保存義務が厳格化される
・ 会計ソフト導入などのコストが発生する可能性がある
Q4 少額特例とは何ですか?免税事業者との取引にどのように活用できますか?
A4少額特例とは、1取引あたり税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例です。免税事業者との取引において、以下のような場合に活用できます
・ 1取引あたり税込1万円未満の取引を個別に行う
・ 定期的な発注を月単位ではなく、週単位や日単位に分ける
・ 継続的な取引を個別取引として発注・請求する
ただし、少額特例の対象とするために、実態に反して意図的に発注や請求を分割する行為は、税務上問題となる可能性があるため、注意が必要です。
Q5 免税事業者との取引において、独占禁止法・下請法上問題となる行為とは具体的にどのようなものですか?
A5免税事業者との取引において、独占禁止法・下請法上問題となり得る具体的な行為は以下のとおりです
独占禁止法上の問題行為
・ 複数の事業者が共同して、免税事業者との取引を拒絶すること
・ 免税事業者であることのみを理由に取引を打ち切ること
・ 免税事業者に対して、一方的に著しく低い価格での取引を要請すること
下請法上の問題行為
・ 免税事業者である下請事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由に、一方的に下請代金を減額すること
・ 発注後に、免税事業者であることを理由に下請代金を減額すること
・ 免税事業者である下請事業者に対して、仕入税額控除ができないことを理由に、著しく低い下請代金を設定すること
まとめ
インボイス制度における免税事業者との取引は、経過措置の活用、適正な価格交渉、法的留意点の理解など、多角的な視点からの対応が求められます。
課税事業者側は、免税事業者の特定と管理、仕入税額控除の計算と経理処理、取引先との関係維持のための対応策を検討することが重要です。一方、免税事業者側は、インボイス発行事業者になるかどうかの判断、免税事業者のままでいる場合の対応策、インボイス発行事業者になる場合の手続きと留意点を理解することが必要です。
また、政府や業界団体の取り組みを活用し、企業の社会的責任(CSR)の観点からも適切な対応を行うことが求められます。
インボイス制度は2029年10月以降に完全実施となりますが、経過措置期間中に段階的に対応を進めることで、円滑な制度移行が可能となります。本記事の内容を参考に、自社の状況に合わせた適切な対応を検討し、計画的に準備を進めていただければ幸いです。
参考資料
1. 国税庁「インボイス制度とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kojin_01.htm
2. 公正取引委員会「インボイス制度関連コーナー」
https://www.jftc.go.jp/invoice/
3. 公正取引委員会「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」
https://www.jftc.go.jp/invoice/pdf/220210-3.pdf
4. 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa/index.htm
5. 中小企業庁「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/invoice_qa.html
—
免責事項本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する法的アドバイスではありません。記事内容の正確性には万全を期していますが、法規制や制度は変更される可能性があります。具体的な対応については、最新の公式情報を確認するか、専門家にご相談ください。