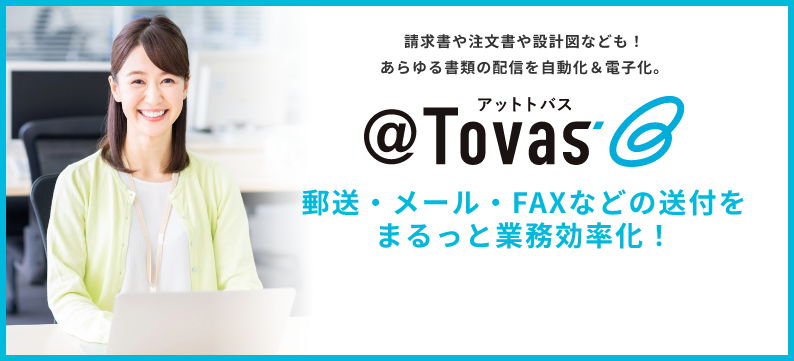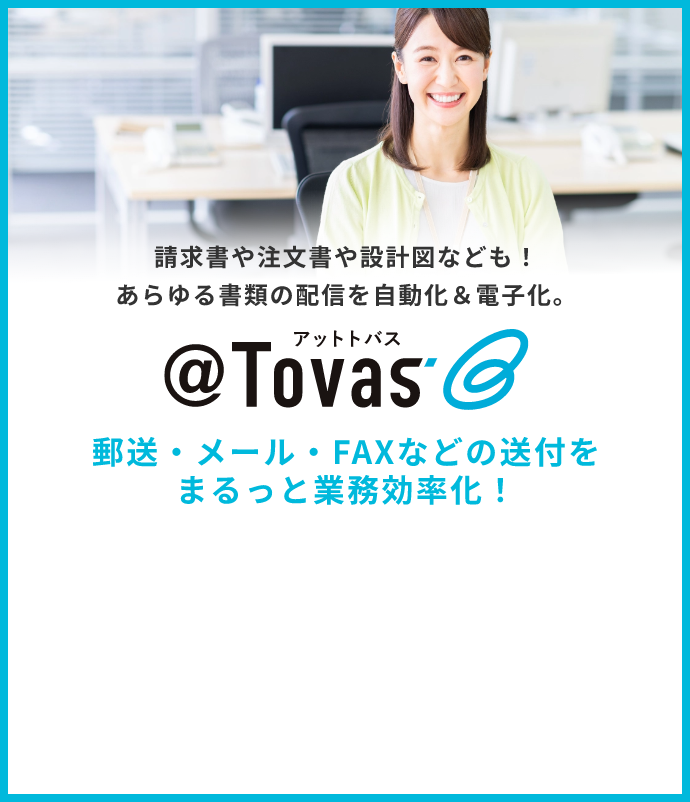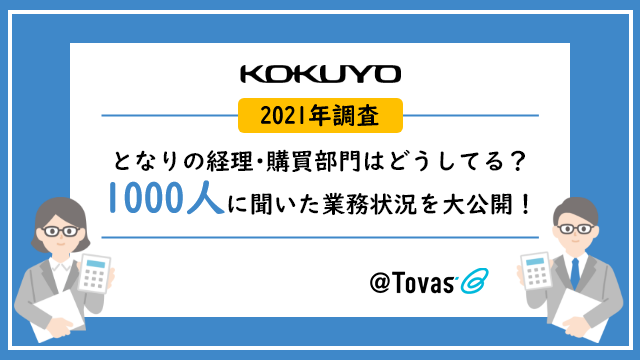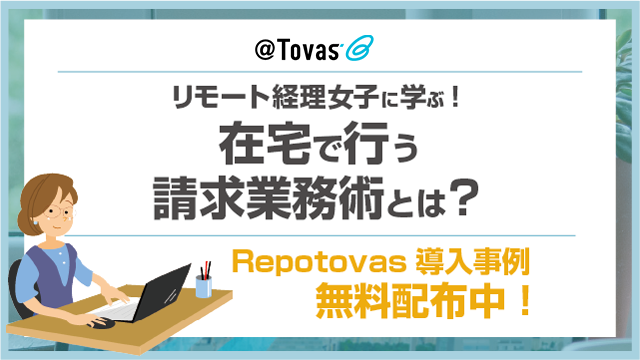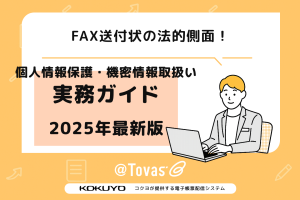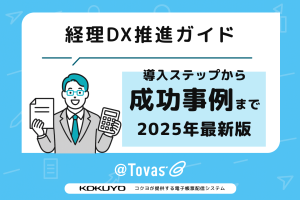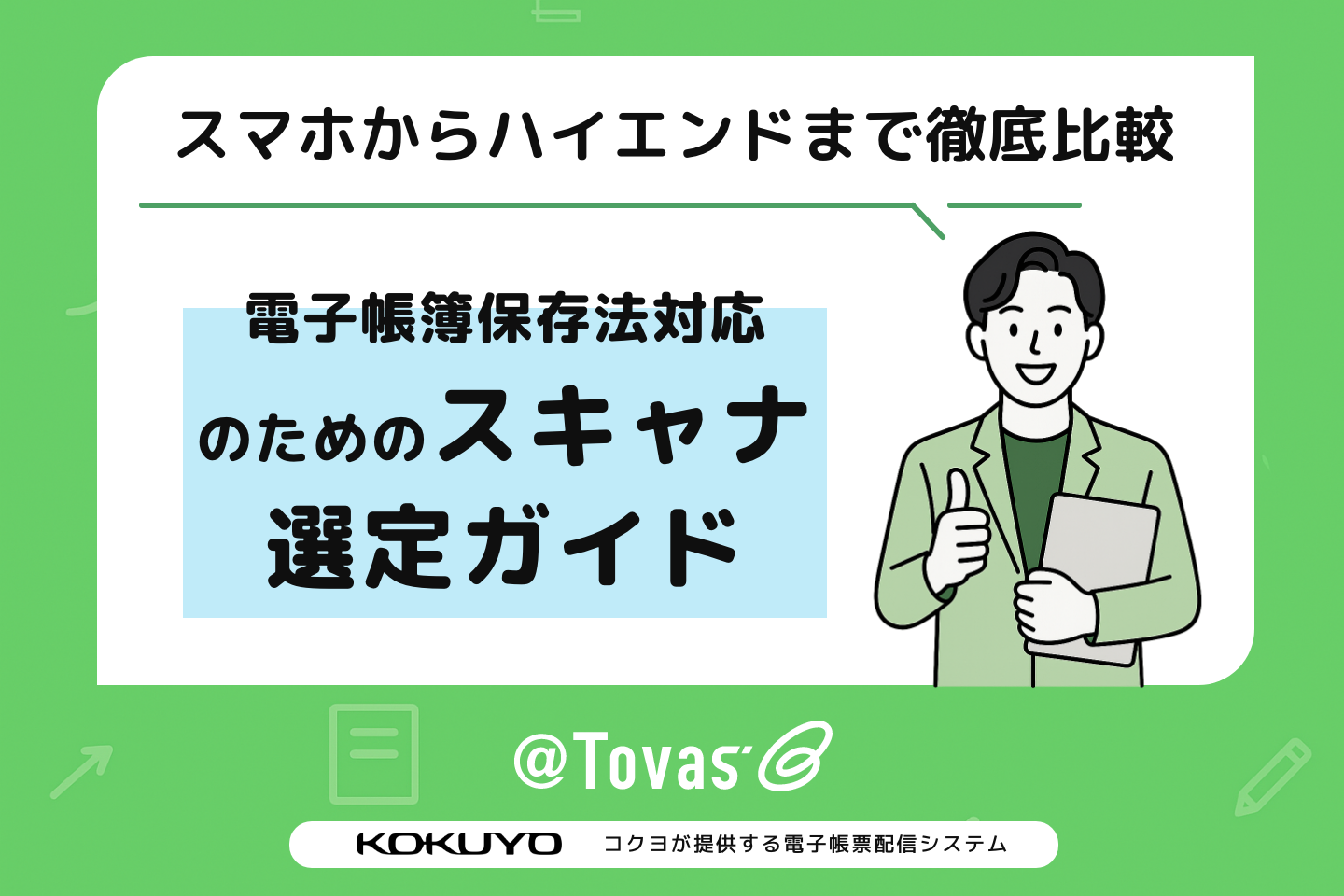
電子帳簿保存法対応のためのスキャナ選定ガイド:スマホからハイエンドまで徹底比較
公開日:2025年4月26日 更新日:2025年7月28日
目次
電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正や、2024年から本格運用が開始された電子取引データの電子保存義務化の流れを受け、多くの企業が書類の電子化やペーパーレス化に取り組んでいます。その中で、紙の書類を電子データ化する際に重要な役割を果たすのがスキャナです。適切なスキャナを選定することは、電帳法のスキャナ保存要件への対応はもちろん、業務効率化にも直結する重要な課題となっています。本記事では、電帳法に対応したスキャナ選定のポイントを詳しく解説します。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の基本要件
電帳法におけるスキャナ保存とは、紙で受け取った国税関係書類(請求書、領収書、契約書など)や、自社で作成したこれらの書類の控えをスキャンして電子データとして保存することを指します。スキャナ保存制度の利用は任意ですが、ペーパーレス化を推進する上で有効な手段の一つです。2022年1月の法改正により要件が緩和されましたが、依然としていくつかの重要な要件を満たす必要があります。
まず、スキャナ保存の対象となる書類には、取引先から受け取った請求書や領収書、自社が作成した書類の控えなどが含まれます。これらの書類をスキャンして保存する際には、以下の主要な要件を満たす必要があります。
1. 一定の解像度・階調での読み取り
・ 解像度が200dpi以上であること。
・ 赤・緑・青の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取ること。(※後述しますが、一般書類はグレースケールも可)
2. タイムスタンプの付与等(真実性の確保)
・ スキャンしたデータには、定められた期間内に、一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付与する必要があります。
・ または、訂正・削除の事実や内容を確認できるシステム(もしくは訂正・削除ができないシステム)で保存・管理する場合、タイムスタンプの付与は不要となります。
3. 入力期間の制限
・ 書類を受領または作成してからスキャナで読み取り、タイムスタンプを付与する(または訂正削除履歴が残るシステムに格納する)までの期間には、厳格な制限があります。
・ 早期入力方式書類を受領後、特に速やか(おおむね7営業日以内)に入力する方法。
・ 業務サイクル方式その業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)に入力する方法。この方式を採用する場合は、その業務サイクルの規程を定めておく必要があります。
・ この入力期間の遵守は非常に重要であり、遅れるとスキャナ保存の要件を満たさないことになるため、運用ルールで明確に定める必要があります。
4. ヴァージョン管理(訂正・削除履歴の確保)
・ タイムスタンプを付与しない場合、訂正または削除の事実及び内容を確認できるシステムで保存するか、そもそも訂正・削除ができないシステムで保存する必要があります。
5. 帳簿との相互関連性の確保
・ 保存されたスキャンデータと、関連する国税関係帳簿(仕訳帳など)の記録事項との間で、相互にその関連性を確認できるようにしておく必要があります。例えば、仕訳データから対応する請求書の画像データを、また請求書の画像データから関連する仕訳データを容易に特定できるようにします。
6. 見読可能性の確保
・ 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく必要があります。
7. 検索機能の確保
・ 「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を検索条件として設定できること。
・ 日付または金額については、範囲を指定して検索できること。
・ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること。
これらの要件を満たすスキャナを選定し、適切な運用体制を構築することが、電帳法に準拠したスキャナ保存を実現するための第一歩となります。
スキャナ選定の基本的な考え方
電帳法に対応したスキャナを選定する際には、上記の法的要件を満たすことは大前提として、自社の業務フローや取り扱う書類の特性に合わせた選定が重要です。基本的な考え方として、以下の点を押さえておきましょう。
まず、取り扱う書類の量と種類を把握することが重要です。日々大量の書類を処理する必要がある場合は、高速で連続スキャンが可能な自動給紙機能付きのドキュメントスキャナが適しています。一方、スキャンする書類の量が少ない、あるいは不定期に発生する程度であれば、フラットベッドスキャナやスタンドスキャナなど、より手軽なタイプでも十分かもしれません。
次に、スキャンする書類のサイズや形状も考慮すべき点です。A4サイズの定型書類が中心であれば標準的なスキャナで対応できますが、A3サイズの図面や契約書、不定形の領収書やレシートなど、様々なサイズや形状の書類を扱う場合は、それらに柔軟に対応できるスキャナ(例A3対応モデル、長尺モード搭載モデル、サイズの混在読み取り機能付きモデルなど)を選ぶ必要があります。
また、スキャナの設置場所や使用環境も重要な要素です。個人のデスクスペースが限られている場合はコンパクトなモデルが適していますし、複数の部署や拠点で共有して使用する場合はネットワーク対応モデル(有線LAN/無線LAN)が便利です。
さらに、長期的な運用コストも考慮すべきです。初期導入費用だけでなく、消耗品(ローラーやパッドなど)の交換費用や保守サービスにかかる費用などのランニングコストも含めた総所有コスト(TCO)で比較検討することが、賢明な投資判断につながります。
スキャナの種類と特徴
電帳法に対応するためのスキャナには、様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の業務に最適なタイプを選びましょう。
ドキュメントスキャナ
ドキュメントスキャナは、大量の書類を効率的にスキャンするために設計された専用機です。自動給紙機能(ADF:Automatic Document Feeder)を備えており、複数枚の書類をセットして連続でスキャンできます。両面同時スキャンが可能なモデルも多く、処理速度も高速なため、経理部門など大量の書類を扱う企業や部署に適しています。
例えば、1分間に30〜60枚程度(ppm pages per minute)のスキャン速度を持つモデルが一般的で、高速モデルになると1分間に100枚以上の処理能力を持つものもあります。また、OCR(光学文字認識)機能を内蔵、または連携ソフトウェアで提供するモデルも増えており、スキャンと同時にテキストデータ化することで、後の検索性を高めることができます。
ドキュメントスキャナの価格帯は、エントリーモデルで3万円前後から、ハイエンドモデルになると30万円以上するものまで幅広く存在します。導入コストは比較的高めですが、大量の書類を扱う場合は作業効率の大幅な向上によって、長期的には人件費を含めたコスト削減につながる可能性が高いです。
フラットベッドスキャナ
フラットベッドスキャナは、ガラス面に書類を原稿台にセットしてスキャンするタイプのスキャナです。書籍や雑誌のページ、製本された契約書、ホチキス留めされた書類、破損しやすい古い書類など、自動給紙(ADF)が難しい原稿のスキャンに適しています。
一般的に解像度が高く、細かい文字や印影、写真なども鮮明にスキャンできるのが特徴です。また、A3サイズに対応した大型モデルもあり、大きなサイズの図面やポスターなどのスキャンにも対応できます。
一方で、1枚ずつ手動で原稿をセットしてスキャンする必要があるため、大量の書類を処理する効率はドキュメントスキャナに劣ります。そのため、少量の書類や特殊な形状・状態の書類を扱う場合、あるいは高画質でのスキャンが求められる場合に適しています。
フラットベッドスキャナの価格帯は、一般的に1万円前後から10万円程度までと、ドキュメントスキャナに比べて手頃なモデルが多いです。ADFを併設した複合タイプのモデルもあり、両方のメリットを活かしたい場合に選択肢となります。
スタンドスキャナ(書画カメラ)
スタンドスキャナは、デスク上に設置したスタンドのアーム先端に取り付けられたカメラで、真上から書類を撮影するタイプのスキャナです。設置が簡単で、厚みのある書籍や立体物(サンプル品など)もそのままの状態でスキャン(撮影)しやすいのが特徴です。非破壊スキャナとも呼ばれます。
最近のモデルでは、高解像度のカメラを搭載し、電帳法の要件である200dpi以上の解像度を十分に満たしています。また、LEDライトを内蔵し、影を軽減する機能や、歪みを補正するソフトウェアを備えたモデルも多く、比較的鮮明な画像を得ることができます。
操作も直感的で、書類を置いてボタンを押すだけ、あるいはソフトウェア上でクリックするだけという簡単さが魅力です。リアルタイムでプレビュー画像を確認できるため、スキャン結果をすぐに確認・調整できます。
スタンドスキャナの価格帯は、エントリーモデルで1万円前後から、高機能モデルで5万円程度までと比較的手頃です。設置スペースも小さく済むため、個人のデスクや受付カウンターなど、スペースが限られている場所にも適しています。
ハンディスキャナ
ハンディスキャナは、本体を手で持って書類の上をなぞるようにしてスキャンする、小型で持ち運びが容易なスキャナです。主に領収書やレシート、名刺など、小さなサイズの書類のスキャンに適しています。
バッテリー駆動でWi-Fi接続が可能なモデルも多く、外出先や出張先での経費精算のための書類スキャンなどに活用できます。また、スマートフォンと連携して使用できるモデルもあり、スキャンしたデータをその場で確認し、クラウドストレージに直接アップロードすることも可能です。
ただし、スキャンできる幅が限られているため、A4サイズなどの大きな書類には不向きな場合があります(複数回に分けてスキャンし合成する機能を持つモデルもありますが、手間がかかります)。また、手動でスキャンするため、スキャン速度や精度は操作者のスキルに依存し、大量の書類を処理するのには効率が悪くなります。
ハンディスキャナの価格帯は、一般的に5,000円前後から2万円程度までと、比較的安価です。外出が多い営業担当者や、個人経費の精算が多い従業員に個人用として支給するケースなどに適しています。
電子帳簿保存法対応スキャナの選定ポイント
電帳法に対応したスキャナを選定する際には、前述の基本要件を満たすことに加えて、以下のポイントを具体的に考慮することが重要です。
1. 解像度とカラー要件(グレースケール含む)
電帳法では、スキャナの解像度が200dpi以上、カラースキャンの場合は赤・緑・青の各色256階調以上(24ビットカラー)であることが要件とされています。現在市販されているほとんどのスキャナはこの基本的な要件を満たしていますが、購入前に必ず仕様を確認しましょう。
特に、細かい文字やかすれた印影が含まれる書類、図面などを扱う場合は、より高い解像度(300dpi〜600dpi)を持つスキャナを選ぶことで、文字認識(OCR)の精度向上や視認性の向上が期待できます。ただし、解像度を高く設定すると、その分ファイルサイズが大きくなり、保存先のストレージ容量を圧迫したり、ネットワーク転送に時間がかかったりするデメリットもあるため、バランスを考慮する必要があります。
なお、契約書や領収書などの「重要書類」以外(例見積書、注文書、納品書などの「一般書類」)については、グレースケール(白黒階調)での保存も認められています。カラーに比べてファイルサイズを大幅に削減できるため、一般書類のスキャンが多い場合は、グレースケール保存に対応したスキャナやソフトウェアを選択し、運用ルールで使い分けることも有効な手段です。
2. スキャン速度と処理能力
日々の業務効率を考えると、スキャン速度と処理能力は非常に重要な選定ポイントです。1日あたりにスキャンする書類の枚数や、スキャン作業にかけられる時間を考慮し、適切な処理能力を持つモデルを選びましょう。
スキャン速度は、一般的に「ppm(pages per minute1分間にスキャンできる片面のページ数)」や「ipm(images per minute1分間にスキャンできる両面の画像数)」で表されます。両面スキャン機能が必要な場合はipmの数値を確認しましょう。
また、ドキュメントスキャナを選ぶ際は、自動給紙機能(ADF)の給紙容量(一度にセットできる枚数)も確認すべきポイントです。給紙容量が大きいほど、スキャン中に何度も紙を補充する手間が減り、連続して効率的に作業を進めることができます。
3. OCR機能の有無と精度
OCR(光学文字認識)機能は、スキャンした画像データからテキスト情報を抽出する技術です。電帳法の検索要件(「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索)を満たすためには、これらの情報を正確に抽出し、検索可能なデータとして保存する必要があるため、OCR機能は非常に重要です。
最近のスキャナでは、本体に高性能なOCRエンジンを内蔵しているモデルや、高精度なOCR処理が可能なソフトウェアが付属しているモデルが増えています。日本語の認識精度(特に手書き文字や特殊なフォントへの対応)、帳票のレイアウト自動認識機能、抽出したデータの編集・修正機能なども比較検討するとよいでしょう。スキャナ本体の機能だけでなく、連携する文書管理システム側で高度なOCR処理を行う選択肢もあります。
4. 連携ソフトウェアとの互換性
スキャナは単体で使用するだけでなく、スキャンしたデータを管理・保存・活用するためのソフトウェアと連携して使用することが一般的です。そのため、導入を検討している、あるいは既に利用している文書管理システムや会計ソフト、経費精算システム、クラウドストレージサービスなどとの連携性・互換性を確認することが重要です。
特に、タイムスタンプの付与(時刻認証業務認定事業者のサービスとの連携)、検索機能の実装、アクセス権限の管理、保存期間に応じた自動削除機能など、電帳法の要件を満たすための機能が、連携するシステム側でどのように提供されているかを確認しましょう。
スキャナメーカーが提供する標準ソフトウェアだけでなく、サードパーティ製のソフトウェアとの連携実績なども確認しておくと、よりスムーズな導入と運用が可能になります。API連携などが可能であれば、より柔軟なシステム構築が期待できます。
5. 耐久性と信頼性
業務で日常的に使用するスキャナには、安定した動作と長期間の使用に耐える耐久性・信頼性が求められます。一般的に、スキャナの耐久性は「推奨読み取り枚数(1日あたり)」や「耐久読み取り枚数(総読み取り枚数の目安)」、「月間デューティサイクル」といった指標で仕様に記載されています。
自社の想定するスキャンボリューム(例1日あたり何枚、月間何枚程度)に合わせて、十分な耐久性を持つモデルを選びましょう。耐久性の低いモデルで過度なスキャンを行うと、故障のリスクが高まり、結果的に業務が滞る可能性があります。
また、給紙機構の信頼性も重要です。紙詰まり(ジャム)や重送(複数枚の原稿が同時に給紙されること)を防止するための機能(例超音波センサーによる重送検知、ブレーキローラーやリタードローラーによる分離性能向上など)が搭載されているかどうかも確認しておくと、ストレスなく安定したスキャン作業が可能になります。
6. 保守サポートの充実度
業務用スキャナは、企業の重要な業務インフラの一部となるため、万が一の故障時に迅速に対応してもらえる保守サポート体制の充実度も重要な選定ポイントです。
メーカーや販売店が提供する保守サービスの内容(例センドバック修理、オンサイト修理)、対応時間、修理期間中の代替機の提供有無などを事前に確認しておきましょう。特に、基幹業務で使用する場合は、ダウンタイムを最小限に抑えるためのオンサイト保守や、複数年契約の保守パッケージを検討する価値があります。
また、消耗品(給紙ローラー、分離パッド、クリーニングキットなど)の交換頻度や費用、入手しやすさも、長期的な運用コストと利便性に影響します。ユーザー自身で消耗品の交換が可能か、あるいは専門業者によるメンテナンスが必要かも確認しておくとよいでしょう。
業種・規模別のスキャナ選定ガイド
業種や企業規模によって、最適なスキャナのタイプや求められる機能は異なります。ここでは、代表的な業種・規模別のスキャナ選定のヒントを紹介します。
小規模事業者・個人事業主向け
スキャンする書類の量が比較的少なく、予算も限られることが多い小規模事業者や個人事業主の場合、コストパフォーマンスが重視されます。
・ おすすめタイプコンパクトなドキュメントスキャナ、A4フラットベッドスキャナ、スタンドスキャナ、スマートフォン連携可能なハンディスキャナ
・ 選定ポイント
・ 設置スペースを取らないコンパクトさ
・ 操作の簡単さ、分かりやすさ
・ 手頃な価格帯(1〜5万円程度)
・ 基本的な電帳法要件(解像度、階調)を満たしていること
・ クラウドストレージ連携機能(データ管理の容易化)
・ OCR/検索要件対応スキャナ付属ソフトのOCR機能や、連携する会計ソフト側の検索機能、あるいは低コストのクラウドOCRサービスを活用することも検討。
中小企業向け
ある程度の書類量があり、経理部門や総務部門など、特定の部署または複数の担当者がスキャナを利用することが想定される中小企業の場合、効率性と共有性がポイントになります。
・ おすすめタイプ中速〜高速(30-60ppm程度)のドキュメントスキャナ、ネットワーク対応モデル
・ 選定ポイント
・ 十分なスキャン速度とADF給紙容量
・ 両面同時スキャン機能
・ ネットワーク共有機能(有線/無線LAN)
・ ある程度の耐久性(推奨日次枚数)
・ 文書管理システムや基幹システムとの連携性
・ 信頼性の高いOCR機能(ソフトウェア含む)
・ 価格帯目安5万円〜20万円程度
大企業・多拠点企業向け
大量の書類を日常的に処理する必要があり、複数拠点での利用や、システム全体としての最適化・ガバナンスが求められる大企業の場合、処理能力、耐久性、管理性が重要になります。
・ おすすめタイプ高速・大容量(60ppm以上)のドキュメントスキャナ(プロダクションスキャナ)、高性能な複合機(MFP)のスキャン機能活用
・ 選定ポイント
・ 非常に高いスキャン速度と大容量ADF
・ 高い耐久性と信頼性(連続運転、重送検知・防止機能)
・ 集中管理機能(複数台のスキャナ設定、利用状況監視など)
・ 高度な画像処理機能(傾き補正、白紙除去、文字向き自動判定など)
・ 文書管理システム、ワークフローシステムとの高度な連携
・ 充実した保守サポート体制(オンサイト保守推奨)
・ システム構築スキャナ単体ではなく、文書管理システム全体の一部として、セキュリティポリシーや運用ルールと合わせて導入・設計することが不可欠。
業種別の特徴と対応
さらに、業種特有の書類や業務フローに合わせて、以下のような点も考慮するとよいでしょう。
小売業・飲食業
・ 特徴大量のレシート、伝票、納品書など、小型・不定形の書類が多い。店舗での利用も想定。
・ 選定ポイントレシートなど小型書類の安定した給紙性能、コンパクトさ、簡単な操作性(ワンタッチスキャンなど)、POSシステムや店舗管理システムとの連携。
製造業・建設業
・ 特徴A3サイズの図面、仕様書、現場帳票など、大判や特殊な用紙を扱うことがある。現場での利用も想定。
・ 選定ポイントA3対応(フラットベッド or ADF)、長尺モード、堅牢性、防塵・防滴性能(現場利用の場合)、CADデータ連携など。
医療・福祉業
・ 特徴診療報酬明細書(レセプト)、カルテ、処方箋など、機密性の高い個人情報を扱う。定型・非定型の書類が混在。
・ 選定ポイント高度なセキュリティ機能(データ暗号化、アクセス制御)、医療用規格への対応、レセプトOCR機能、電子カルテシステムとの連携、プラスチックカード(保険証など)のスキャン対応。
スキャナ導入後の運用ポイント
適切なスキャナを選定し導入しただけでは、電帳法のスキャナ保存要件を継続的に満たし、業務効率化の効果を十分に得ることはできません。適切な運用体制を整備し、それを維持していくことが極めて重要です。
社内規程の整備
まず、スキャナ保存に関する社内規程(事務処理規程)を明確に定め、関係者に周知徹底することが不可欠です。最低限、以下のような内容を規定しておきましょう。
・ スキャナ保存の対象となる書類の範囲と種類
・ スキャン作業の担当部署、担当者、責任者
・ 書類の受領から入力(スキャン、タイムスタンプ付与等)までの具体的な手順と期限(入力期間制限の遵守ルール)
・ スキャン時の解像度、階調、ファイル形式などの設定基準
・ スキャン画像の品質チェック方法と基準(読み取れない場合の対処法含む)
・ タイムスタンプの付与方法とタイミング(利用する場合)
・ 訂正・削除の履歴確保に関するルール(タイムスタンプを利用しない場合)
・ 電子データのファイル命名規則、保存場所(フォルダ構成など)
・ 帳簿との相互関連性を確保するための具体的な方法
・ 電子データの保存期間と廃棄方法
・ 電子データの定期的なバックアップ方法
・ アクセス権限の設定・管理方法
・ 不正アクセスや改ざんを防止するためのセキュリティ対策
これらの規程は、電帳法の要件を満たすだけでなく、業務の標準化、担当者変更時の引き継ぎ、内部統制の強化にも役立ちます。
教育・トレーニング
新しいスキャナの導入や運用ルールの変更に伴い、担当者への適切な教育・トレーニングを実施することが重要です。特に、スキャン作業を実際に行う従業員には、以下のような内容を理解してもらう必要があります。
・ スキャナの基本的な操作方法、各種設定の意味
・ 電帳法のスキャナ保存要件の概要(特に解像度、入力期間、検索要件など)
・ 社内規程で定められた具体的な作業手順
・ 書類の前処理(ホチキスやクリップの除去、付箋の取り扱い、折れやシワの修正など)の重要性
・ スキャン画像の品質チェックポイント(傾き、欠け、文字の潰れ、裏写りなど)
・ OCR処理を依頼する場合の注意点(読み取りやすいスキャン品質の確保など)
・ ファイル名の付け方、保存先フォルダのルール
・ エラー発生時の基本的な対処方法と報告・相談ルート
定期的な研修の実施や、分かりやすいマニュアル(手順書)の整備などを通じて、スキャン作業の品質と効率を維持・向上させることが求められます。
定期的な監査とメンテナンス
スキャナ保存の運用が開始された後も、定期的にその運用状況が適切に行われているかを監査(自己チェック)することが重要です。これにより、問題点の早期発見と是正、継続的な法令遵守が可能になります。監査項目としては、以下のような点が考えられます。
・ 入力期間制限が遵守されているか(タイムスタンプの時刻やシステムログで確認)
・ スキャン画像の品質が規定の基準を満たしているか(ランダムサンプリングによる目視確認)
・ タイムスタンプが適切に付与されているか(有効性の検証)
・ 訂正・削除履歴が適切に記録・管理されているか
・ 検索機能が要件通りに動作するか(実際に検索して確認)
・ 帳簿との相互関連性が確保されているか(相互に辿れるか確認)
・ 電子データのバックアップが計画通りに実施されているか
・ アクセス権限が適切に設定・管理されているか
・ 社内規程からの逸脱がないか
また、スキャナ本体の定期的なメンテナンスも、安定した運用のためには欠かせません。読み取りガラス面やローラー部分の清掃、消耗品(給紙ローラー、分離パッドなど)の適切なタイミングでの交換などをメーカーの推奨に従って行うことで、スキャン品質の低下や紙詰まり、故障のリスクを低減できます。
まとめ:最適なスキャナ選定で電子帳簿保存法対応と業務効率化を両立
電帳法に対応したスキャナ選定は、単に法令遵守のためだけでなく、ペーパーレス化による業務効率化や生産性向上を実現するための重要な投資と捉えるべきです。自社の業務特性、取り扱う書類の量・種類、予算、将来的な拡張性などを総合的に考慮し、最適なスキャナを選定することが成功の鍵となります。
解像度やカラー要件、入力期間制限、検索機能といった法的要件を満たすことは大前提ですが、それに加えて、スキャン速度、処理能力、OCR機能の精度、連携ソフトウェアとの互換性、耐久性と信頼性、そして保守サポートの充実度など、実用面での多角的な視点で比較検討することをお勧めします。
そして、忘れてはならないのが、スキャナ導入後の運用体制の構築と維持です。明確な社内規程の整備、担当者への十分な教育・トレーニング、そして定期的な運用状況の監査とスキャナ本体のメンテナンスを通じて、継続的に適切なスキャナ保存を行うことが求められます。
電帳法への対応は、一部の企業にとっては負担と感じられるかもしれませんが、これをデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、データ活用による新たな価値創造を目指す好機と捉えることもできます。適切なスキャナ選定と運用体制の整備を通じて、法令遵守と業務効率化を両立させ、企業競争力の強化につなげていきましょう。
参考資料
1. 国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」(パンフレット等)
2. 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」
3. 一般財団法人日本データ通信協会「タイムビジネス認定センター」
4. 一般社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」等