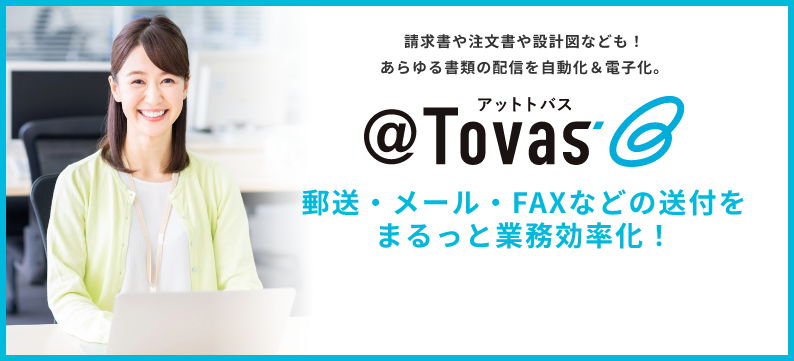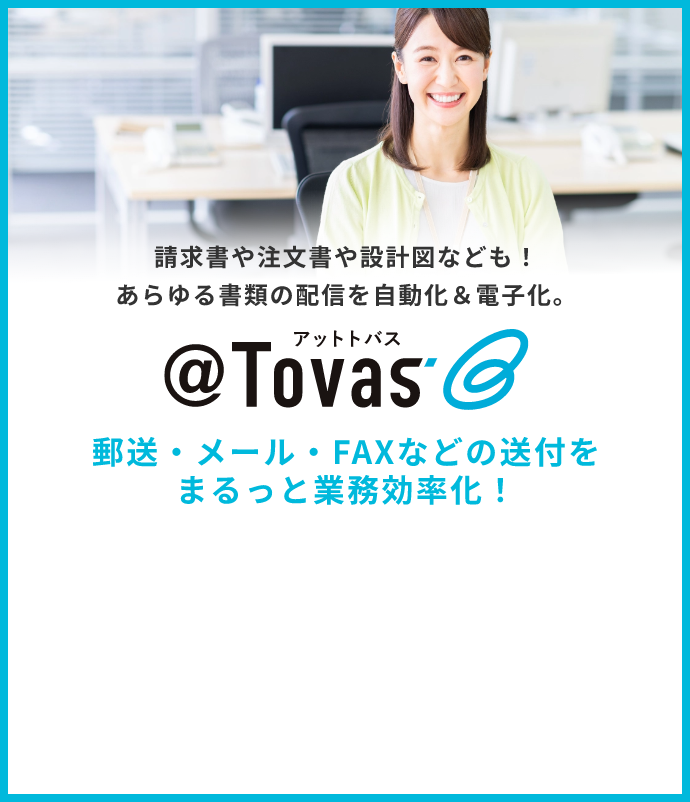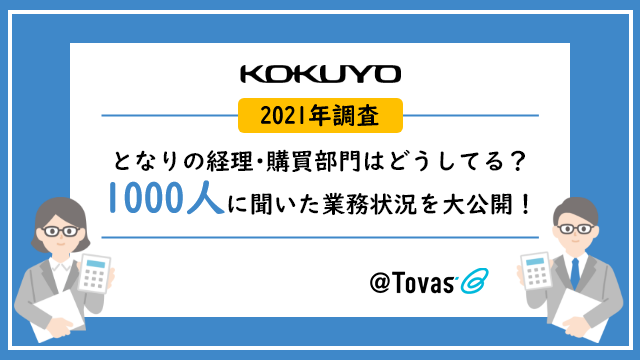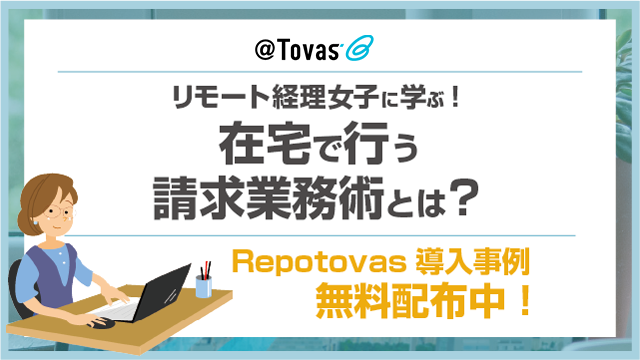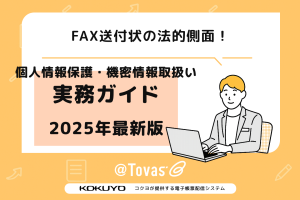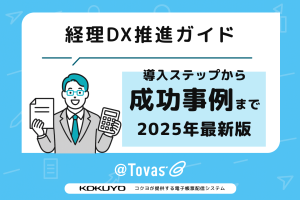FAXをAPI連携で自動送信 メリットと連携種類を解説【2025年最新版】
公開日:2025年5月12日 更新日:2025年9月3日
目次
「大量の帳票をFAXで送信しなければならない」
送信先の番号を一つ一つ入力し、ミスが起きないように送る作業には大きな負担がかかるもの。
そんな課題を解決する手段の一つが、「FAXのAPI連携による自動送信サービス」です。
2025年は電子帳簿保存法の完全施行年であり、帳票の電子化と効率的な管理がますます重要になっています。本記事では、
・FAXの送信作業に不便を感じている方
・作業の効率化を目指して自動送信サービスの導入を検討している方
に向けて、FAXのAPI連携の概要と導入のメリット、そして連携の種類などについて詳しく解説します。
API連携とは

API(Application Programming Interface)連携とは、異なるソフトウェアやシステム間でデータなどをやり取りするための仕組みです。API連携を利用することで、異なるアプリケーション間でシームレスに情報を交換できるため、既存のシステムを活用しながら必要な機能を利用できます。既存のソフトウェアを機能拡張させるようなイメージです。
専用のシステムと接続だけすればいい、すなわち自社でゼロから専用のサーバーを用意したり、ゼロからシステムを開発したりといったコストがかからないため、少ない工数でスピーディーに機能を実装したい場合に有効な手段です。
今回のテーマであるFAXのAPI連携では、社内の業務システムや基幹システムと自動送信サービスを接続することで、企業で保有する送信先リストや帳票などのデータを連携し、自動的にFAXの送受信を行うことが可能になります。
自社でゼロからプログラムを開発しなくても、既存の基幹システムなどを用いて自動化できるため、FAX業務の自動化を進めたいという課題に対して非常に効率的なアプローチです。
2025年3月6日からは、コクヨの電子帳票配信システム「@Tovas」と、アステリア株式会社提供のデータ連携ツール「ASTERIA Warp」とのシームレスな連携を実現する「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」が提供開始され、多様な基幹システムとの連携が容易になりました[※1]。
FAXをAPI連携するメリット

FAXの送信作業をAPI連携で自動化する場合、作業時間を短縮できるというほかにもさまざまなメリットがあります。
メリット① 業務効率の向上
FAX自動送信サービスの導入により、これまで手作業で一件ずつFAXを送信していた場合に比べ、送信業務を自動化することで時間と労力を大幅に削減できます。
さらに、大量のFAXを一括で送信することも容易になるため、発注書や請求書などの帳票類を毎月FAXで送付している企業や、PRとして大量の宛先にFAXを送る企業などでは、特に恩恵が大きいといえるでしょう。
2025年4月17日からは、コクヨの「@Tovas」とYoom株式会社提供のハイパーオートメーションツール「Yoom」との連携も開始され、クラウドサービスから出力されるPDFファイルやマスタ情報を「Yoom」からノーコードで「@Tovas」へ連携することが可能になりました[※2]。
メリット② FAX回線・サーバーが不要
FAXの自動送信サービスを利用する場合、サービス側が保有しているFAX回線を利用するため、インターネット回線さえあればFAXを送信できます。自社でFAX専用の電話回線やサーバーなどを設置する必要がないため、FAXサーバーの入れ替えやリース切れのタイミングでAPI連携のサービスに切り替えるケースも増えています。
また、近年ではテレワークを導入する企業も増えていますが、インターネットFAXであれば自宅からでもFAXの送受信が可能です。FAXのためだけに出社する必要がなくなり、リモートワークを導入している企業には大きなメリットとなります。
さらに、大量のFAX回線数を保有しているサービスを選べば、膨大な量のFAXを高速で送信できたり、一部の回線で通信障害が発生した際にも安定して送信できたりと、自社で回線を管理するより優れた環境を利用できるのも利点の一つです。
メリット③ 管理コストの削減
送信作業を自動化することにより、FAX番号の入力ミスや送信忘れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。誤送信のリスクが大きく減るため、送付そのものにかかる時間だけではなく、宛先の確認作業にかかっていた負担も削減可能です。
また、前述の通りサーバー設置の必要がないため、リース費用やインクなどの消耗品費用といった本体の保守管理費用がかからず、さらにペーパーレス化の促進にも繋がります。
FAX送信にかかる業務時間が短くなることで、作業にあてていた人件費を削減できるのはもちろん、そのほかFAXにかかるさまざまなコストや運用リスクを低減できるのも大きなメリットです。
2025年5月13日からは、コクヨの「@Tovas」に帳票を「受け取る」機能が追加され、帳票の送受信機能を兼ね備えたサービスとして生まれ変わりました。これにより、帳票業務全体の効率化と人手不足の解消が実現できます[※3]。
メリット④ 送信状況をリアルタイムで確認可能
FAXを利用する上では、「送り先に届いていなかった」というトラブルがよくあるもの。自動送信サービスを利用すれば、FAXの送信状況を管理画面などからリアルタイムで確認できるため、送り先に届いていなかったという事態にもすぐ対処できます。
不達の原因も送信結果のデータから見直すことができ、その後の対応もスムーズに進めることができます。
送信結果の通知機能や、不達時の再送信機能などについては各サービスによって充実度が異なりますので、導入を検討する場合にはこうした利便性も判断材料にすると良いでしょう。
FAX自動送信におけるシステム連携の種類

2025年現在、各社でさまざまなFAXのシステム連携サービスが提供されていますが、その仕組みについてはいくつかの種類があります。ニーズに合わせて最適なサービスを選択しましょう。
API
自社で運用している基幹システムとクラウド上のFAXサービスをAPI連携することで、インターネット経由でFAXの送受信を行う方法です。SOAPやRESTなどのプロトコルが用意されていることが多く、一から機能を開発しなくても、企業が保有している帳票プログラムなど既存のシステムを利用しながら自動送信に対応できます。
また機能の柔軟性が高く、リアルタイムでの状況確認やスケジューリングといった機能が搭載されているサービスも多いため、このあと紹介するメールなどを使った連携に比べて、機能性の面では最も優れた手段です。
FAXの利用頻度や配信数が多い場合や、機能の充実したサービスを選びたいという場合にはAPIでの連携がおすすめです。
メール送信による連携
送信するデータをメールに添付してリクエストすることで、サービス側がメールを受信し、添付されているファイルをFAXとして送信してくれるという連携方法もあります。これは通常使用している既存のメールサーバーをそのまま使用するやり方で、特別なシステム開発などを必要としないため、ユーザー目線でも使いこなしやすく、APIに比べて簡単に実装できるのが特徴です。
一方で、ファイルの容量に制限があったり、送信結果をリアルタイムで把握することは難しかったりと、APIでの連携に比べて機能面は制限されます。
最小限の機能で、手軽に自動化を図りたいというニーズに適した連携方法といえるでしょう。
ファイル転送による自動送信
こちらはAPI接続とは異なる手段ですが、ファイルを所定のフォルダに配置することでFAXとして転送してくれる、という自動送信ツールもあります。指定されたディレクトリにファイルを配置しておくと、サービス側で定期的に自動送信の処理をしてくれる仕組みになっており、メールを使った連携に比べて、大容量ファイルの転送にも適しています。
ただし、フォルダを出力するための開発が別途必要なほか、機密情報を含むファイルの取り扱いには、暗号化などの追加対策が必要になる場合がある点に注意が必要です。
FAX自動送信サービス導入時のポイント

2025年現在、各社でさまざまなFAX自動送信サービスが提供されています。
FAXのAPI連携を導入する際は、次の4つのポイントを踏まえてじっくり検討しましょう。
1.FAXの回線数や安定性
2.既存システム間の互換性
3.機能性やサポート体制
4.トータルコストでの比較
1. FAXの回線数や安定性
まず注目すべきは、送信速度に直結するFAXの回線数です。せっかく外部の自動送信サービスを利用するのであれば、大量の宛先でも高速で送信できるような盤石なサービスを選ぶのがおすすめです。数千単位の回線を備えたサービスであれば、大量に送信する場合も一度でスピーディーに送信できます。
また、回線の種類が豊富であるかも確認しておくと良いでしょう。一部の通信事業者で障害が発生した場合にも、複数の回線を保有しているサービスであれば、安定的にFAXの送受信が可能です。
2. 既存システム間の互換性
API連携のサービスを利用する場合、現在使用している基幹システムと導入予定の自動送信サービスの互換性については必ず確認しておかなければなりません。自社の体制でAPI連携が可能かどうか、各サービスに個別に問い合わせると良いでしょう。
また、システムのAPI連携にあたっては、実装までにプログラミングなど一部技術的な知識を要する場合があります。特に、APIでの連携を検討する場合には、導入の難易度や導入までのフォロー体制なども含めて比較しておくと安心です。
2025年3月から提供開始された「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」は、「ASTERIA Warp」の強みである多様な基幹システムの連携が可能になり、多様な基幹システムのデータをお取引先に送信し、シームレスな企業間取引を実現できます[※1]。
3. 機能性やサポート体制
回線数や互換性といった基本的な機能をクリアしていると判断できたサービスについては、導入した後の利便性やサポート体制の充実度で比較しましょう。
Web-APIを用いた連携サービスを利用する場合、リアルタイムで送信状況を把握できるのがメリットの一つですが、そうした送信結果や履歴の管理がしやすいか、またエラーが起きた際の通知機能や再送信のシステムが充実しているかなどの項目をチェックしましょう。
加えて、API側の仕様が変更になったり、FAXの送受信ができなくなったりといったアクシデントが生じた際、手厚いサポートが受けられるとより安心です。
4. トータルコストでの比較
API連携によってFAXの送受信作業を自動化することで、確かに業務効率が向上し、FAX設備のコストカットになります。その一方で、自動送信サービスを導入する際にも一定の初期費用やランニングコストがかかってしまうのも事実です。
料金は、初期費用と月額料金に加えて、月ごとの利用配信数によって追加料金が発生したり、1枚あたりの料金が利用数によって変動したりと各社サービスによって細かく異なります。料金の詳細については、各社に問い合わせてみると良いでしょう。
また、FAXの使い方によっても満足度が異なる点にも注意が必要です。例えば、「同一形式のFAXデータを大量の宛先に配信したい」というニーズの場合、単に宛先を入力するリソースが削減できるため、導入後すぐに自動化のメリットを感じやすいでしょう。一方、それぞれ異なる形式のデータを個別の宛先に送りたいという場合、事前にAPIに合わせたデータを各種揃えなければならないため、送信までにかなりのコストを要する可能性もあります。
もちろん、これまで解説した通りFAXの自動送信によるメリットは多岐に渡りますが、このように「個別に少量で利用したい」というニーズの場合には、想定していたほどメリットを感じられないという結果にもなり得ます。
いずれの場合も、現在FAXの送受信にかかっているコストを改めて算出し、自動送信サービスの導入にかかるコストとじっくり比較するのが導入成功のカギです。
当社の@TovasはFAXをAPI連携して一斉送信できるおすすめサービス

当社のSaaS・クラウド型のインターネットFAXサービス「@Tovas」は、請求書や納品書、注文書などの帳票をワンクリックで送信できます。インターネットの回線で送受信ができ、大量送信も快適。相手先は通常のFAX機で受信可能で、取引先にも負担の少ないサービスです。
また、@Tovasがもつプログラムインターフェイス「@Tovas API機能」では、簡単な実行コマンドで 多くの基幹システムと@Tovasを連携させることができます。 基幹システムからのFAXデータ(TIFF)を@Tovasサーバを経由することにより、既存の仕組みを使いながら、簡単・安全・確実に送信先へ配信することが可能です。
さらに、FAX以外も郵送・電子ファイルなどさまざまな送信形式に対応しており、毎月発生する手作業の帳票業務において、総合的な効率化に繋がります。
2025年5月13日からは帳票の「受け取る」機能も追加され、帳票の送受信機能を兼ね備えたサービスとして生まれ変わりました[※3]。また、2025年3月6日からは「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」の提供も開始され、多様な基幹システムとのシームレスな連携が実現しています[※1]。
FAXをはじめとした帳票配信コストの削減を目指すなら、ぜひ一度ご相談ください。
参考文献
[※1]: コクヨ株式会社「電子帳票配信システム「@Tovas」と基幹システムのシームレスな連携を実現!「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」を提供開始」2025年3月6日
https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20250306cs1.html
[※2]: コクヨ株式会社「電子帳票配信システム「@Tovas」とハイパーオートメーションツール「Yoom」がサービス連携を開始」2025年4月17日
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001049.000048998.html
[※3]: コクヨ株式会社「電子帳票配信システム「@Tovas」に帳票の受け取り機能が追加」2025年4月2日
https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20250402cs1.html