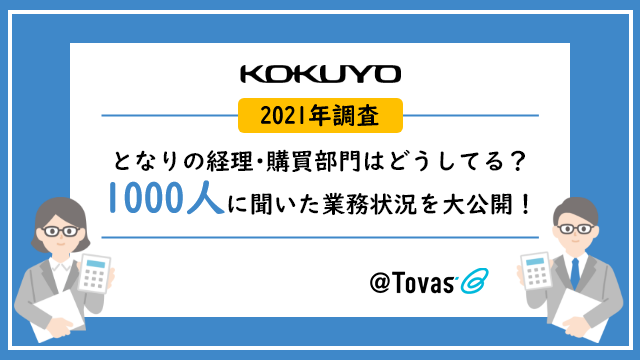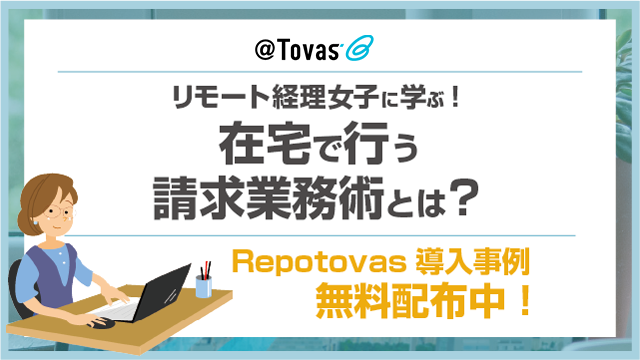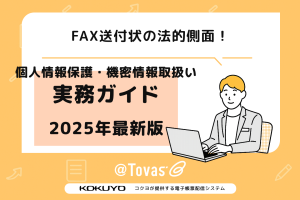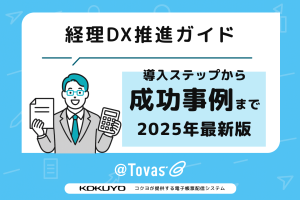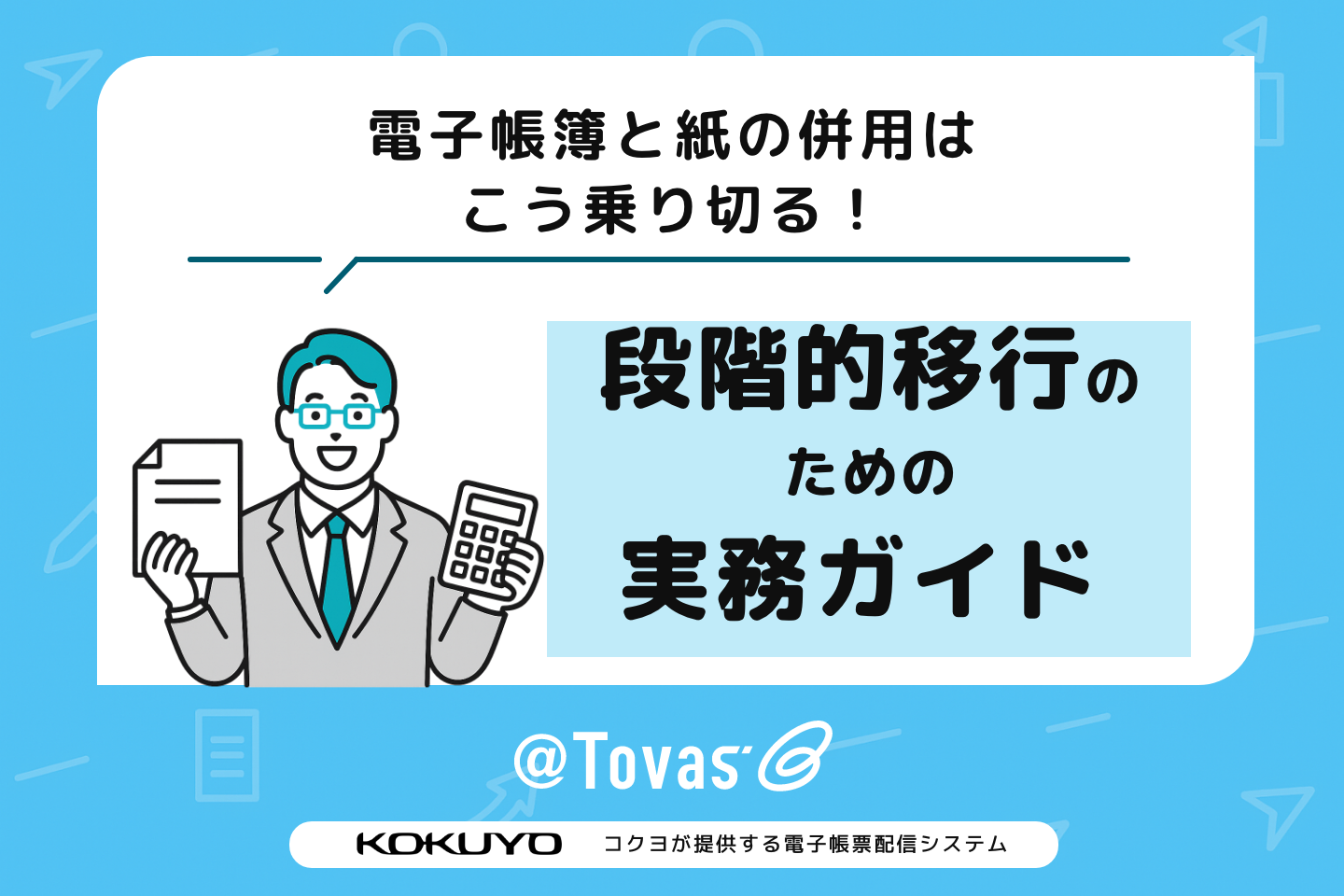
電子帳簿と紙の併用はこう乗り切る!段階的移行のための実務ガイド
公開日:2025年5月25日 更新日:2025年9月2日
2024年1月から電子取引データの保存が完全義務化され、多くの企業が電子と紙の併用環境での運用に頭を悩ませています。本記事では、この過渡期を乗り切るための段階的移行の実務ポイントを解説します。
目次
1. はじめに:電子帳簿と紙の併用の現状と課題
2. 電子帳簿保存法における紙と電子の併用ルール
3. 段階的移行のための5ステップ実務計画
4. 書類種類別の併用環境での具体的な管理方法
5. 併用環境での検索性確保と運用効率化のポイント
6. 併用環境から完全電子化への移行ステップ
7. 併用環境での税務調査対応のポイント
8. 併用環境でよくあるトラブルと解決策
9. @Tovasによる併用環境の効率的な管理方法
10. まとめ:併用環境を乗り切るための実務チェックリスト
1. はじめに:電子帳簿と紙の併用の現状と課題
2024年1月1日から電子取引データの保存が完全義務化され、電子メールやクラウドサービスで受け取った請求書や契約書などは、データのまま保存することが必須となりました。しかし、多くの企業では依然として紙の書類も多く存在し、電子と紙が混在する「ハイブリッド環境」での運用を強いられています。
または「現在でも多くの企業で電子と紙の併用が継続」、完全電子化への移行はまだ道半ばという状況です。特に中小企業では、リソースやノウハウの不足から、この併用環境が長期化する傾向にあります。
経理担当者からは以下のような悩みの声が多く聞かれます:
・「電子と紙、どちらで保存すべきか判断に迷う」
・「両方の保存形式が混在して、書類を探すのに時間がかかる」
・「部署によって対応がバラバラで統一できない」
・「税務調査の際に両方の形式から証拠を提示する必要があり不安」
本記事では、このような併用環境を効率的に運用しながら、段階的に電子化を進めるための実務的なガイドを提供します。法的要件を満たしつつ、現場の負担を最小限に抑える方法を具体的に解説していきます。
2. 電子帳簿保存法における紙と電子の併用ルール
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月からは電子取引データの保存が完全義務化されましたが、すべての書類を電子化しなければならないわけではありません。紙と電子の併用が認められるケースを正確に理解することが、効率的な移行の第一歩です。
電子保存が必須のケース(紙保存不可)
電子取引で受領した書類は、必ず電子データのまま保存する必要があります。
具体的には以下のようなケースが該当します:
・電子メールに添付された請求書や契約書
・クラウドサービスを通じて受領した書類
・Webサイトからダウンロードした書類
・EDI取引で受領したデータ
これらの書類を印刷して紙で保存するだけでは法的要件を満たさず、税務調査の際に否認されるリスクがあります。
「電子取引で受領した書類は、紙保存の併用ができません。電子メールを使って受け取った請求書は、紙で保存するだけでは不十分です。電子データとして保存する必要があります」
紙保存が認められるケース
一方で、以下のケースでは紙での保存が認められています:
1. 紙で受領した書類:取引先から紙で受け取った請求書や契約書などは、そのまま紙で保存できます。任意でスキャナ保存することも可能です。
2. 紙で作成・送付した書類の控え:自社で作成し、取引先に送付した書類の控えも紙で保存できます。
3. 自社で作成した国税関係書類:仕訳帳や現金出納帳などの国税関係帳簿は、紙で保存することが可能です。会計ソフトやエクセルなど電子データとして作成した場合でも、電子データとして保存しながら、必要に応じて紙に印刷して保存する方法も認められています。
「会計ソフトやエクセルなど電子データとして作成した場合、電子データとして保存しながら、必要に応じて紙に印刷して保存する方法も認められます」
併用環境における法的要件の整理
併用環境で特に注意すべき法的要件は以下の通りです:
1. 電子保存データの検索要件は原則必要ですが、基準期間の売上高が5,000万円以下で、税務調査等の際に電子データのダウンロードの求め及び書面提示に応じられる体制がある場合は、検索機能の全てを不要とする措置の対象になり得ます。
2. タイムスタンプ要件:電子取引データの真実性を確保する方法としては、タイムスタンプの付与のほか、訂正削除の防止機能があるシステムの利用や、「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」(規則8条1項4号)の整備・運用など、複数の方法が認められています。特定のクラウドサービスや電子契約システムなど、これらの要件を満たすシステムを経由する場合には、タイムスタンプの付与が不要となるケースがあります。
3. 事務処理規程:電子と紙の併用環境では、どの書類をどのように保存するかを明確にした事務処理規程の整備が重要です。
「紙保存から電子保存に移行する場合は、スキャナ保存の手続きを行い、事務処理規程を作成します。その後、税務署への申請は不要ですが、管理規程を整備して運用する必要があります」
3. 段階的移行のための5ステップ実務計画
電子と紙の併用環境から段階的に電子化を進めるためには、計画的なアプローチが不可欠です。以下の5ステップで実務計画を立てましょう。
ステップ1:現状把握と対象書類の分類
まずは自社で取り扱う書類の全体像を把握し、分類することから始めます。
実践方法:
1. 全社的な書類の洗い出しを行う
2. 以下の4つに分類する
・電子で受領・電子保存が必須の書類
・紙で受領・紙保存可能な書類
・紙で受領・電子化したい書類
・自社作成・保存形式を選択できる書類
3. 各書類の年間取扱量を把握する
「電子保存への移行は、計画的かつ段階的に進めることが重要です。既存の文書管理システムを点検し、電子帳簿保存法の要件を満たすために必要な対応を特定しましょう」
ステップ2:優先順位付けと段階的移行計画の策定
分類した書類に優先順位をつけ、段階的な移行計画を立てます。
実践方法:
1. 以下の観点で優先順位をつける
・法的要件(電子保存必須のものを最優先)
・取扱量(量が多いものほど効率化効果が高い)
・業務影響(コア業務に関わるものは慎重に)
・部門対応力(ITリテラシーの高い部門から)
2. 四半期ごとの移行計画を立てる
3. 各フェーズの目標と評価指標を設定する
「紙の原本をスキャンする場合、経理でデータ化するか受け取った部署でデータ化するかは事前に決めておくとよいでしょう。原則として受け取った部署でデータ化することをお勧めします」
ステップ3:保存ルールと業務フローの整備
電子と紙の併用環境での保存ルールと業務フローを整備します。
実践方法:
1. 書類種類ごとの保存ルールを明文化する
・保存形式(電子/紙/両方)
・保存場所(システム名/ファイル場所/キャビネット番号)
・保存期間
・命名規則・整理方法
2. 業務フロー図を作成する
・受領から保存までの流れ
・責任者と担当者の役割
・例外処理の方法
3. 事務処理規程として文書化する
「電子帳簿等保存制度は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度です。保存方法を明確にした事務処理規程の整備が重要です」(国税庁, 2024)
ステップ4:システム選定と導入
併用環境を効率的に管理するためのシステムを選定・導入します。
実践方法:
1. 必要な機能要件を整理する
・電子保存の法的要件対応
・紙書類の電子化機能
・検索・閲覧機能
・既存システムとの連携
2. 複数のシステムを比較検討する
3. 小規模な部門でパイロット導入する
4. 効果を検証し、全社展開する
「電子帳簿保存法システムの選定では、自社の業務フローに合ったものを選ぶことが重要です。特に検索機能や他システムとの連携性、将来的な拡張性を考慮しましょう」
ステップ5:社内教育と運用開始
新しい保存ルールとシステムについて社内教育を行い、運用を開始します。
実践方法:
1. 部門別の教育資料を作成する
2. 説明会とハンズオントレーニングを実施する
3. よくある質問と回答集(FAQ)を作成する
4. ヘルプデスクを設置する
5. 定期的なフォローアップを行う
「社内教育は移行の成功に不可欠です。特に経理部門だけでなく、書類を受領・作成する全部門の担当者に対して、新しいルールとシステムの使い方を丁寧に説明することが重要です」
4. 書類種類別の併用環境での具体的な管理方法
書類の種類によって最適な管理方法は異なります。ここでは主要な書類種類別の具体的な管理方法を解説します。
請求書・領収書の併用管理方法
請求書と領収書は取引量が多く、管理が煩雑になりやすい書類です。
電子で受領した場合:
1. 受信した電子メールやダウンロードしたPDFをそのまま保存
2. ファイル名に「請求書_取引先名_日付_金額」などの命名規則を適用
3. 取引年月日、取引金額、取引先で検索できるよう整理
紙で受領した場合:
1. 紙のまま保存するか、スキャナ保存を選択
2. スキャナ保存する場合は、受領後できるだけ早くスキャン
3. 電子データと同様の命名規則を適用
4. 原本は法定保存期間が経過するまで保管するか、要件を満たせば廃棄
「電子取引のデータ保存の主な対象書類は、電子データでやりとりした請求書等の取引関連書類であり、Web請求書やメールデータ、EDI取引、クラウドサービスを利用して授受した書類などが挙げられます」
契約書・注文書の併用管理方法
契約書や注文書は法的重要性が高く、慎重な管理が必要です。
電子で締結・受領した場合:
1. 電子契約システムのデータをそのまま保存
2. システム外で受領した場合は、専用フォルダに整理して保存
3. 契約の重要度に応じてアクセス権限を設定
紙で締結・受領した場合:
1. 原本は紙で保存
2. 重要契約は参照用にスキャンして電子保存も並行
3. 契約台帳(エクセルなど)で紙と電子の両方を一元管理
「電子契約と紙契約が混在する環境では、契約台帳による一元管理が効果的です。契約書の保存場所(電子/紙)を明記し、検索性を確保することが重要です」
社内帳票の併用管理方法
社内帳票は自社で作成・完結するため、保存形式を選択できます。
電子で作成する場合:
1. 会計ソフトやエクセルで作成したデータをそのまま保存
2. 必要に応じて紙出力も並行(両方保存可能)
3. 電子データを正本として明確に位置づけ
紙で作成する場合:
1. 紙の原本を保存
2. 参照頻度が高い場合は電子化も検討
3. 段階的に電子化への移行を計画
「自社で作成した国税関係帳簿は、紙で保存することが可能です。会計ソフトやエクセルなど電子データとして作成した場合、電子データとして保存しながら、必要に応じて紙に印刷して保存する方法も認められます」
経費精算関連書類の併用管理方法
経費精算は従業員全員が関わる業務であり、特に丁寧な移行が必要です。
電子領収書の場合:
1. 経費精算システムに直接取り込み
2. システムで承認フローを完結
3. データのまま保存
紙の領収書の場合:
1. スマホアプリなどでスキャン
2. 経費精算システムに取り込み
3. 原本は一定期間保管後、要件を満たせば廃棄
「経費精算業務は電子化による効率化効果が特に高い領域です。紙の領収書が多い場合でも、スマートフォンでのスキャンと経費精算システムの組み合わせにより、大幅な業務効率化が可能です」
5. 併用環境での検索性確保と運用効率化のポイント
電子と紙が混在する環境では、書類の検索性確保と運用効率化が大きな課題となります。以下のポイントを押さえましょう。
紙書類と電子書類の関連付け方法
紙と電子の書類を関連付けることで、どちらの形式からでも必要な情報にアクセスできるようにします。
実践方法:
1. 共通の管理番号を付与する
・紙書類には管理番号を印字
・電子ファイル名にも同じ管理番号を含める
2. QRコードや管理バーコードを活用する
・紙書類にQRコードを貼付
・QRコードをスキャンすると対応する電子データにアクセスできる仕組み
3. 紙書類の保管場所情報を電子データに記録する
「紙と電子の書類を効率的に管理するには、共通の識別子による関連付けが効果的です。特に取引量の多い書類では、バーコードやQRコードを活用した管理が推奨されます」
統一的な検索・参照の仕組み作り
紙と電子の両方を対象とした統一的な検索・参照の仕組みを構築します。
実践方法:
1. 書類管理台帳(エクセルやデータベース)を作成する
・書類の基本情報(日付、取引先、金額など)
・保存形式(電子/紙/両方)
・保存場所(システム名/フォルダパス/キャビネット番号)
2. 文書管理システムを導入する
・電子データの直接管理
・紙書類の所在情報管理
・横断的な検索機能
3. 定期的なインデックス更新ルールを設ける
「電子帳簿保存法では、電子保存している書類は、取引年月日、取引金額、取引先で検索できる必要があります。紙書類についても同様の検索性を確保することで、業務効率が大幅に向上します」
併用環境でのファイリングルール
紙と電子それぞれに適したファイリングルールを整備します。
紙書類のファイリングルール:
1. 書類種類ごとにバインダーを分ける
2. 取引先別・日付順に整理
3. 背表紙に内容と保存期間を明記
4. 定期的に保存期間経過分を整理
電子書類のファイリングルール:
1. フォルダ構造を標準化(年/月/書類種類など)
2. ファイル命名規則を統一
3. メタデータ(タグ付け)を活用
4. バックアップと定期的な整理
「フォルダ管理やファイル名管理でも検索要件を満たすことができます。例えば、『取引年月日_取引先_金額』といったファイル名の付け方や、年月日・取引先ごとのフォルダ分けなどが有効です」
併用環境での業務効率化テクニック
併用環境での業務効率を高めるテクニックを紹介します。
実践テクニック:
1. 定型業務の標準化
・書類受領から保存までの手順書作成
・チェックリストの活用
2. バッチ処理の導入
・紙書類のスキャンを一日一回など定時に実施
・電子データの整理・バックアップを定期実行
3. 自動化ツールの活用
・OCR技術による紙書類のデータ化
・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型作業の自動化
4. クロスチェック体制の構築
・紙と電子の整合性を定期的に確認
・不一致の早期発見と修正
「OCR技術を活用することで、紙書類からデータを自動抽出し、電子データとの連携を効率化できます。特に請求書や領収書など定型フォーマットの書類では効果が高いでしょう」
6. 併用環境から完全電子化への移行ステップ
併用環境は過渡期の状態であり、最終的には完全電子化を目指すことが理想的です。以下のステップで段階的に移行を進めましょう。
部門別・書類種類別の段階的移行計画
全社一斉ではなく、部門や書類種類ごとに段階的に移行を進めます。
実践方法:
1. スタートする部門を選定する
・ITリテラシーが高い部門
・書類取扱量が比較的少ない部門
・改善意欲の高い部門
2. 書類種類の優先順位を決める
・電子化効果が高いもの(取扱量が多い)
・標準化しやすいもの(フォーマットが統一)
・法的要件が厳しいもの
3. 成功事例を他部門に展開する
・効果測定と改善点の洗い出し
・成功ノウハウの文書化
・横展開のためのサポート体制
「電子保存への移行は、計画的かつ段階的に進めることが重要です。以下に、移行手順を説明します。既存の文書管理システムを点検し、電子帳簿保存法の要件を満たすために必要な対応を特定しましょう」
社内規程の整備と更新
電子化の進展に合わせて社内規程を整備・更新します。
実践方法:
1. 文書管理規程の改定
・電子文書の正本性の明確化
・保存形式と保存場所の定義
・保存期間と廃棄ルール
2. 業務マニュアルの更新
・電子化後の業務フロー
・システム操作手順
・例外処理の方法
3. 権限管理規程の整備
・アクセス権限の設定
・承認フローの電子化
・電子印鑑・電子署名の運用ルール
「紙保存から電子保存に移行する場合は、スキャナ保存の手続きを行い、事務処理規程を作成します。その後、税務署への申請は不要ですが、管理規程を整備して運用する必要があります」
社員教育と意識改革のポイント
電子化の成功には社員の理解と協力が不可欠です。効果的な教育と意識改革を進めましょう。
実践方法:
1. 階層別の教育プログラム
・経営層:電子化の意義と効果
・管理職:運用管理と部下指導
・一般社員:具体的な操作方法
2. 実践的なトレーニング
・ハンズオン形式の操作研修
・実際の業務データを使った演習
・e-ラーニングによる自己学習
3. 意識改革のための取り組み
・電子化の効果の見える化
・成功事例の共有
・改善提案制度の導入
「社内教育は移行の成功に不可欠です。特に経理部門だけでなく、書類を受領・作成する全部門の担当者に対して、新しいルールとシステムの使い方を丁寧に説明することが重要です」
移行期間中のリスク管理と対策
移行期間中は特有のリスクが発生します。事前に対策を講じておきましょう。
主なリスクと対策:
1. データ紛失リスク
・二重保存(電子+紙)の一時的実施
・バックアップ体制の強化
・移行状況の日次確認
2. 業務停滞リスク
・段階的移行による負荷分散
・ヘルプデスクの設置
・緊急時の代替手段の確保
3. コンプライアンスリスク
・税理士や専門家のレビュー
・定期的な自主点検
・監査証跡の確保
「移行期間中は、電子と紙の両方で保存することで、万一の場合のリスクを軽減できます。ただし、最終的にはどちらが正本かを明確にし、二重管理による非効率を解消することが重要です」
7. 併用環境での税務調査対応のポイント
電子と紙が混在する環境での税務調査は特有の難しさがあります。適切に対応するためのポイントを解説します。
紙と電子が混在する環境での税務調査の実態
税務調査官は、保存されている書類の形式に関わらず、必要な証拠の提示を求めます。
税務調査の実態:
1. 調査官は電子データと紙書類の両方を確認
2. 保存形式の法的要件への準拠を重点的にチェック
3. 電子と紙の整合性を検証
4. 検索機能の実効性を確認
調査官からよく質問される事項と回答準備
税務調査でよく質問される事項とその回答準備について解説します。
よくある質問と回答準備:
1. 電子取引データの保存方法
・保存システムの概要説明資料
・検索機能のデモンストレーション準備
・事務処理規程の提示
2. 紙と電子の区分方法
・書類種類ごとの保存形式一覧
・判断基準の明確化
・例外処理の記録
3. システム変更の履歴
・システム導入・変更の記録
・移行前後のデータ保存状況
・データ移行の検証結果
「税務調査では、電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかが重点的に確認されます。特に検索機能やタイムスタンプの要件について、実際に操作して示せるよう準備しておくことが重要です」
併用環境での証跡の提示方法
電子と紙が混在する環境での効果的な証跡提示方法を解説します。
実践方法:
1. 証跡マップの作成
・取引の流れと証跡の対応関係を図示
・電子と紙の証跡の関連性を明示
・保存場所の一覧化
2. 効率的な提示手順の確立
・電子データの検索・抽出手順
・紙書類の特定・取り出し手順
・両者の突合方法
3. 視覚的な説明資料の準備
・システム概要図
・業務フロー図
・保存体制の組織図
「電子取引データと紙書類が混在する環境では、それぞれの保存状況と相互関連性を明確に説明できることが重要です。特に、同一取引に関する書類が電子と紙に分かれている場合、その全体像を示せるよう準備しておきましょう」
調査対応を見据えた日常的な準備
税務調査に備えた日常的な準備について解説します。
実践方法:
1. 定期的な自主点検
・月次での保存状況確認
・検索機能のテスト実施
・不備の早期発見と修正
2. 証跡サンプルの定期抽出
・四半期ごとに主要取引の証跡を抽出
・電子と紙の整合性確認
・抽出結果の記録保存
3. 想定問答集の作成
・想定される質問のリストアップ
・回答内容と提示資料の整理
・担当者への教育
「税務調査への対応は日常的な準備が鍵となります。特に電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかを定期的に自主点検し、不備があれば早急に修正することが重要です」
8. 併用環境でよくあるトラブルと解決策
電子と紙の併用環境では特有のトラブルが発生します。代表的なトラブルとその解決策を解説します。
保存形式の誤りと対処法
書類の保存形式を誤ってしまった場合の対処法を解説します。
よくあるケースと対処法:
1. 電子取引データを紙だけで保存してしまった
・原データが残っている場合:速やかに電子保存に切り替え
・原データが消失した場合:取引先に再送を依頼
・再入手不可の場合:経緯を記録し、今後の対策を強化
2. 紙書類を誤って廃棄してしまった
・コピーや控えがある場合:その旨を記録して保存
・取引先に複製を依頼できる場合:再入手
・完全に消失した場合:経緯を記録し、内部統制を強化
「電子取引データを誤って紙だけで保存してしまった場合、できるだけ早く電子データを入手し直して保存することが重要です。また、このようなミスを防ぐための社内ルールと教育を徹底しましょう」
検索性確保の失敗と改善策
検索性の確保に失敗した場合の改善策を解説します。
よくあるケースと改善策:
1. ファイル名やフォルダ構造が不統一
・命名規則の再設定と周知
・既存ファイルの一括リネーム
・ファイル整理ツールの導入
2. メタデータの不足や誤り
・メタデータ入力ガイドラインの作成
・一括修正ツールの活用
・入力チェック機能の導入
3. 検索システムの機能不足
・システムのアップグレード
・補助的な検索ツールの導入
・代替的な索引作成
「検索要件を満たすためには、取引年月日、取引金額、取引先で検索できる必要があります。これらの情報をファイル名やフォルダ名に含めるか、メタデータとして付与することで、検索性を確保できます」
社内ルール不徹底による混乱と対策
社内ルールが徹底されず混乱が生じた場合の対策を解説します。
よくあるケースと対策:
1. 部門によって運用がバラバラ
・全社統一ルールの再周知
・部門責任者への個別説明
・定期的な運用状況チェック
2. 新入社員や異動者への教育不足
・入社時・異動時の必須研修化
・マニュアルの整備と配布
・メンター制度の導入
3. ルールの複雑さによる混乱
・ルールの簡素化と明確化
・チェックリストの作成
・判断に迷うケースのQ&A整備
「社内ルールの不徹底は、電子と紙の併用環境における最大の課題の一つです。定期的な研修と、わかりやすいマニュアル・チェックリストの整備が効果的な対策となります」
システム障害時の対応策
システム障害が発生した場合の対応策を解説します。
実践方法:
1. 緊急時の代替手順の整備
・一時的な紙運用への切り替え手順
・復旧後のデータ反映方法
・責任者と連絡体制
2. バックアップと復旧体制
・定期的なバックアップの実施
・復元テストの定期実施
・復旧手順の文書化
3. 障害記録と再発防止
・障害内容と対応の記録
・原因分析と再発防止策
・関係者への情報共有
「システム障害は必ず発生するものと想定し、事前に対応策を準備しておくことが重要です。特に電子保存が義務付けられている書類については、障害時の代替手段と復旧後の処理手順を明確にしておきましょう」
9. @Tovasによる併用環境の効率的な管理方法
コクヨの電子帳票配信システム「@Tovas」は、電子と紙の併用環境を効率的に管理するための機能を備えています。
@Tovasの併用環境対応機能
@Tovasが提供する併用環境対応機能を紹介します。
主な機能:
1. 電子取引データの法的要件対応
・タイムスタンプ付与
・検索要件対応
・改ざん防止
2. 紙書類の電子化支援
・送付する取引先によって紙または電子配信の選択が可能
3. 併用環境の一元管理
・電子書類と紙書類の統合管理
・保存形式に関わらない検索
・アクセス権限の一元管理
「@Tovasは2025年5月13日から帳票の「受け取る」機能が追加され、送信だけでなく受信した帳票も一元管理できるようになりました。これにより、電子と紙の併用環境における管理効率が大幅に向上します」
紙書類と電子書類の一元管理
@Tovasによる紙書類と電子書類の一元管理方法を解説します。
実践方法:
1. 書類の統合管理
・電子原本はシステム内に保存
2. 統合検索の活用
・書類種類、日付、取引先などの条件で横断検索
・保存形式(電子/紙)での絞り込み
3. 一元的なワークフロー
・電子書類も紙書類も同一のワークフローで処理
・承認処理
・処理状況の可視化
「2025年3月6日から提供開始された「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」により、基幹システムとの連携が強化され、シームレスな紙と電子の書類の送信が可能となりました。」
段階的移行を支援する機能
@Tovasによる段階的移行支援機能を解説します。
主な機能:
1. 移行計画支援
・現状分析
・段階的移行シミュレーション
・効果予測
2. 並行運用サポート
・電子と紙(郵送)の並行運用
・例外処理の柔軟対応
3. 教育・啓発支援
・操作マニュアルの提供
・ヘルプデスクサポート
「@Tovasは段階的な電子化移行を支援するため、部門や書類種類ごとに異なる移行スケジュールに対応できる柔軟な設計となっています。これにより、企業の状況に合わせた最適な移行が可能です」
導入事例と効果
@Tovasを活用した併用環境管理の導入事例と効果を紹介します。
導入事例:
1. 製造業A社の事例
・課題:紙と電子の併用による業務非効率
・対策:@Tovasによる一元管理体制の構築
・効果:書類検索時間70%削減、保管コスト50%削減
2. 卸売業B社の事例
・課題:電子取引データの法的要件対応
・対策:@Tovasによる自動タイムスタンプと検索機能の活用
・効果:コンプライアンスリスク解消、業務効率30%向上
3. サービス業C社の事例
・課題:部門間の保存方法のバラつき
・対策:@Tovasによる全社統一ルールの導入
・効果:社内ルールの標準化、教育コスト削減
10. まとめ:併用環境を乗り切るための実務チェックリスト
電子と紙の併用環境を効率的に運用し、段階的に電子化を進めるための実務チェックリストを提供します。
法的要件の遵守状況チェック
法的要件の遵守状況を確認するためのチェックリストです。
チェック項目:
・□ 電子取引データは電子保存されているか
・□ 電子保存データは検索要件を満たしているか
・□ タイムスタンプ要件は満たされているか
・□ 事務処理規程は整備されているか
・□ スキャナ保存の要件は満たされているか
・□ 保存期間は遵守されているか
・□ システムの変更履歴は記録されているか
「電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかを定期的にチェックすることが重要です。特に電子取引データの保存が完全義務化された2024年以降は、より厳格な対応が求められます」
業務効率化状況チェック
業務効率化の状況を確認するためのチェックリストです。
チェック項目:
・□ 書類の検索に要する時間は短縮されているか
・□ 紙と電子の二重管理による無駄はないか
・□ 部門間の連携はスムーズか
・□ 例外処理の頻度は減少しているか
・□ システムの操作性に問題はないか
・□ バックアップと復旧の手順は機能しているか
・□ 業務マニュアルは最新か
「併用環境では業務効率化が特に重要です。定期的に業務フローを見直し、無駄な作業や重複作業を削減することで、限られたリソースを有効活用しましょう」
社内教育状況チェック
社内教育の状況を確認するためのチェックリストです。
チェック項目:
・□ 全社員に対する基本教育は実施されているか
・□ 部門責任者への詳細説明は行われているか
・□ 新入社員・異動者への教育は徹底されているか
・□ マニュアルやFAQは整備されているか
・□ 質問や相談の窓口は明確か
・□ 定期的な研修や情報共有の場はあるか
・□ 教育効果の測定は行われているか
「社内教育は電子化成功の鍵です。特に紙と電子の併用環境では、どの書類をどのように保存すべきかの判断が複雑になるため、わかりやすい教育と継続的なフォローアップが重要です」
段階的移行計画の進捗チェック
段階的移行計画の進捗を確認するためのチェックリストです。
チェック項目:
・□ 移行計画は文書化されているか
・□ 各フェーズの目標と期限は明確か
・□ 進捗状況は定期的に確認されているか
・□ 遅延や問題点への対応策はあるか
・□ 成功事例は共有されているか
・□ 計画の見直しと調整は行われているか
・□ 最終目標(完全電子化)への道筋は明確か
「段階的移行を成功させるには、明確な計画と定期的な進捗確認が不可欠です。特に部門や書類種類ごとの移行状況を可視化し、全体の進捗を把握することが重要です」
おわりに
電子と紙の併用環境は、多くの企業にとって避けられない過渡期の状態です。しかし、適切な計画と実務対応により、この併用期間を効率的に乗り切り、段階的に電子化を進めることが可能です。
本記事で紹介した実務ガイドとチェックリストを活用し、法的要件を満たしながら業務効率を高め、最終的な完全電子化への道筋をつけていただければ幸いです。
コクヨの電子帳票配信システム「@Tovas」は、このような併用環境の効率的な管理と段階的な電子化移行を強力にサポートします。2025年5月から提供開始された帳票を「受け取る」機能や、データ連携サービス「ASTERIA Warpアダプターfor@Tovas」、「Yoom」との連携など、最新機能を活用することで、より効率的な移行が可能になります。
電子帳簿保存法対応でお悩みの方は、ぜひ@Tovasの導入をご検討ください。