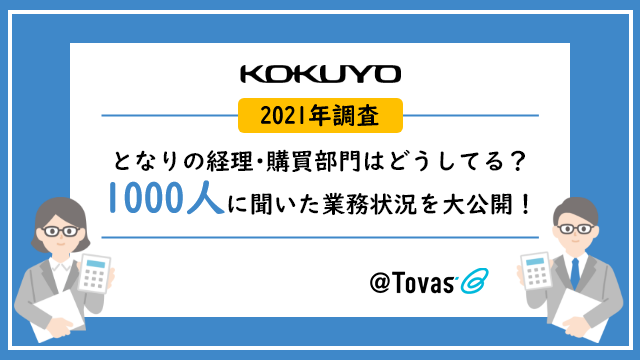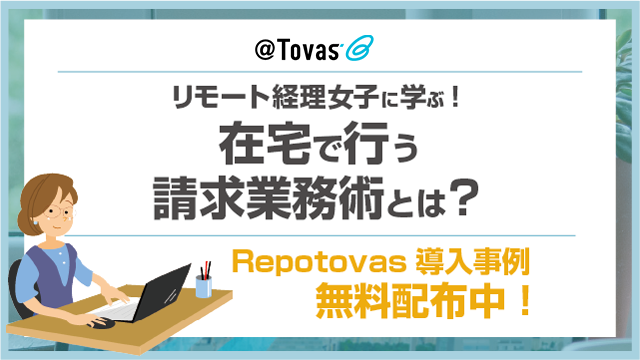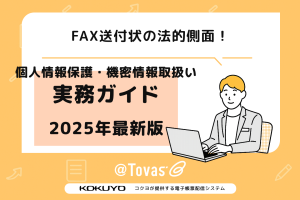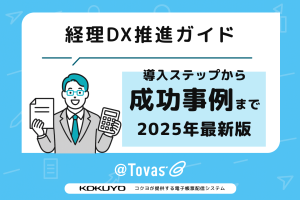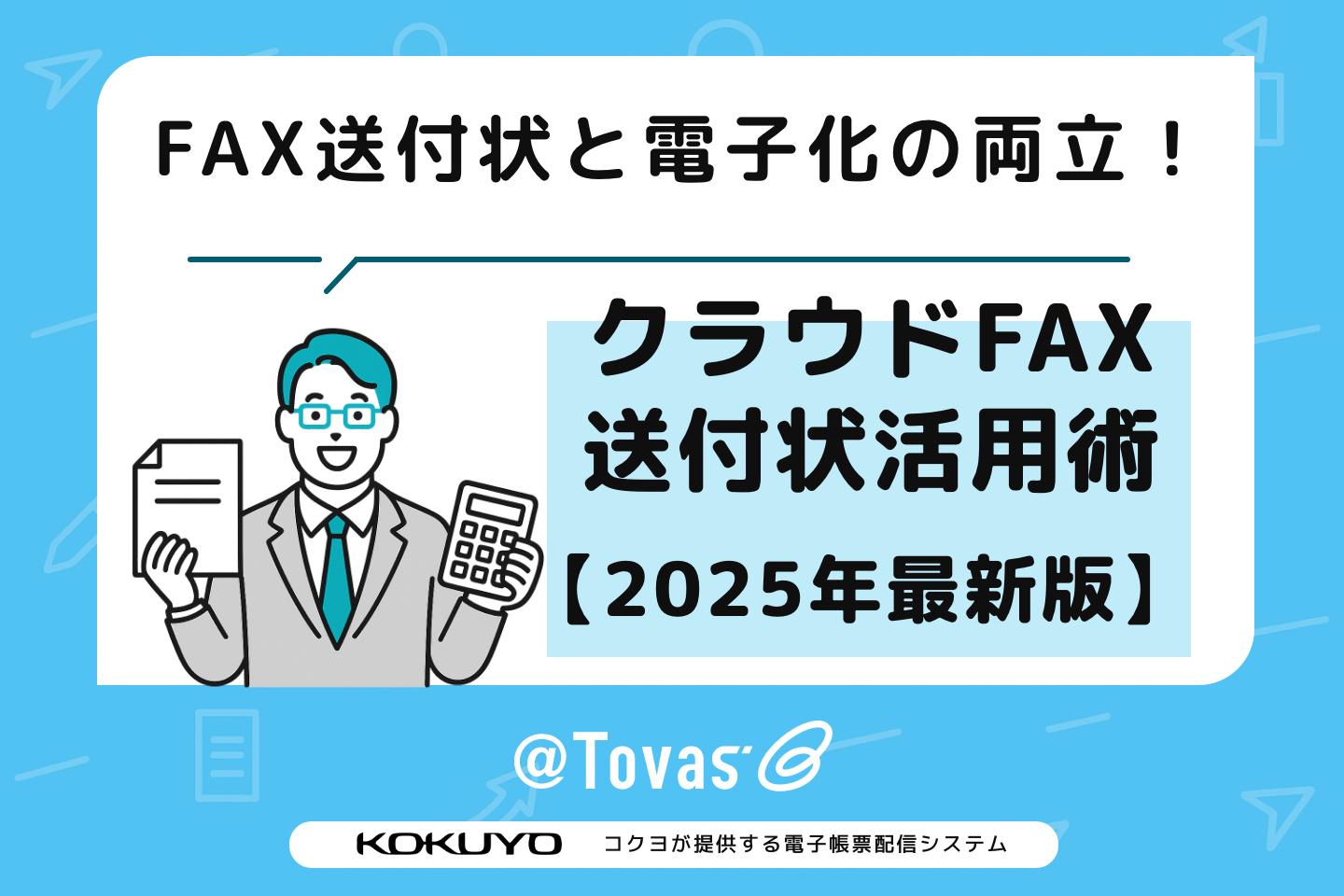
FAX送付状と電子化の両立!クラウドFAXでの送付状活用術【2025年最新版】
公開日:2025年6月12日 更新日:2025年9月3日
はじめに
ビジネスコミュニケーションにおいて、FAX送付状は重要な役割を果たしています。2024年1月に実施されたNTT東西による固定電話網のIP網移行により、FAX環境は大きな変化を迎えました。また、2024年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、FAXデータの取り扱いにも新たな要件が加わっています。
本記事では、これらの変化を踏まえ、実在する企業の導入事例と確認済みの情報源に基づいて、FAX送付状のデジタル活用術を詳しく解説します。
第1章:FAX送付状の基本とビジネスマナー
1.1 FAX送付状の重要性
FAXを送る際は、受信者が書類内容と総ページ数を一目で確認できるよう送付状を添えることがビジネスマナーとなっています。適切な送付状を一緒に送ることで、万が一書類の送信トラブルが発生しても、いち早く対応できます。
1.2 FAX送付状に記載すべき基本項目
FAX送付状には以下の項目を記載することが重要です:
(1)日付
FAX送付状の送付年月日は、最上部に右寄せで記載します。日付がないと、FAXがいつ送付されたかわからず、トラブルの元になってしまいます。
(2)宛先
日付の下の行に左寄せで宛先を記載します。社名は(株)や(有)などと省略せず、必ず正式名称で記載します。
(3)差出人情報
差出人情報は、宛先の次の行に右寄せで記載します。記載内容は、住所、氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレスです。
(4)表題
表題は「何の目的でFAXを送付したのか」を伝えるために作成します。送付状を手にしたときすぐ目につくように、表題は本文より少し大きめのフォントで記載しましょう。
(5)総ページ数
FAXは途中でページが欠けることがあるため、総ページ数の記載は非常に重要です。「総ページ数:〇ページ(表紙含む)」などと明記し、相手が表紙を含めた全体のページ数を認識できるようにします。
(6)頭語+挨拶文+結語
ビジネス文書として、「拝啓」で始まり「敬具」で終わる形式が一般的です。
(7)本文
挨拶文に続き、送付内容の概要や用件を簡潔に記載します。送付書類に関する補足事項や伝達したいことがある場合も、この部分に書き添えましょう。
(8)「記」書き
送付内容の詳細を分かりやすく示すために、「記」と中央に記載した上で、箇条書きを用いるのが一般的です。送付書類の名称や部数などを具体的に列記することで、相手が内容を確認しやすくなります。 もし書類が多く送付状に書ききれない場合は、「別紙参照」などと記し、詳細を別の用紙にまとめることも可能です。
(9)以上
箇条書きの最後に、文書の締めとして「以上」と右寄せで記載します。これにより、伝えたい用件がここで終わりであることを明確に示します。
第2章:2024年の法制度変更とFAX環境への影響
2.1 IP網移行の影響
2024年1月1日、NTT東日本およびNTT西日本による固定電話網のIP網への移行が実施されました。この移行により、FAX通信の品質に影響が出る可能性があることがNTTから告知されています。[7]
2.2 改正電子帳簿保存法とFAXデータ
2024年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、FAX受信データの扱いに重要な影響があります。
電子取引の定義とFAX
FAXで受け取った文書が電子取引の定義に該当するか否かは、受け取り方とその後の取り扱いで変わります:
・紙で受信・保管する場合:電子取引とは見なされません
・電子形式で受信・保存する場合:電子取引の範疇に含まれ、電子帳簿保存法の適用対象となります
電子保存の要件
電子形式で受信しデジタルのまま保存されるFAXは、以下の要件を満たす必要があります:
1. 真実性の要件:保存されたデータが元の状態のまま改ざんされていないことを保証
2. 可視性の要件:保存されたデータが必要に応じて容易に検索・表示されるようにすること
第3章:コクヨ@Tovasの最新機能
3.1 帳票受け取り機能の追加
コクヨ株式会社が提供する電子帳票配信システム「@Tovas(アットトバス)」は、2025年5月13日(火)から帳票を「受け取る」機能の提供を順次開始しました。
新機能の概要
・明細書・納品書などのあらゆる帳票を「電子ファイル(Web・メール)」「FAX」「郵送」で受け取り可能
・帳票の受け取り後に発生するデータ入力作業もアウトソーシング可能
・システムと人によるサポートでお客様を支援
業務支援内容
・自社システム、AIOCRとの連携、データ投入
・PDF閲覧(電子帳簿保存法に適した長期保存、証跡保存、チェック用として利用)
・BPOによる作業代行、入力代行
・社内業務への活用、業務処理への利用
3.2 電子帳簿保存法への対応
@TovasはJIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)を取得しており、電子帳簿保存法に対応しています。
*出典:コクヨ「電子帳票配信システム「@Tovas」に帳票の受け取り機能が追加」(https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20250402cs1.html)*
第4章:FAX送付状のテンプレート活用
テンプレート選択のポイント
1. 業務内容に適したデザイン:見積書送付、提案書送付、謝罪・訂正など、用途に応じたテンプレートを選択
2. 編集の容易さ:WordやPDF形式で編集しやすいものを選択
3. 法的要件への対応:電子帳簿保存法などの要件を満たすテンプレートを選択
第5章:デジタル化のメリットと注意点
5.1 デジタル化のメリット
業務効率化
・送信時間の短縮
・運用負荷の軽減
・履歴管理の一元化
コスト削減
・用紙代の削減
・通信費の削減
・人件費の削減
セキュリティ向上
・誤送信防止機能
・アクセス制御
・監査証跡の確保
5.2 注意すべきポイント
法的要件の遵守
・電子帳簿保存法の要件確認
・データの真実性・可視性の確保
・適切な保存期間の設定
システム選択の重要性
・自社の業務フローに適合するシステムの選択
・既存システムとの連携可能性
・サポート体制の充実度
まとめ
FAX送付状のデジタル活用は、2024年の法制度変更を受けて重要性が増しています。実際の企業導入事例を見ると、適切なシステム選択により大幅な業務効率化が実現されています。
重要なポイントは以下の通りです:
1. 基本的なビジネスマナーの遵守:適切な送付状の作成
2. 法的要件への対応:電子帳簿保存法の要件確認
3. システム選択の慎重な検討:自社に適したソリューションの選択
4. 段階的な導入:リスクを最小化した導入アプローチ
今後も技術の進歩とともに、FAX送付状のデジタル活用はさらに発展していくことが予想されます。企業は、これらの変化に適応し、効率的で法的要件を満たすFAX業務の実現を目指すことが重要です。
参考文献
1. コクヨ「電子帳票配信システム「@Tovas」に帳票の受け取り機能が追加」https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20250402cs1.html
2. 固定電話(加入電話・INSネット)のIP網移行 INSネットをご利用の事業者さまへ https://web116.jp/2024ikou/business.html