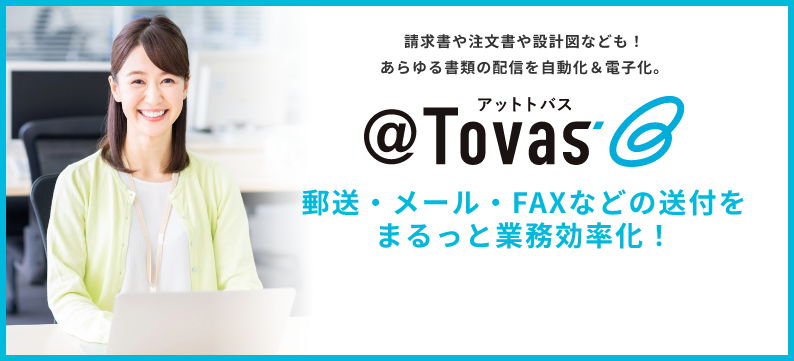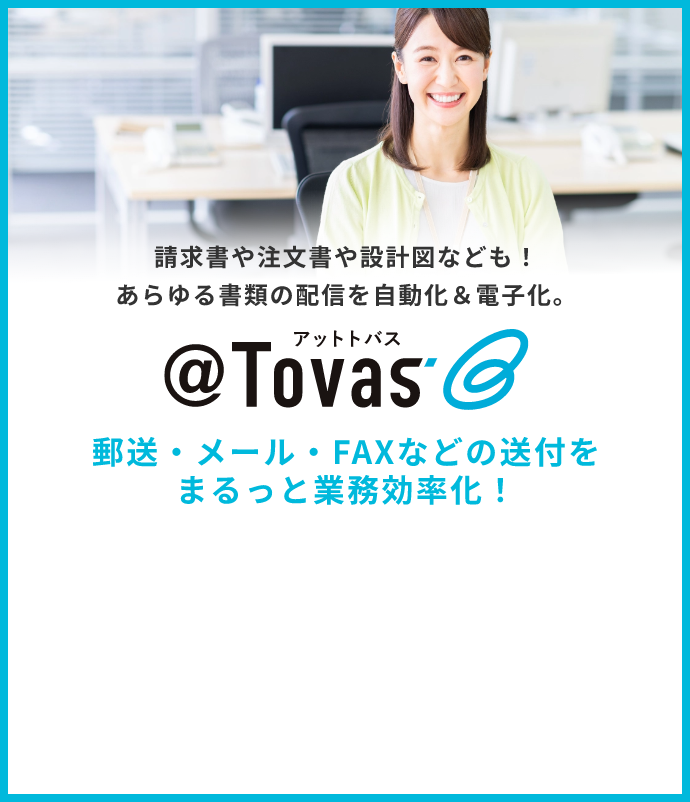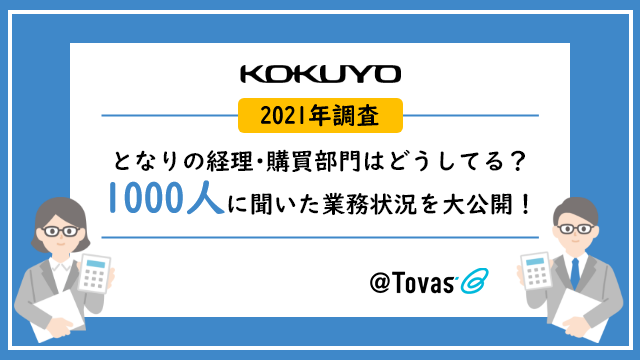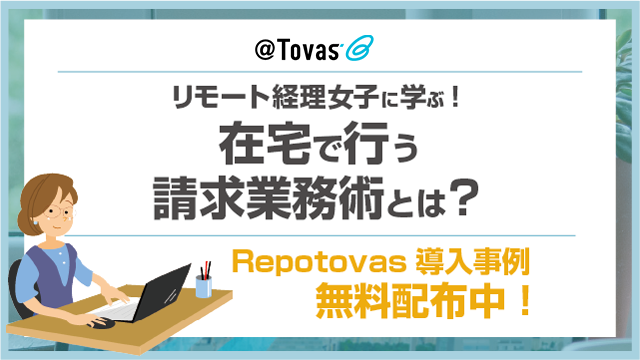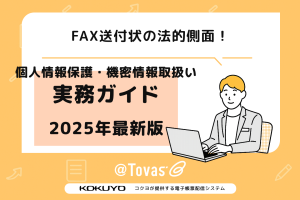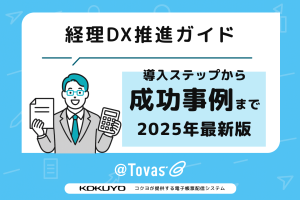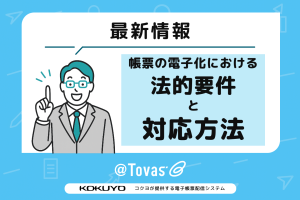20年先を見据えた帳票DX─「@Tovas(アットトバス)」が拓く、業務電子化の未来
公開日:2025年11月12日 更新日:2025年12月8日
目次
開発者プロフィール

コクヨ株式会社
イノベーションセンター @Tovas事業部
システムグループ グループリーダー
渡部 善之(わたべ・よしゆき)
20年間一貫して「帳票」に関連する業務に携わり、豊富な経験から「帳票親方」と呼ばれています。
培ったノウハウを利用して様々な角度で帳票に関する業務の問題解決をご提案しています。
紙から電子へ。FAXと帳票の“未来”を切り拓いた20年
クラウドという言葉すらなかった2004年、コクヨが世に送り出したのが、帳票送信サービス「@Tovas(アットトバス)」です。企業間で交わされる「発注書」や「請求書」、「送付状」など、業務に不可欠な帳票類。その送り方を、FAXや郵送に頼る時代から電子送信へと変えていく挑戦が始まりました。
@Tovasが開発された当時は、「電子帳票」「電子送信」という概念すら一般的ではなく、企業の多くが紙文化に強く根付いていました。特にFAXは、信頼性が高い一方で、「送ったかどうか分からない」「誤送信してしまった」「どこに届いたか不明」など、多くの課題も抱えていたのです。
しかし、@Tovasは、こうしたFAXや送付状の「送り方」そのものにテクノロジーで解を提示。20年間の進化を通じて、FAXの課題を乗り越え、発注書などの帳票の電子化を支える社会基盤へと成長してきました。
「@Tovas(アットトバス)」とは?
コクヨの@Tovasは、請求書や納品書、注文書などの帳票を「電子ファイル」「FAX」「郵送」で送受信できるクラウドサービスです。
特長は以下の通りです。
・帳票の種類は問わない
・郵送やFAX業務の自動化・電子化でコスト削減
・直感的なUIによる簡単操作と柔軟なシステム連携
・セキュアな環境と専任サポート
つまり、@Tovasは「帳票送信業務の手間・コスト」を解決します。
紙は減っても帳票は減らない──「アットトバス」の誕生背景
「帳票は、企業間取引の“血液”のようなもの」
そう語るのは、@Tovas開発責任者の渡部氏。@Tovasは2004年、ペーパーレス化の第3波が押し寄せる中で誕生しました。
当時の世の中は「郵送が当たり前」。クラウドどころか、電子帳票の必要性すら疑問視される時代でした。コクヨもまた、伝票や請求書など“紙の帳票”を主力商品としていたからこそ、「紙は減っても、帳票という機能はなくならない」と信じ、電子送信という新たな価値に挑んだのです。
この「送る」に特化したサービスは、社名で、ダジャレを込めて“あっという間に飛ばす”=「@Tovas」と名付けられました。
送った証拠が残る。「改ざん防止」の仕組みが他社との違い
帳票の電子化にあたって、多くの企業が抱える不安は「送った」「届いていない」という“証拠不在”の問題でした。@Tovasはこれを解消するため、外部認証局によるタイムスタンプと改ざん防止ログを活用し、「対顧客間での紛争解決における証拠能力(送信証跡)を十分に担保している」を実現しました。
・送信・受信・開封など、全ての操作をログ化
・データはすべてハッシュ化し、改ざんを完全防止
・外部認証局でタイムスタンプを取得
これにより、紙の「消印」と同等の電子証拠を担保できる、日本でも稀有な電子帳票サービスとなっています。
つまり、@Tovasは「対顧客間での紛争解決における証拠能力(送信証跡)を十分に担保している」と言えます。
FAXは“なくならない”。だからこそ、止まらない仕組みを
FAXというと「古い」「なくなる」と思われがちですが、@TovasではFAX送信の需要は依然として高いといいます。その背景には、「FAXは現場に深く根づいた業務インフラ」であるという事実があります。
だからこそ@Tovasでは、FAX機能の改善に注力しています。
・複数のFAX回線を保持し、障害時も即座に切り替え可能(冗長化設計)
・数百のFAX回線をバックグラウンドに保持し、大量送信にも即時対応
・電子FAXとして、送信記録(証跡)を必ず残す設計
・「送付状付きのFAX」が確実に届いたか、誰が受け取ったかも可視化
つまり、@Tovasは「FAXインフラの止まらない運用」を解決します。
送付状・送り方もDXの対象に
また、特筆すべきは、@Tovasでは送信対象が発注書や請求書などの帳票だけでなく、「送付状」の電子化にも対応している点です。従来はFAX機の前に立ち、1件ずつ送付状を付けて手作業で送るのが当たり前でしたが、今やその“送り方”も自動化されています。
たとえば
・発注書と一緒に送付状を自動添付
・FAXの宛先に応じて、帳票の種類や送付状も分けることが可能
・送付履歴や受信履歴をすべて電子ログで保存
これにより、送信の“安心感”が格段に向上し、DXのハードルを下げることに成功しています。
FAXの“誤送信ゼロ”に挑む
もう一つ注目すべきは、FAXにまつわる誤送信の撲滅。
従来のFAX送信では
・番号入力ミスで他社に誤送信
・送付状が未添付で内容不明
・送信エラーに気づかず再送漏れ
といったトラブルが日常茶飯事でした。
@Tovasではこれをすべて電子化と自動化で解決しました。
・宛先リストをマスター登録 → 人為ミスを排除
・情報トレーサビリティ→送受信の履歴を第三者的に記録・証明
・基幹システムとのシステム連携→FAX送信を自動化
また、「FAXは届いたかわからない」という課題にも、「いつ・どこへ・誰宛に」送ったかが電子ログで即確認できるため、“FAXで送った書類がどこにいるか”すら感じ取れる可視化性を備えています。
現場の“安心感”を重視したUI/UX改善
2004年当初のレガシーなUIは、使い慣れた人向けの画面。しかし、5年前に大幅リニューアルを行い、誰でも直感的に操作できるUIへと刷新しました。
・グローバルメニューから直感的に操作可能
・ワクワク感・共感を生むデザイン
・UX改善で問い合わせや導入障壁を大きく削減
「安心して使える」「面白いから触りたくなる」
そんな気持ちを持ってもらえる設計を目指したと渡部氏は語ります。
発注書電子化の障壁を“後ろ側”で解決
発注書業務の電子化においても、@Tovasは現場の運用負荷を増やさないことを重視。既存の業務フローを変えることなく、裏側でデータ連携を完結できるAPI設計が強みです。
・現場は「今まで通りの操作」でOK
・基幹システム連携はSEチームがサポート
・小規模な構築で導入可能な設計
「送り方」を選ばない。API連携とマルチ出力の哲学
「現場には、現場なりの理由がある。」
紙がなくならないのは、決して時代に逆行しているからではありません。多くの中小企業や物流現場では、FAXや紙による帳票送付が“最適”な送り方であることも多いのです。
@Tovasが掲げる「マルチインプット・マルチアウトput」では、以下のような形で送り方を柔軟に設計可能です:
・発注書をFAXで送る(自動で送付状付き)
・電子帳票をPDFでメール送信
・帳票をクラウドに保管し、URL付きメールで送付
・送り先に応じて送付手段(郵送・FAX・メール)を切り替える
そしてその基盤には強力なAPI連携機能があり、基幹システム(ERP)との連携も可能です。業務を変えずに「送り方だけ変える」ことで、現場の負荷をかけずにDXを推進できるのです。
発注書の電子化をスムーズにする“裏側の工夫”
発注書業務の電子化においては、現場の抵抗感が大きな壁になります。
「操作が変わるのは嫌だ」「帳票の送り方を変えたくない」──そんな声に応えるべく、@Tovasはユーザーインターフェースを変えず、裏側だけを連携・自動化する設計にしています。
・今の発注書を出力するだけで、裏側でTovasが送り先に送信
・操作は従来と同じ。FAXか電子かは自動判別
・送付状や送信履歴はすべて記録・検索可能
これにより、業務フローを変えずに帳票と送付状の電子化が実現します。特に、FAXの利用率が高い業界では、導入後すぐに「ミスが減った」「楽になった」と評価されることが多いそうです。
電子帳票保存法にも即応可能。先を見据えた設計思想
2024年に改正された電子帳票保存法では、より厳格な保存要件が求められるようになりましたが、「@Tovas」にとっては“想定内”だったといいます。
「実は、1998年の法施行当初から対応を視野に入れていました」
と語るのは、20年以上帳票に関わってきた渡部善之氏。
@Tovasでは、全ての帳票を、改ざん不可能なログとして記録。タイムスタンプ付きで外部認証機関に登録され、仮に裁判で証拠として提出する場合でも通用する「デジタル証跡」が残されます。
これは単なる電子送信ではありません。送り方そのものが、ガバナンス対応の一環として設計されている点が、@Tovasの大きな強みです。
2030年の未来を見据えた、完全自動化・完全デジタル化の構想
現在、@Tovasが目指しているのは「完全自動化」「完全デジタル化」の2つの潮流に対応したインフラ基盤づくりです。
すでに下記の機能を実装しております:
1. システム連携を重視したAPI強化
・様々な基幹システムと柔軟に接続可能
2. 帳票種別にこだわらない対応力
・請求書・納品書・注文書など、すべてに対応
3. マルチインプット・マルチアウトプット
・郵送・FAX・電子送信などあらゆる経路に対応
さらに、コクヨでは、帳票入力業務の代行を行うBPO(業務代行)サービスも展開中。入口から出口まで、企業の帳票業務を“丸ごとDX化”するための準備が着実に進められています。
20年の帳票人生が描く、社会課題解決のビジョン
最後に、@Tovasの開発責任者であり、帳票に携わって20年の渡部氏に、その想いを聞きました。
「帳票業務って、実は20年間あまり変わっていないんです。紙はなくならないし、FAXも生き続けている。でも、技術は確実に進化している。だからこそ、送り方や保存方法だけでも変えることができれば、現場は大きく楽になります。」
彼が思い描くのは、帳票・送付状・発注書が“文化として標準化”される未来。企業ごとにバラバラなフォーマットを統一し、APIで簡単に繋がる社会を作ることが、社会課題の解決に繋がると語ります。
FAQ:よくある質問
Q1. 導入にどのくらい時間がかかりますか?
A. 既存フローを変えずに導入できるため、最短数週間で利用開始可能です。
Q2. 小規模事業でも利用できますか?
A. 可能です。小規模構築にも対応しております
Q3. セキュリティ面は大丈夫ですか?
A. データはすべてハッシュ化・外部認証付で改ざん防止。コクヨのセキュア環境で運用されます。
編集後記
帳票という「地味だけれど絶対に必要なもの」を、20年以上かけて磨き続けた@Tovas。その強さは、派手な機能ではなく、止まらない・誤らない・安心できる──そんな“当たり前”を愚直に支える仕組みにありました。
誰もが見過ごしがち、でも絶対に欠かせない“帳票の未来”。
それを支える裏方の挑戦に、改めて敬意を表したいと思います。
この記事は税理士平川文菜の監修を受けています。
この記事を書いた人

平川 文菜(ねこころ)
税理士|熊本出身|2018年京都大学卒業
在学中より税理士試験の勉強を始め、2018年12月に税法三科目(法人・消費・国徴)を同時に合格し、官報合格を果たす。
2018年9月よりBIG4 税理士法人の一つであるKPMG税理士法人において、若手かつ女性という少数の立場ながら2年間にわたり活躍。税務DDやアドバイザリーといった幅広い業務に従事。
2020年9月より、外資系戦略コンサルティングファームであるボストンコンサルティンググループに転職。戦略策定から実行支援まで幅広い業務に従事。2024年12月にフリーランスとして独立。