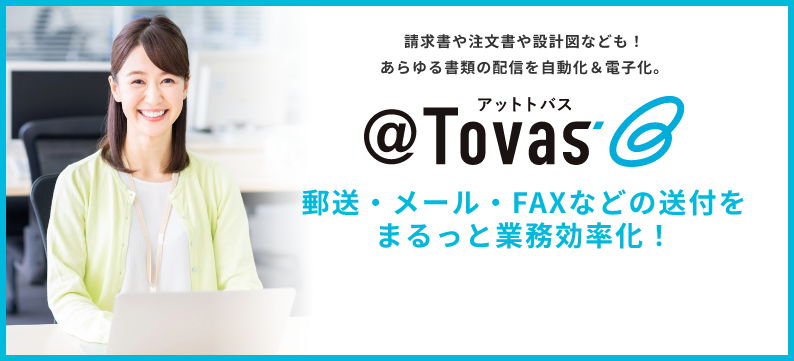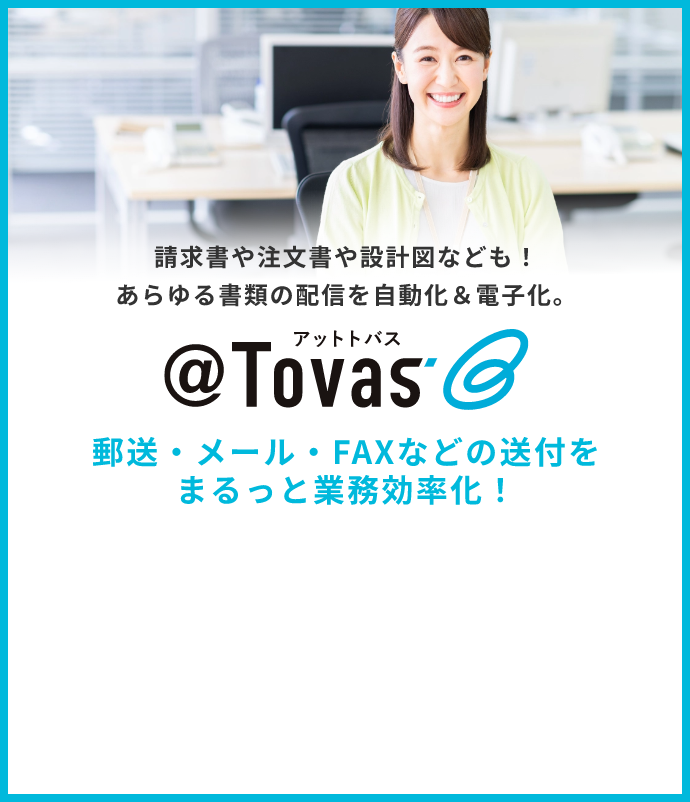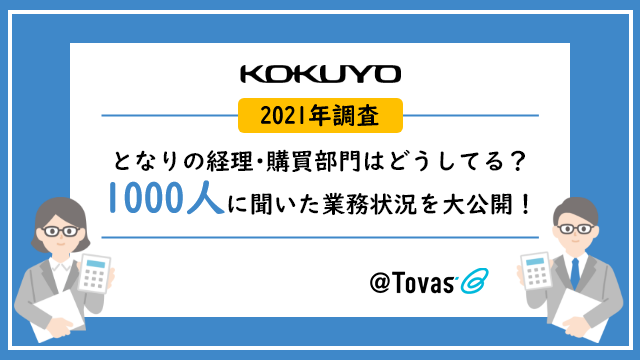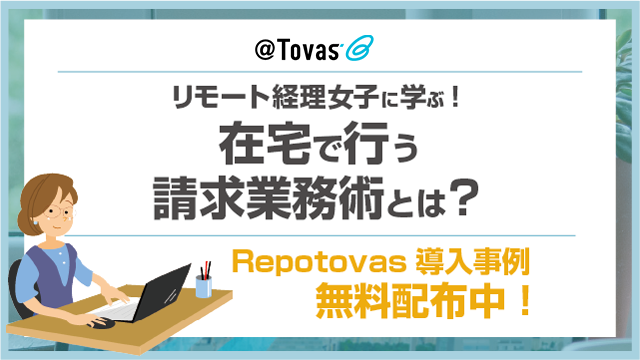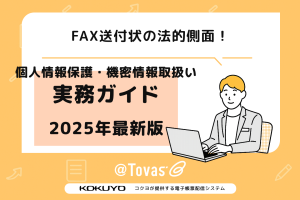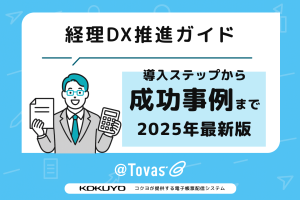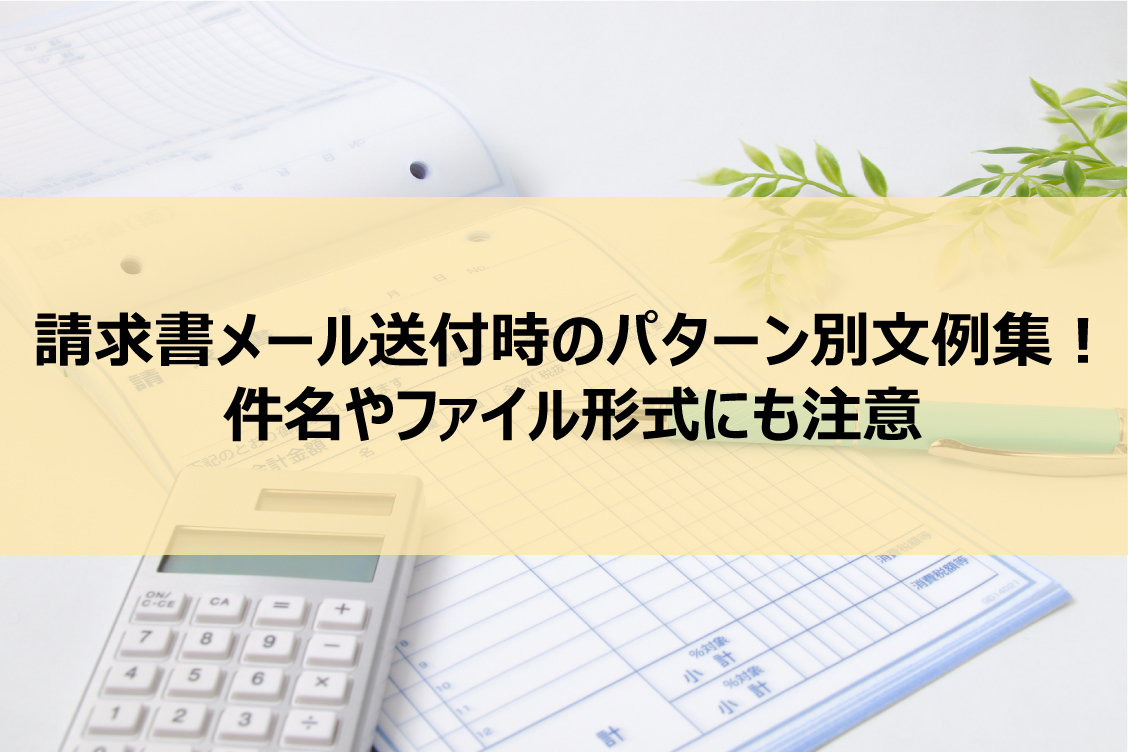
請求書メール送付時のパターン別文例集!件名やファイル形式にも注意
公開日:2022年9月22日 更新日:2024年6月12日
法律上、請求書の送り方に決まりはありません。相手の了承さえ得られれば、データ化したものをメールに添付して送っても問題はありません。しかし請求書をメールで送る場合、どのような文面で送ればよいのかわからない人もいるでしょう。また相手が本来の期限までに入金がない場合は、 どのように催促をすればよいのでしょうか。 この記事では、請求書をメールで送る際の文例や注意点を解説します。具体的に解説しているので、ぜひ参考にしてください。
ご利用件数6,000件以上!コクヨの@Tovasは帳票発行業務の改善・効率化・コスト削減を実現!
TOPICS
請求書をメールで送っても問題ない?
請求書は紙ベースで郵送、というルールで運用している会社も多いかもしれません。そこで最初に、そもそも請求書をデータ化したものをメールで送るのは問題がないのかを解説します。
相手の了承があれば問題ない
結論から言うと、相手の了承があれば問題ありません。法律上、請求書の発行自体が義務付けられているわけではないためです。相手への送付方法の規定もないので、データ化したものをメールで送っても問題ありません。
ただし実務上、相手の了承は必須です。取引があった証明として紙の原本を保存するというルールを設けている場合、やはり紙ベースの請求書を求められるでしょう。請求書をメールで送ってもよいか、あらかじめ取引先に確認することをおすすめします。
請求書をデータ化すれば保存も可能
請求書をデータ化すれば保存も簡単になります。請求書を含む証憑書類は7年間保存しなくてはいけませんが、実際に保存するとなるとスペースを確保したり、すぐに取り出せるよう分類したりする手間がかかるでしょう。そこで活用したいのが、請求書のデータ化です。データ化された状態であれば、紙の請求書に比べると、保存するスペースの確保や分類の手間も大幅に省けます。
なお、請求書を保存する際は方法に気をつけなくてはいけません。2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法では、紙で受け取った請求書であれば、紙のまま保存できますが、データで受け取った請求書を紙に出力して保存すること は認められなくなりました。
2023年12月31日までの2年間はやむを得ない事情があれば宥恕措置を受けられますが、原則として電子取引における電子データの保存は義務になります。
送信側、受信側ともにデータを保存するにあたっては、以下の4つの要件を満たす必要があります。
1.システム概要に関する書類の備え付け
2.見読可能装置の備え付け
3.検索機能の確保
4.データの真実性を担保する措置
請求書の必要項目
請求書の必要項目は次の通りです。なお請求書の送付手段(郵送なのか電子なのか)にかかわらず共通の項目となります。
請求者の氏名
請求者である法人の名称または個人事業主の氏名を記載しましょう。
慣習として住所や請求書発行側の担当者名、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどが記載されることがあったり、会社印が押されたりすることもありますが、仕入税額控除を受ける上でこのような項目は必須ではありません。
取引先名
請求書の宛名欄には、請求相手である取引先の氏名や会社名を正式名称で記載します。株式会社や一般社団法人といった名称も、「(株)」「(一社)」などと略さずに正式名称で記載します。企業によっては、部署名や担当者名の記載が必要な場合があるため、請求書発行前に確認しておきましょう。なお、請求者名と同様に請求先の住所や電話番号などの記載は求められていません。
取引年月日
請求書を作成(発行)した日付を記載します。請求書の発行日とは異なることがありますので注意しましょう。請求書の発行日にルールを定めている企業も多いため、事前に取引先へ確認しておくことが大切です。
取引内容
商品名やサービス名、品名や数量・単価・金額(単価×数量)を記載し、取引内容の詳細を記載します。品名は、商品名だけではなく品番など、自社と相手先の双方にとってわかりやすく記載することが重要です。また、消費税の軽減税率(8%)が混在している場合は、その旨も明記します。
取引金額
合計請求金額の欄には、消費税などを含めた請求金額の総額を税率ごとに分けて記載します。
支払期限
取引先に事前に確認のうえ、支払期限(振込期限)を記載します。「月末締め」の「翌月末払い」「翌々月末払い」など、企業ごとに締日と支払日が決まっているので事前に双方での確認が必要です。
振込先
支払い方法が銀行振込の場合、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人といった振込先情報を記載します。振込手数料をどちらが負担するかについては、事前に取り決めのうえ、請求書にも記載しておきましょう。
請求書をメールで送る際の注意点
請求書をメールで送る際には、いくつか注意すべき点があります。取引先とのトラブルに発展しないためにも、特に以下のポイントには気をつけて手配を進めましょう。
事前に取引先の了承を得る
まず請求書をメールで送ってよいか、取引先の担当者に問い合わせ、了解を得るようにしましょう。請求書の原本を必須としている会社はやはり多いためです。取引先から請求書の原本を送るよう求められた場合は、先にメールで請求書を送ったのちに原本を郵送するとよいでしょう。
加えて初回の取引となる企業とは、あらかじめ請求書をどのように送ればよいかを確認しておくのも、トラブル対策として有効です。
改ざんできないファイル形式で送る
請求書を送る際はPDFなど改ざんしづらいファイル形式で送るのが好ましいでしょう。仮にWordなど改ざんできるファイル形式で送った場合、悪意がある人の手によって内容が書き換えられる可能性は捨てきれません。悪意がなくても、ファイルを開いた際にデータが意図せず変更されたり、自動計算の数式が崩れたりして、思いがけないトラブルにつながります。
またメールを誤送信してしまった場合に備え、ファイルにはパスワードを設定しておきましょう。パスワードが分からなければファイルを開けないため、被害は最小限に食い止められます。
請求書の送付と分かる件名・ファイル名にする
請求書をメールで送る際は「請求書を送った」と相手にわかってもらえる件名・ファイル名にしましょう。人によっては、毎日数十~数百件のメールを受け取っているため、全部を開封しているとは限りません。開封するメールの優先度を、件名から判断している可能性もあります。
そのため件名には「請求書」「○月分の請求書の送付につきまして」などの明記をすることをおすすめします。強調するために「【重要】」「【要確認】」と付け加えておくのも有効です。
また、より確実に開封してもらうためには、メールを送った直後に一度取引先に電話をしましょう。担当者が電話を受けたタイミングで確認し、問題があれば知らせてくれるはずです。
請求書をメールで送るときの文例集
 ここからは請求書をメールで送るときの文例集を紹介します。メールのみで送る場合、後で原本を送る場合、初めてメールで送る場合の3つのパターンを紹介するので、状況に応じて使ってみてください。
ここからは請求書をメールで送るときの文例集を紹介します。メールのみで送る場合、後で原本を送る場合、初めてメールで送る場合の3つのパターンを紹介するので、状況に応じて使ってみてください。
請求書をメールのみで送る場合
まず請求書をメールでのみ送り、原本は送付しない場合の文例です。
件名:【重要: 要ご確認】 ◇月分請求書送付のご案内【作成者の会社名】
[相手先の会社名、部署名、氏名] 様
平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。 [作成者の会社名、部署名、担当者名] と申します。
◇年◇月分の請求書を本メールにて送付いたします。 お手すきの際にご確認いただければ幸いです。
【添付内容】
・御請求書 ファイル名 1通
・請求金額
・お支払い期日
添付ファイルが開封できないなどお気づきの点、ご不明な点がございましたらご一報ください。
誠に勝手ではございますが、 振込手数料は御社にてご負担いただけますよう、お願い申し上げます。
また、請求書の原本をご希望の場合はその旨お知らせください。
別途郵送いたします。
ご多用のところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
メールで送った後で原本を郵送する場合
先にメールで請求書のデータを送ってから、原本を郵送する場合の文例も紹介します
件名: ○月分請求書郵送のご案内 【作成者の会社名】
[相手先の会社名、部署名、氏名]様
お世話になっております。 [作成者の会社名、担当者名] です。
○月分の請求書を本メールへの添付にてお送りいたします。なお、請求書原本も併せて郵送いたしました。
添付ファイルが開封できない、請求書原本が届かないなどの不都合やその他 ご不明な点がございましたら、ご一報いただければ幸いです。
ご多用のところ誠に恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
記
ご請求番号:○○
ご請求金額:○○
お支払期日:○○
添付ファイル:○○
以上
初めてメールで請求書を送る場合
取引先に初めて請求書をメールで送付する場合の文例も紹介します。
件名:○月分請求書送付のご案内 【作成者の会社名】
[相手先の会社名、部署名、氏名] 様
平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。 [作成者の会社名、部署名、担当者名] と申します。
このたびは [商品やサービス名] のご依頼をいただき、ありがとうございました。 改めて感謝申し上げます。
早速ではございますが、 請求書を本メールへの添付にてお送りいたしますので、 ご査収ください。
ご不明な点や添付ファイルが開封できないなどお困りの点がございました ら、たいへんお手数ですがご一報いただければ幸いです。
【添付内容】
・請求書 ファイル名 1通
・請求金額
・お支払期日
ご多用のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
請求書をメールで送るメリット
請求書をメールで送る方法は、さまざまなメリットがあります。具体的なメリットを手間やコスト、テレワークとの相性、トラブル対策の3つの観点から紹介します。
手間やコストを抑えられる
郵送で請求書を送る場合、印刷や宛名書き、封入をする手間や郵便代などのコストがかかります。一方、メールで請求書を送る場合、これらの手間やコストはかかりません。請求書のファイルをPDFなどの改ざんできないファイル形式で作成し、取引先に送れば請求書の送付は完了します。
加えて保存の面でもメリットがあります。前段でもお伝えしたとおり、郵送で請求書を送る場合は紙ベースで保存しますが、数がたまってくると分類・整理する手間や保存するスペースの確保も大変です。メールで請求書を送る場合はデータとして保存できるため、確保すべきスペースや手間は大幅に省けるようになります。
テレワークに対応できる
テレワークを導入している企業であれば、出社せずに請求書を送付できます。
紙で請求書を発行する場合、担当部署の印鑑をもらうために出社を余儀なくされる従業員が出る可能性があります。複数の従業員が持ち回りで担当できるなら問題ありませんが、一部の従業員に負担を強いる結果にもなりかねません。
一方、請求書を電子データで発行するなら電子印鑑で対応可能です。担当者がWeb上のやり取りで確認の上、電子印鑑を押印し、メールでデータを送信すれば出社する必要はなく、一部の従業員に負担を強いる必要もありません。
トラブルの防止になる
請求書をメールで送るのは、トラブル対策としても有効です。請求書を郵送する場合、印刷して封入する際に紛失する可能性があります。また仮に請求書の内容に誤りがあった場合は、正しいものをすぐに送りなおさなければなりません。 再度郵送で送りなおすことになると、取引先に届くまでにさらに時間がかかります。
一方メールで請求書を送れば、請求書を紛失するトラブルは回避できます。万が一送付先を間違えてしまったり、請求書の内容に誤りがあったりしても、早急に対応が可能です。
メールで入金の催促をするときは?
相手にメールで請求書を送ったものの、入金期限日までに入金がなく、遅れる旨の事前連絡もないといった状況の場合、どのように対応するのがよいでしょうか。ここでは入金の催促を行うタイミングや文例を紹介していきます。まずは冷静に状況を確認した上で、入金の催促をしましょう。
催促メールを送るタイミング
入金期日までに入金がなかったからといって、すぐに督促メールを送るのは避けたほうがよいでしょう。
まずは落ち着いて状況を確認する必要があります。例えば相手から入金に関する連絡が来ていないか、社内で再度確認してみましょう。メールではなく電話で入金した旨を伝えてくる場合もあるためです。
また請求書を送ったメールへ相手から返信がなかった場合、相手にメールが届いていない可能性もあるため、相手にメールが届いたかを確認しましょう。
このように、さまざまな確認を行った上で、入金や連絡が確認できない場合は、本来の入金日から1週間程度までを目安に督促メールを送りましょう。
催促メールを送る場合の注意点
本来、支払いは請求書に記載されている期日までに行うのがしかるべき対応です。支払いがなかったら催促すること自体は何ら問題ありません。しかし、伝え方次第では相手との関係が悪化する恐れもあるので、催促メールを送る際には細心の注意を払いましょう。
例えば件名には「【重要】」とつけ、一目で重要と分かるのが望ましいです。そして、相手が高圧的に感じることのないよう、なるべく丁寧な言葉を選びましょう。「行き違いとなっていたらご容赦くださいませ」など、相手がすでに払っていた場合を想定した文言を付け加えるのも効果的です。請求書の送付日や請求番号、支払い期日など、支払いに必要な情報も盛り込みましょう。
入金の催促メール文例
入金の督促を行うメールの文例を紹介します。
件名: 【重要:要ご確認】 ○月分請求書の入金に関するお願い
[相手先の会社名、部署名、氏名] 様
平素より格別のお引き立てをいただき、 御礼申し上げます。 [作成者の会社名、部署名、担当者名] と申します。
さて、過日お送りいたしました○月分請求書につき、◆月◆日現在、弊社にて入金が確認できておりません。
何かのお手違いかとは存じますが、請求書に記載された期日を1週間過ぎております。
大変お手数ではございますが、早急にご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、行き違いでご送金いただいておりました場合は、 何卒ご容赦くださ い。
取り急ぎご連絡まで。
記
ご請求番号:○○
ご請求金額:○○
お支払期日:○○
以上
請求書をメールで送れば経理業務が効率的に!
 請求書をデータ化し、メールで送信すれば経理業務を効率化できます。ただし、会社によっては原本を必須としているケースもあるため、事前に確認しましょう。メールで送信する場合は、本文中で紹介した文例も参考にしてください。
請求書をデータ化し、メールで送信すれば経理業務を効率化できます。ただし、会社によっては原本を必須としているケースもあるため、事前に確認しましょう。メールで送信する場合は、本文中で紹介した文例も参考にしてください。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』なら、請求書などの帳票書類を自動で電子化できます。電子化されたデータは、メール(データをダウンロードできるURL付きメール)やFAXで簡単に送信が可能です。送った請求書の受取確認がメールで受信できたり、管理画面で相手が受け取ったかどうかを簡単に知ることもできます。また、電子化されたデータを提供していただければ、郵送業務の代行もいたします。原本を必須としている取引先がある場合でも、手間をかけずにご対応が可能です。業務効率化を目指すなら、ぜひ導入をご検討ください。
@Tovasマーケティング担当(コクヨ株式会社)