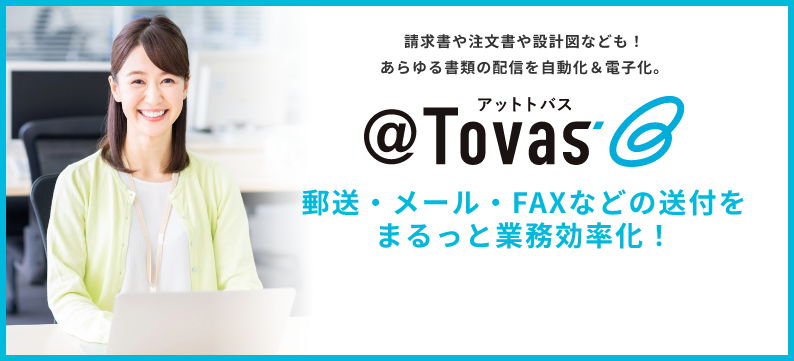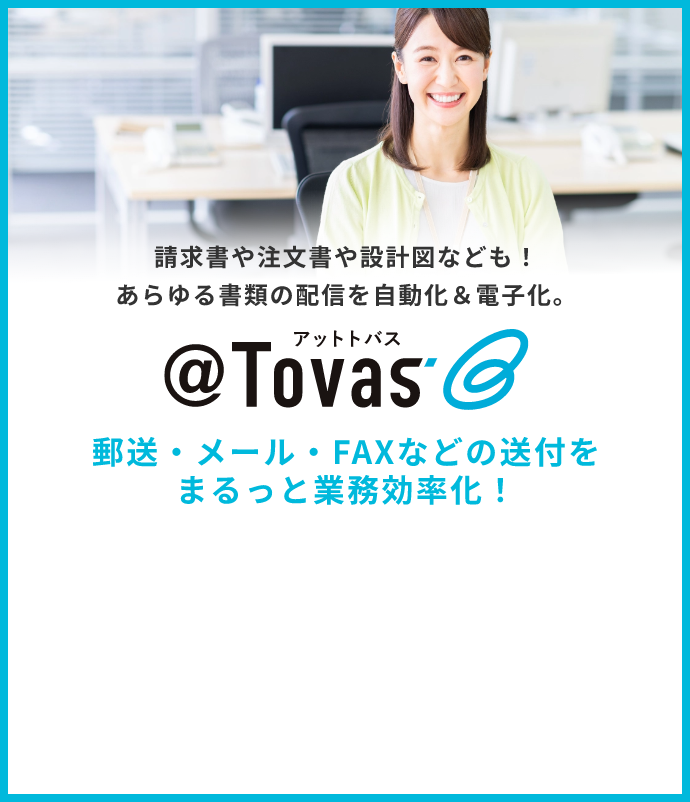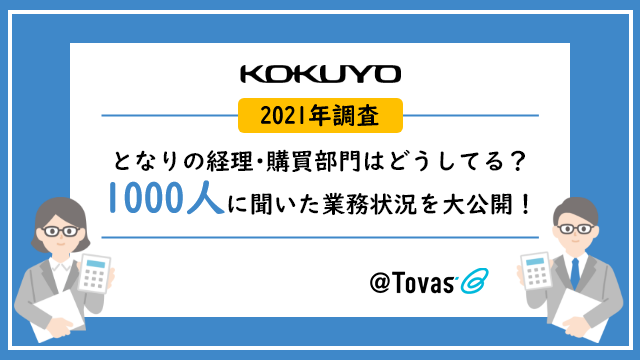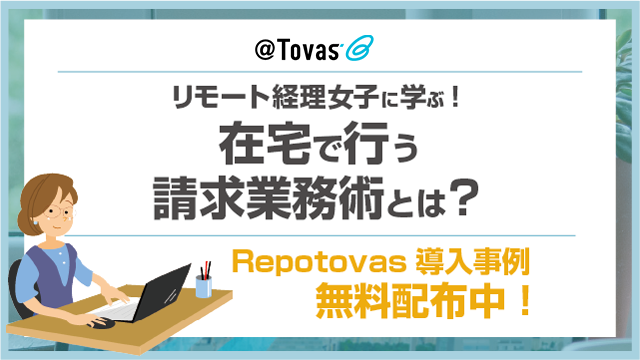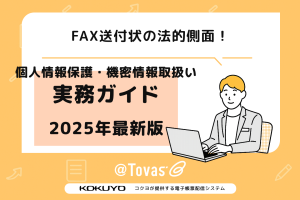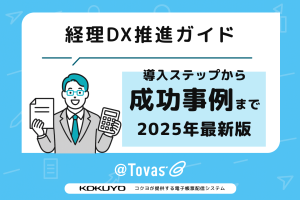電子契約システム比較と法的効力:2025年最新ガイド
公開日:2025年4月10日 更新日:2025年7月27日
企業のDX推進やテレワークの普及に伴い、契約業務のデジタル化が急速に進んでいます。特に電子契約システムの導入は、業務効率化やコスト削減、環境負荷低減など多くのメリットをもたらすため、多くの企業が検討・導入を進めています。しかし、「電子契約は本当に法的に有効なのか」「自社に最適な電子契約システムはどれか」といった疑問を持つ担当者も少なくありません。
本記事では、電子契約の法的効力について詳しく解説するとともに、2025年最新の主要電子契約システムを比較し、自社に最適なシステム選びのポイントを紹介します。電子契約の導入を検討している経営者や担当者の方々にとって、信頼できる情報源となることを目指しています。
ご利用件数6,000件以上!コクヨの@Tovasは帳票発行業務の改善・効率化・コスト削減を実現!
目次
電子契約とは?基本概念と仕組み
電子契約の定義と従来の紙契約との違い
電子契約とは、紙の契約書ではなく電子データ上で契約を締結する方法です。従来の紙契約では、契約書を印刷し、押印や署名を行い、郵送などで相手方とやり取りする必要がありました。一方、電子契約では、契約書のデータに電子署名を付与し、オンライン上でやり取りすることで契約を成立させます。
紙契約と電子契約の主な違い

電子契約の種類
電子契約には、主に以下の3つの種類があります。
1. 当事者型電子署名(電子証明書を用いる方式)
契約当事者自身が電子証明書を取得し、自らの電子署名を契約書に付与する方式です。電子署名法第2条第1項に定められた電子署名に該当し、最も法的効力が高いとされています。
2. 立会人型電子署名(クラウド型電子契約サービス)
電子契約サービス提供事業者が「立会人」となり、契約当事者の指示に基づいて電子署名を行う方式です。利便性が高く、現在最も普及している電子契約の形態です。2020年に総務省・法務省・経済産業省から「立会人型電子契約サービスも電子署名法の要件を満たす場合がある」との見解が示されました。
3. リモート署名(クラウドに保管された電子証明書を利用)
利用者の電子証明書をクラウド上に保管し、必要なときにリモートで利用する方式です。当事者型の利便性を高めた方式として注目されています。
電子契約の基本的な流れと仕組み
電子契約の基本的な流れは以下の通りです。
1. 契約書の作成契約書をWord、Excel、PDFなどで作成します。多くの電子契約システムでは、テンプレート機能も提供されています。
2. 契約書のアップロード作成した契約書を電子契約システムにアップロードします。
3. 署名依頼の送信契約相手に対して、電子メールなどで署名依頼を送信します。
4. 本人確認と電子署名契約当事者は、システムにログインし、本人確認を経て電子署名を行います。
5. 契約の成立すべての当事者が署名を完了すると、契約が成立します。
6. 契約書の保存成立した契約書は、電子データとして保存されます。多くのシステムでは、タイムスタンプが付与され、改ざん防止措置が講じられます。
電子契約の法的効力
電子署名法の概要と2025年最新の法的枠組み
電子契約の法的効力は、主に「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」によって規定されています。2001年に施行されたこの法律は、電子署名に手書きの署名や押印と同等の法的効力を与えることを目的としています。
電子署名法第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。つまり、適切な電子署名が付された電子契約書は、紙の契約書と同等の法的効力を持つことが法律で認められているのです。
2025年現在、電子署名法に加えて、以下の法律や指針も電子契約の法的枠組みを形成しています。
・ デジタル社会形成整備法(2021年施行)書面・押印・対面規制の見直しを行い、電子契約の適用範囲を拡大
・ 電子帳簿保存法(最新改正2022年)電子取引データの保存要件を規定
・ 民法(債権法改正2020年施行)契約の成立要件として書面性を求めていない
電子契約の法的有効性の要件
電子契約が法的に有効であるためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
1. 本人性(誰が署名したかの識別)
電子署名が本人によって行われたことを証明できる必要があります。これは、以下のような方法で担保されます。
・ 電子証明書による本人確認
・ 多要素認証(パスワードとSMSなど複数の認証方法の組み合わせ)
・ 生体認証(指紋、顔認証など)
2. 非改ざん性(内容が署名後に変更されていないこと)
電子署名後に契約内容が改ざんされていないことを証明できる必要があります。これは、以下のような技術で担保されます。
・ ハッシュ関数による改ざん検知
・ タイムスタンプによる存在証明
・ ブロックチェーン技術の活用
電子署名の種類と法的効力の違い
電子署名には、法的効力の強さによって以下の3つの種類があります。
1. 認定認証事業者が発行する電子証明書を用いた電子署名
電子署名法に基づく認定認証事業者(日本トラストテクノロジー協会など)が発行する電子証明書を用いた電子署名です。最も法的効力が高く、「電子署名法第3条の推定効」が働きます。
2. 認定認証事業者以外が発行する電子証明書を用いた電子署名
民間の認証事業者が発行する電子証明書を用いた電子署名です。電子署名法第3条の推定効は直接的には働きませんが、技術的に本人性と非改ざん性が担保されていれば、実質的に有効な証拠となります。
3. 電子契約サービス提供事業者による立会人型電子署名
クラウド型電子契約サービスで用いられる電子署名です。2020年9月に公表された3省(総務省・法務省・経済産業省)のQ&Aにより、一定の要件を満たせば電子署名法第3条の推定効が働く可能性があることが示されました。
電子契約の証拠能力と裁判での扱い
電子契約は、以下の条件を満たしていれば、裁判においても有効な証拠として認められます。
1. 真正性の証明電子署名やタイムスタンプにより、契約内容の真正性が証明できること
2. 完全性の証明契約締結後に内容が改ざんされていないことが証明できること
3. 保存性の証明法定保存期間中、適切に保存されていたことが証明できること
実際の裁判例でも、適切に電子署名が付された電子契約書は有効な証拠として認められています。2025年現在、電子契約の有効性を否定した裁判例はほとんどなく、適切に運用されていれば紙の契約書と同等以上の証拠能力を持つと考えられています。
電子契約にできる契約書とできない契約書
電子契約が可能な主な契約書
2025年現在、ほとんどの契約書は電子契約で締結することが可能です。主な例としては以下のようなものがあります。
・ 取引基本契約書
・ 秘密保持契約書(NDA)
・ 雇用契約書
・ 労働者派遣契約書
・ 売買契約書
・ 請負契約書
・ 委任契約書
・ 業務委託契約書
・ 代理店契約書
・ フランチャイズ契約書
・ 注文書・注文請書
また、2022年5月の宅地建物取引業法・借地借家法等の改正により、不動産売買・賃貸借等に関する契約書や重要事項説明書についても電子契約による完全電子化が可能となりました。
電子契約にできない契約書(2025年現在)
一方で、2025年現在でも電子契約にできない契約書が一部存在します。これらは主に、法律により公正証書での作成が義務付けられているものです。

これらの契約書については、公正証書によって契約を締結すべきことが法律で定められているため、現状は書面での締結が必要となります。ただし、公正証書についても電子化を認める範囲や時期について検討が進められており、将来的には電子署名によって作成することが認められる可能性があります。
相手方の承諾・希望が必要な契約書
電子契約の利用は可能なものの、契約相手方の承諾・希望・請求が必要な契約書も存在します。主な例としては以下のようなものがあります。
相手方の「承諾」が必要なもの
・ 建設工事の請負契約書(建設業法19条3項)
・ 下請事業者に対して交付する「給付の内容」等記載書面(下請法3条2項)
・ 宅地建物の売買・交換・賃借の際の重要事項説明書(宅建業法35条8項、9項)
・ 特定商取引における契約書面(改正特商法第4条第2項など)
相手方の「希望」が必要なもの
・ 労働条件通知書面(労働基準法15条1項、施行規則5条4項)
・ 派遣労働者への就業条件明示書面(派遣法34条、施行規則26条1項2号)
相手方の「請求」が必要なもの
・ 金銭支払の受取証書(民法486条2項)
不動産契約・労働契約における電子契約の最新動向
不動産契約の電子化
2022年5月18日以降、宅地建物取引業法・借地借家法等の改正により、不動産売買・賃貸借等に関する契約書や重要事項説明書についても電子契約による完全電子化が可能となりました。これにより、不動産取引のデジタル化が大きく進展しています。
ただし、電子契約を行うためには、取引相手の承諾を得る必要があります。また、重要事項説明については、テレビ会議等のITを活用した説明が認められていますが、説明自体は宅地建物取引士が行う必要があります。
労働契約の電子化
労働契約についても電子契約が可能ですが、労働条件通知書については労働者の希望がある場合には書面で交付する必要があります(労働基準法施行規則5条4項)。
2025年現在、多くの企業が採用手続きや雇用契約の電子化を進めており、特にリモートワークの普及に伴い、電子契約による労働契約の締結が一般的になりつつあります。
電子契約システム導入のメリット
コスト削減効果
電子契約システムを導入することで、以下のようなコスト削減効果が期待できます。
1. 印紙税の削減
紙の契約書には、契約金額に応じて印紙税が課税されますが、電子契約では印紙税が課税されません。例えば、1億円の請負契約の場合、紙の契約書では6万円の印紙税がかかりますが、電子契約ではこのコストが完全に削減できます。
2. 郵送費・交通費の削減
契約書の郵送費や、契約締結のための出張費などが削減できます。特に海外との契約や、複数拠点間での契約が多い企業では、大きなコスト削減効果が期待できます。
3. 保管コストの削減
紙の契約書を保管するためのキャビネットやスペースが不要になります。また、契約書の検索や管理のための人件費も削減できます。
4. 印刷コストの削減
契約書の印刷にかかる用紙代やトナー代、プリンターの維持費などが削減できます。
業務効率化
電子契約システムの導入により、契約業務が大幅に効率化されます。
1. 契約締結時間の短縮
紙の契約書では、印刷、押印、郵送、受領、保管という一連のプロセスに数日から数週間かかることがありますが、電子契約では数分から数時間で完了することが可能です。
2. 契約管理工数の削減
電子契約システムでは、契約書の検索や管理が容易になります。契約の期限管理や更新管理も自動化できるため、管理工数が大幅に削減されます。
3. 承認フローの効率化
電子契約システムでは、承認フローを電子化・自動化できるため、承認プロセスが効率化されます。承認者の不在時にも代理承認の設定などで対応できるため、契約締結の遅延を防ぐことができます。
4. テンプレート活用による作業効率化
多くの電子契約システムでは、契約書のテンプレート機能が提供されています。これにより、契約書作成の効率化と標準化が図れます。
セキュリティ強化と透明性の向上
電子契約システムの導入により、セキュリティと透明性が向上します。
1. 改ざん防止
電子署名やタイムスタンプにより、契約書の改ざんを防止・検知することができます。
2. アクセス制御
電子契約システムでは、契約書へのアクセス権限を細かく設定できるため、情報漏洩のリスクを低減できます。
3. 監査証跡の記録
誰がいつ契約書を作成、閲覧、署名したかという履歴が自動的に記録されるため、契約プロセスの透明性が向上します。
4. バックアップと災害対策
電子データはバックアップが容易であり、災害時のデータ消失リスクを低減できます。
テレワーク・リモートワーク対応
電子契約システムは、テレワークやリモートワークとの親和性が高く、場所を問わない働き方を支援します。
1. 場所を問わない契約締結
インターネット環境があれば、オフィス以外の場所からでも契約締結が可能です。
2. モバイル対応
多くの電子契約システムでは、スマートフォンやタブレットからも契約書の確認や署名が可能です。
3. グローバル対応
海外との契約も、時差を気にせずスムーズに締結できます。
環境負荷の低減
電子契約システムの導入は、環境負荷の低減にも貢献します。
1. 紙の使用量削減
契約書の印刷が不要になるため、紙の使用量が削減されます。
2. CO2排出量の削減
紙の生産、輸送、廃棄に伴うCO2排出量が削減されます。また、契約締結のための移動が減ることで、交通機関によるCO2排出量も削減されます。
3. 森林資源の保護
紙の使用量が減ることで、森林資源の保護につながります。
電子契約システム選定のポイント
自社の契約業務の分析方法
電子契約システムを選定する前に、自社の契約業務を分析することが重要です。以下のポイントを確認しましょう。
1. 契約書の種類と数量
・ どのような種類の契約書を、月間・年間どれくらいの数量で取り扱っているか
・ 定型的な契約と非定型的な契約の割合
2. 契約フローの把握
・ 契約書の作成から締結、保管までのフロー
・ 承認プロセスの複雑さと承認者の数
・ 契約締結までの平均所要時間
3. 契約相手の特性
・ 取引先の数と規模
・ 海外取引先の有無
・ 取引先の電子契約への対応状況
4. 法的要件の確認
・ 取り扱う契約書の法的要件(電子化の可否、相手方の承諾の必要性など)
・ 業界特有の規制や慣行
5. システム連携の必要性
・ 既存の基幹システムや文書管理システムとの連携の必要性
・ APIの活用可能性
電子契約システム選定の7つの評価基準
電子契約システムを選定する際の主な評価基準は以下の通りです。
1. 機能性
・ 契約書テンプレート機能
・ 承認ワークフロー機能
・ 一括送信機能
・ リマインダー機能
・ 契約管理機能(期限管理、更新管理など)
・ 検索機能
2. 使いやすさ
・ ユーザーインターフェースの直感性
・ 操作の簡便さ
・ モバイル対応
・ 多言語対応
3. セキュリティ
・ 認証方式(多要素認証、生体認証など)
・ データの暗号化
・ アクセス制御
・ SOC2、ISMSなどの認証取得状況
4. 法的要件への対応
・ 電子署名法への対応
・ 電子帳簿保存法への対応
・ タイムスタンプの付与
・ 監査証跡の記録
5. 他システムとの連携性
・ API提供の有無
・ 基幹システムとの連携実績
・ 文書管理システムとの連携実績
・ シングルサインオン対応
6. サポート体制
・ サポート時間と方法(電話、メール、チャットなど)
・ 導入支援の充実度
・ トレーニングプログラムの有無
・ マニュアルやナレッジベースの充実度
7. コストパフォーマンス
・ 初期費用と月額費用のバランス
・ 契約数や利用者数に応じた料金体系
・ 追加機能のオプション料金
・ 費用対効果の見込み
2025年最新!主要電子契約システム比較
大企業向け電子契約システム比較
1. GMOサイン
・ 特徴350万社以上の導入実績を持つ国内最大級の電子契約サービス。官公庁での導入実績も多数。
・ 主な機能電子契約、電子サイン、ワークフロー、API連携、テンプレート管理
・ セキュリティISO27001取得、SOC2 Type2報告書取得
・ 強み国内最大級の導入実績、手厚いサポート体制、多彩な連携機能
2. クラウドサイン
・ 特徴弁護士ドットコムが提供する法的知見を活かした電子契約サービス。
・ 主な機能電子契約、テンプレート管理、承認フロー、契約管理、API連携
・ セキュリティISO27001取得、SOC2 Type2報告書取得
・ 強み法的知見の豊富さ、使いやすいUI、充実した契約管理機能
3. DocuSign
・ 特徴世界180カ国以上で利用されているグローバルスタンダードの電子契約サービス。
・ 主な機能電子署名、契約管理、テンプレート管理、API連携、多言語対応
・ セキュリティISO27001取得、SOC2 Type2報告書取得、GDPR対応
・ 強みグローバル対応力、多言語・多通貨対応、豊富な導入実績
4. Adobe Sign
・ 特徴Adobe社が提供する電子署名サービス。Adobe製品との連携が強み。
・ 主な機能電子署名、ワークフロー、テンプレート管理、API連携、Adobe製品連携
・ セキュリティISO27001取得、SOC2 Type2報告書取得
・ 強みAdobe製品との連携、使いやすいUI、グローバル対応
中小企業向け電子契約システム比較
1. マネーフォワード クラウド契約
・ 特徴マネーフォワードの会計・経費精算システムと連携できる電子契約サービス。
・ 主な機能電子契約、テンプレート管理、承認フロー、マネーフォワード製品連携
・ セキュリティISO27001取得
・ 強みマネーフォワード製品との連携、使いやすいUI、コストパフォーマンスの高さ
2. freee契約
・ 特徴freeeの会計・人事労務システムと連携できる電子契約サービス。
・ 主な機能電子契約、テンプレート管理、承認フロー、freee製品連携
・ セキュリティISO27001取得
・ 強みfreee製品との連携、使いやすいUI、低コスト
3. ベクターサイン(旧・みんなの電子署名)
・ 特徴低コストで導入できる国産の電子契約サービス。
・ 主な機能電子契約、テンプレート管理、承認フロー、契約管理
・ セキュリティISO27001取得
・ 強み低コスト、シンプルな操作性、充実したサポート
無料・低コストで利用できる電子契約システム
1. GMOサイン フリープラン
・ 特徴GMOサインの無料プラン。月間3通まで無料で利用可能。
・ 主な機能電子契約の基本機能
・ 制限月間3通まで、保存期間1年、テンプレート機能なし
・ 強み大手サービスの安心感、無料でも基本機能は利用可能
2. クラウドサイン フリートライアル
・ 特徴クラウドサインの30日間無料トライアル。
・ 主な機能電子契約の全機能を試用可能
・ 制限30日間の期間制限
・ 強み全機能を試せる、導入前の検証に最適
3. 電子印鑑GMOサイン スタータープラン
・ 特徴GMOサインの低コストプラン。
・ 主な機能電子契約の基本機能
・ 強み低コスト、必要最小限の機能を利用可能
業種別おすすめ電子契約システム
1. 不動産業
・ おすすめクラウドサイン、GMOサイン
・ 理由不動産特化のテンプレート提供、宅建業法対応、重要事項説明対応
2. 建設業
・ おすすめGMOサイン、FAST SIGN
・ 理由建設業法対応、下請法対応、工事関連書類のテンプレート提供
3. IT・サービス業
・ おすすめDocuSign、クラウドサイン
・ 理由API連携の充実、英語対応、グローバル対応
4. 製造業
・ おすすめGMOサイン、WAN-Sign
・ 理由基幹システム連携、大量契約処理、取引先管理機能
5. 金融・保険業
・ おすすめDocuSign、Adobe Sign
・ 理由高度なセキュリティ、コンプライアンス対応、監査証跡の充実
*料金等については各サービスサイト・カタログ等をご確認ください。
電子契約システム導入の流れとポイント
導入前の準備と社内体制の整備
電子契約システムを導入する前に、以下の準備を行いましょう。
1. 推進体制の構築
・ プロジェクトリーダーの選定
・ 関連部門(法務、IT、総務など)のメンバーを含めたプロジェクトチームの編成
・ 経営層の承認と支援の確保
2. 現状分析と課題の洗い出し
・ 現在の契約業務フローの可視化
・ 課題と改善ポイントの特定
・ 電子契約導入による効果の試算
3. 要件定義
・ 必要な機能の洗い出し
・ 優先順位の設定
・ 導入スケジュールの策定
4. 予算確保
・ 初期費用と運用費用の見積もり
・ 費用対効果の算出
・ 予算申請と承認
導入手順と段階的アプローチ
電子契約システムの導入は、段階的に進めることをお勧めします。
1. パイロット導入
・ 特定の部門や契約種類に限定して試験導入
・ 操作性や効果の検証
・ 課題の洗い出しと改善
2. 範囲の拡大
・ パイロット導入の結果を踏まえ、対象部門や契約種類を拡大
・ 運用ルールの調整
・ 社内教育の実施
3. 全社展開
・ 全社的な導入
・ 定着化のためのフォローアップ
・ 効果測定と継続的な改善
社内規程の整備と運用ルールの策定
電子契約システムを導入する際は、社内規程や運用ルールの整備が重要です。
1. 電子契約運用規程の策定
・ 電子契約の対象範囲
・ 電子署名の権限と責任
・ 承認フローのルール
・ 例外処理の方法
2. 文書管理規程の改定
・ 電子契約書の保存方法
・ 保存期間
・ アクセス権限
・ バックアップ方法
3. 情報セキュリティポリシーの見直し
・ 電子契約に関するセキュリティ要件
・ パスワード管理ルール
・ インシデント対応手順
従業員教育と取引先への案内
電子契約システムの導入を成功させるためには、関係者への適切な教育と案内が不可欠です。
1. 従業員教育
・ 操作研修の実施
・ マニュアルの整備
・ ヘルプデスクの設置
・ FAQ集の作成
2. 取引先への案内
・ 電子契約導入の目的と効果の説明
・ 操作方法の案内
・ 問い合わせ窓口の設置
・ 段階的な移行計画の共有
3. フォローアップ
・ 定期的な利用状況の確認
・ 課題の収集と改善
・ 好事例の共有
導入後の効果測定と改善
電子契約システム導入後は、効果を測定し、継続的に改善することが重要です。
1. 効果測定の指標
・ 契約締結までの時間短縮
・ コスト削減額(印紙税、郵送費、人件費など)
・ 契約管理工数の削減
・ ユーザー満足度
2. 定期的なレビュー
・ 月次・四半期ごとの利用状況レビュー
・ 課題の洗い出しと改善策の検討
・ システム改善要望の収集
3. 継続的な改善
・ 運用ルールの見直し
・ 教育プログラムの改善
・ システム機能の拡張検討
電子契約の保存と管理
電子帳簿保存法の要件と対応方法
電子契約書は「電子取引」に該当するため、電子帳簿保存法に基づいた保存が必要です。2022年の法改正により、電子取引データは電子データのまま保存することが義務化されました。
電子帳簿保存法の主な要件
1. 真実性の確保(改ざん防止措置)
・ タイムスタンプの付与
・ 改ざん検知機能の実装
・ 訂正・削除の履歴保存
2. 可視性の確保(見読性の確保)
・ ディスプレイ、プリンタ等の備付け
・ 整然とした形式での出力
・ 7年間の閲覧可能性の確保
3. 検索性の確保
・ 取引年月日、取引金額、取引先で検索可能
・ 日付範囲指定検索
・ ファイル名の規則性確保
対応方法
・ 電子契約システムの保存機能を活用
・ 文書管理システムとの連携
・ バックアップの定期的な実施
・ 検索機能の確認と整備
電子契約の保存期間と保存方法
保存期間
電子契約書の保存期間は、契約の種類や関連法令によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
・ 法人税法・消費税法関連7年間
・ 商法関連10年間
・ 不動産関連20年間以上
・ 労働契約関連退職後3年間以上
保存方法
1. 電子契約システム内での保存
・ 多くの電子契約システムでは、契約書の長期保存機能を提供
・ タイムスタンプの自動付与
・ アクセス権限管理
2. 文書管理システムでの保存
・ 電子契約システムから文書管理システムへのエクスポート
・ メタデータの付与
・ 体系的な分類と管理
3. ローカル環境での保存
・ 専用フォルダでの管理
・ 定期的なバックアップ
・ アクセス制限の設定
検索性・見読性の確保
電子契約書を適切に管理するためには、検索性と見読性の確保が重要です。
検索性の確保
・ メタデータの活用契約日、契約相手、契約種類などのメタデータを付与
・ 全文検索機能契約書の内容を全文検索できる機能の活用
・ 分類体系の整備契約書を体系的に分類し、検索しやすくする
見読性の確保
・ 標準フォーマットの採用PDF/Aなどの長期保存に適したフォーマットの採用
・ 閲覧環境の整備契約書を閲覧するためのソフトウェアの確保
・ 印刷機能の確保必要に応じて印刷できる環境の整備
バックアップと災害対策
電子契約書の消失を防ぐためには、適切なバックアップと災害対策が必要です。
バックアップ
・ 定期的なバックアップ日次・週次・月次でのバックアップ
・ 複数媒体への保存クラウドストレージと物理メディアの併用
・ 世代管理複数世代のバックアップを保持
災害対策
・ 地理的分散データセンターの地理的分散
・ 冗長化システムの冗長化によるダウンタイムの最小化
・ 復旧手順の整備災害時の復旧手順の文書化と訓練
電子契約に関するよくある質問
電子契約は本当に法的に有効?
回答:はい、適切に電子署名が付された電子契約書は、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。これは「電子署名法」によって明確に規定されています。電子署名法第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。
ただし、法的効力を確実に担保するためには、以下の点に注意が必要です。
・ 本人性(署名者の本人確認)が確保されていること
・ 非改ざん性(署名後に内容が変更されていないこと)が確保されていること
・ 電子署名の方式が適切であること
電子契約で印紙税はかからない?
回答:はい、電子契約書には印紙税はかかりません。印紙税法では、課税文書は「紙」に記載されたものと定義されているため、電子データである電子契約書は課税対象外となります。これは国税庁の見解でも明確に示されています。
例えば、1億円の請負契約の場合、紙の契約書では6万円の印紙税がかかりますが、電子契約では印紙税が完全に不要となります。契約数が多い企業では、電子契約の導入により大幅なコスト削減が可能です。
海外取引先との電子契約は可能?
回答:はい、海外取引先との電子契約も可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
1. 準拠法の確認契約の準拠法を明確にし、その法域での電子契約の有効性を確認する
2. 言語対応電子契約システムが多言語に対応しているか確認する
3. 時差への配慮締結プロセスにおける時差の影響を考慮する
4. 国際的な電子署名規格eIDAS(EU)やESIGN Act(米国)など、各国・地域の電子署名規格への対応を確認する
グローバル展開している電子契約サービス(DocuSign、Adobe Signなど)は、多くの国の法的要件に対応しています。
電子契約の導入コストはどれくらい?
回答:電子契約システムの導入コストは、サービスの種類、契約数、ユーザー数などによって異なります。一般的な価格帯は以下の通りです。
初期費用
・ 無料~50万円程度(システムによる)
・ 導入支援やカスタマイズが必要な場合は追加費用が発生
月額費用
・ 小規模企業向け3,000円~15,000円程度
・ 中規模企業向け15,000円~50,000円程度
・ 大規模企業向け50,000円~数十万円程度
従量課金
・ 契約数に応じた従量課金制を採用しているサービスもあり
・ 1通あたり数百円~数千円程度
費用対効果の観点では、印紙税の削減、郵送費の削減、業務効率化による人件費削減などのメリットと比較して検討することが重要です。
電子契約のセキュリティは安全?
回答:適切に設計・運用されている電子契約システムは、紙の契約書よりも高いセキュリティを確保できます。主なセキュリティ対策は以下の通りです。
1. データの暗号化通信経路の暗号化(SSL/TLS)やデータ保存時の暗号化
2. アクセス制御多要素認証、IPアドレス制限、アクセス権限の細かな設定
3. 監査証跡誰がいつ何をしたかの記録
4. 改ざん防止電子署名やタイムスタンプによる改ざん検知
5. セキュリティ認証ISO27001、SOC2などの第三者認証
ただし、セキュリティを確保するためには、ユーザー側でも以下の点に注意が必要です。
・ パスワードの適切な管理
・ 不審なメールやフィッシングへの警戒
・ アクセス権限の適切な設定
・ 定期的なセキュリティ教育
電子契約システム選びのチェックリスト
自社に最適な電子契約システムの選び方
電子契約システムを選ぶ際は、以下のステップで進めることをお勧めします。
1. 自社の契約業務を分析する
・ 契約書の種類と数量
・ 契約フローの複雑さ
・ 契約相手の特性
2. 優先すべき機能を明確にする
・ 必須機能と優先度
・ 将来的に必要となる機能
3. 複数のシステムを比較検討する
・ 機能面の比較
・ コスト面の比較
・ サポート体制の比較
4. トライアルを活用する
・ 実際に操作して使い勝手を確認
・ 社内の関係者からフィードバックを収集
5. 導入計画を立てる
・ 段階的な導入スケジュール
・ 教育・周知計画
・ 効果測定の方法
導入前の確認事項リスト
電子契約システムを導入する前に、以下の項目を確認しましょう。
機能面
・ 必要な電子署名方式に対応しているか
・ 承認フローのカスタマイズが可能か
・ テンプレート機能は充実しているか
・ 契約管理機能は十分か
・ 検索機能は使いやすいか
技術面
・ セキュリティ対策は十分か
・ 既存システムとの連携は可能か
・ モバイル対応しているか
・ 障害時の対応体制は整っているか
・ バックアップ体制は整っているか
運用面
・ サポート体制は充実しているか
・ マニュアルや教育資料は整備されているか
・ 導入支援サービスはあるか
・ バージョンアップの頻度と方法
・ 契約終了時のデータ移行方法
コスト面
・ 初期費用と月額費用のバランス
・ 追加料金が発生する条件
・ 費用対効果の試算
・ 契約期間と解約条件
@Tovasによる電子契約ソリューションの紹介
コクヨの@Tovasは、電子契約を含む電子帳票配信システムとして、多くの企業に導入されています。@Tovasの電子契約ソリューションの特徴は以下の通りです。
@Tovasの主な特徴
1. 基幹システムとの連携
・ 既存の基幹システムと連携し、契約書データを自動取得
・ 契約書の自動生成と配信
2. 多様な配信方法
・ 電子契約だけでなく、郵送、FAX、メールなど多様な配信方法に対応
・ 取引先の状況に応じた柔軟な対応が可能
3. セキュリティ対策
・ ISO27001取得
・ 厳格なアクセス制御
・ データの暗号化
4. 法的要件への対応
・ 電子署名法対応
・ 電子帳簿保存法対応
・ タイムスタンプの自動付与
5. 使いやすさ
・ 直感的なユーザーインターフェース
・ 充実したテンプレート機能
・ 分かりやすい操作ガイド
@Tovasの導入により、契約業務の効率化、コスト削減、ペーパーレス化を実現し、企業のDX推進に貢献します。詳細については、@Tovasの公式サイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
まとめ
電子契約システムの導入は、業務効率化、コスト削減、環境負荷低減など多くのメリットをもたらします。2025年現在、電子署名法や関連法令の整備により、ほとんどの契約書が電子契約で締結可能となっています。
電子契約システムを選ぶ際は、自社の契約業務の特性を分析し、機能性、使いやすさ、セキュリティ、法的要件への対応、他システムとの連携性、サポート体制、コストパフォーマンスなどの観点から総合的に評価することが重要です。
また、導入にあたっては、段階的なアプローチ、社内規程の整備、従業員教育、取引先への案内など、計画的に進めることがポイントです。
電子契約の法的効力や保存要件についても正しく理解し、適切に運用することで、契約業務の大幅な効率化と高度化を実現しましょう。
@Tovasマーケティング担当(コクヨ株式会社)