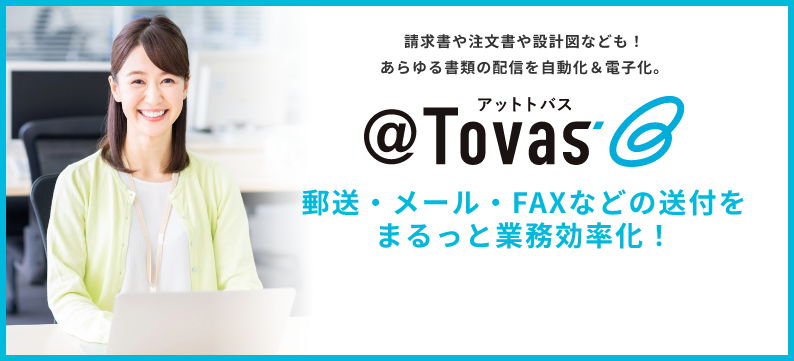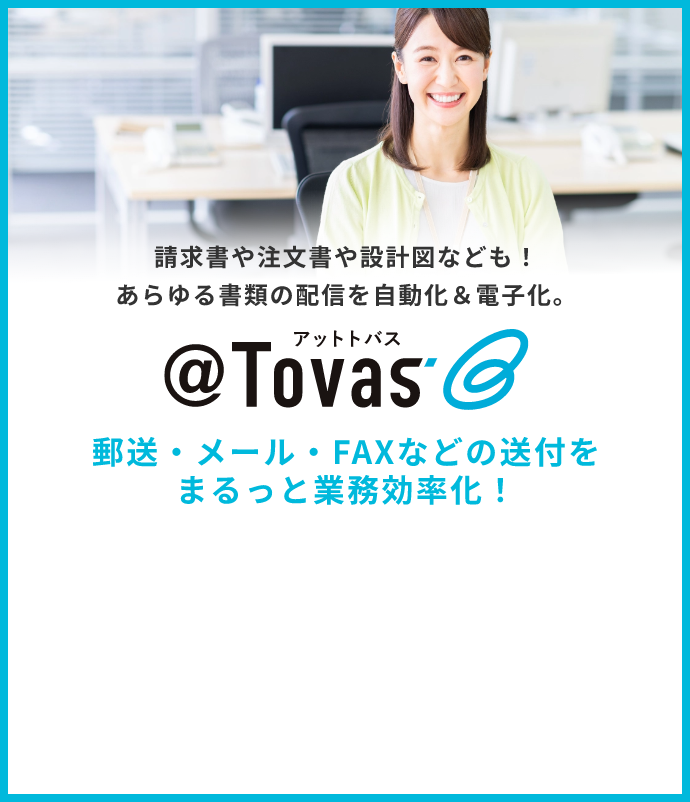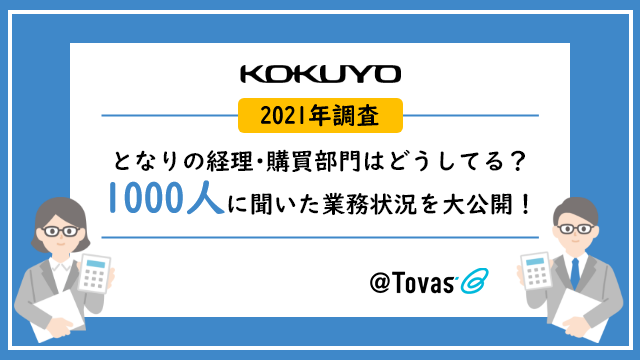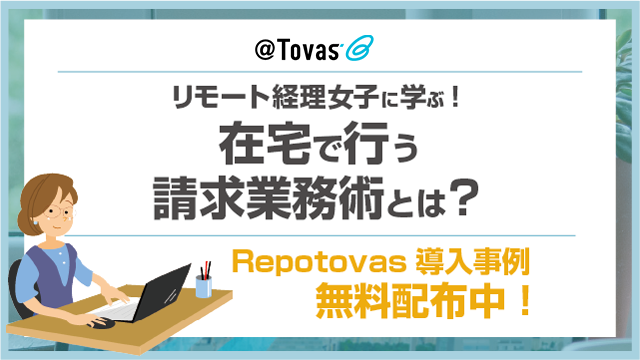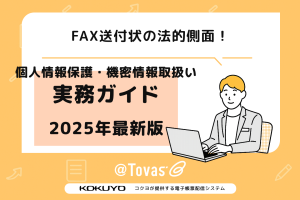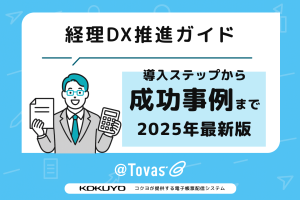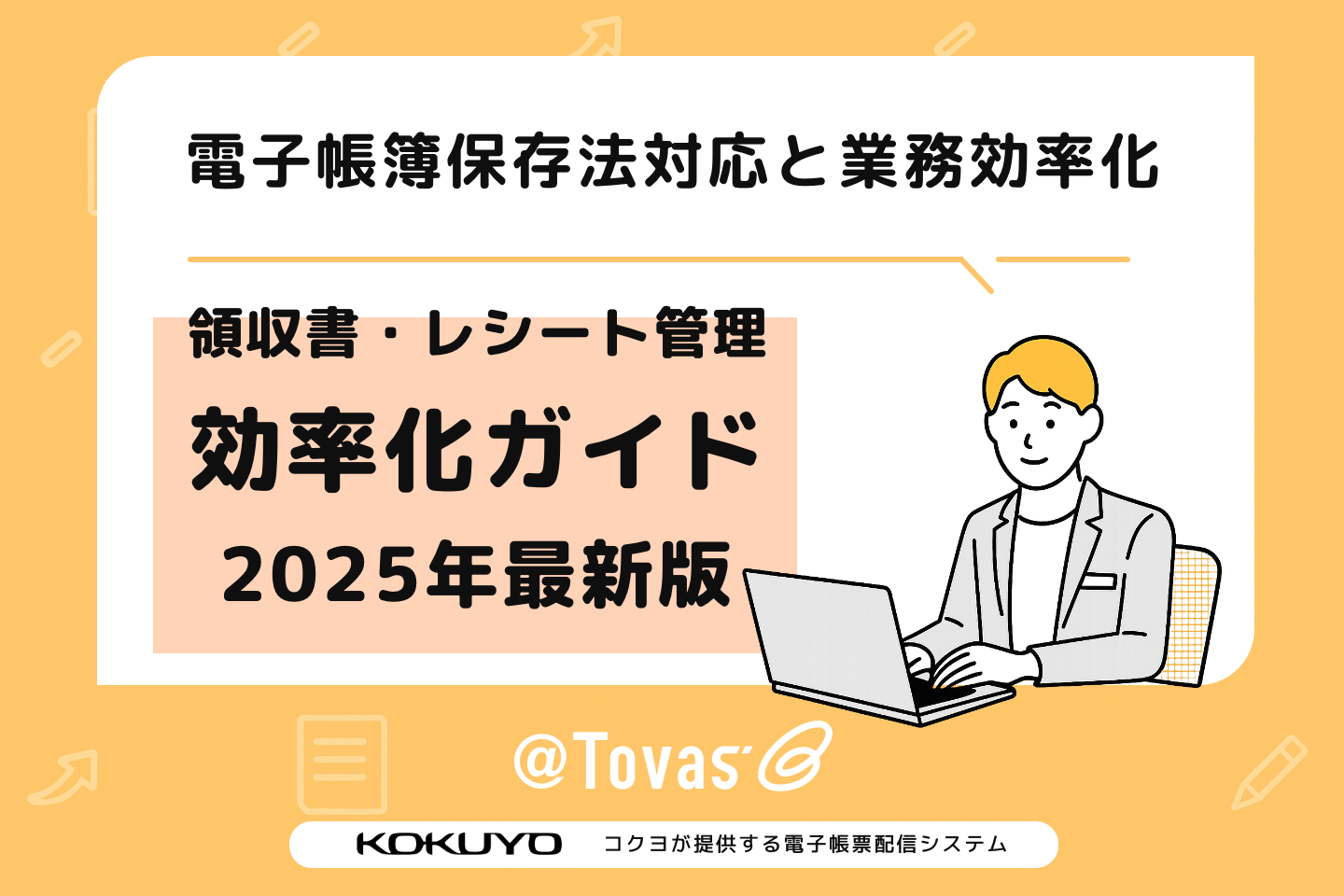
【2025年最新】領収書・レシート管理の効率化ガイド:電子帳簿保存法対応と業務効率化の両立
公開日:2025年4月20日 更新日:2025年7月28日
目次
はじめに
企業活動において、領収書やレシートの管理は経理業務の基本でありながら、多くの企業が頭を悩ませる課題でもあります。紙の領収書やレシートは紛失しやすく、保管スペースを取り、検索や集計に時間がかかるなど、さまざまな問題を抱えています。さらに、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正により、2024年1月以降は電子取引で授受した領収書・レシートデータ等の電子保存が原則として義務化され、その管理方法も大きく変わりつつあります。
本記事では、2025年最新の法令に対応した領収書・レシート管理の効率化方法について、電子帳簿保存法への対応と業務効率化の両立という観点から詳しく解説します。経理担当者の方々が直面する実務的な課題に焦点を当て、具体的な解決策を提案していきます。
領収書・レシート管理の現状と課題
従来の紙ベースでの領収書・レシート管理には、以下のような課題がありました。
1. 紛失・破損のリスク従業員が受け取ったレシートを紛失したり、印字が薄れて読めなくなったりする。
2. 保管スペースとコスト大量の紙の書類を保管するための物理的なスペースが必要となり、ファイルやキャビネットなどの備品コストもかかる。
3. 検索・確認の手間過去の領収書を確認したい場合、大量のファイルの中から探し出すのに時間と手間がかかる。
4. 手入力による非効率・ミス会計ソフトへのデータ入力が手作業となり、時間がかかる上に転記ミスや入力漏れが発生しやすい。
5. コンプライアンス対応の負担法定保存期間(原則7年)の管理や、税務調査時の書類提出準備に手間がかかる。
これらの課題は、経理部門の生産性を低下させるだけでなく、経営管理上のリスクにもつながりかねません。
電子帳簿保存法における領収書・レシート管理の要件
電帳法では、領収書やレシートを電子データとして保存する場合のルールが定められています。主に「電子取引データの保存」と「スキャナ保存」の2つの区分が関係します。
電子取引データの保存(義務)
対象電子メールで受領したPDFの領収書、Webサイトからダウンロードした利用明細、クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの利用履歴データ、スマートフォンアプリの決済データ、電子レシートなど、電子的に授受した取引情報。
対応義務(2024年1月1日以降、電子データで受け取ったものは電子データのまま保存が必要)。
電子取引データを保存する際には、以下の要件を満たす必要があります。
真実性の確保
以下のいずれかの措置が必要です。
1. タイムスタンプが付与されたデータを受領する。
2. データ受領後、速やかに(または入力期間制限内に)タイムスタンプを付与する。
3. データの訂正・削除が記録される、または訂正・削除ができないシステムを利用する。
4. 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿って運用する。
可視性の確保
以下の両方の要件を満たす必要があります。
1. 見読可能性の確保保存場所にPC、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、整然・明瞭・速やかに出力できるようにする。
2. 検索機能の確保原則として以下の要件を満たす検索機能を確保する。
a. 「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる。
b. 日付または金額は範囲指定で検索できる。
c. 二つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる。
【重要検索機能の緩和措置】
ただし、検索要件には重要な緩和措置があります。以下のいずれかに該当する事業者については、上記の検索要件(a, b, c全て)を満たす必要はありません。
(1) その判定期間における基準期間(前々事業年度)の売上高が5,000万円以下である事業者
(2) 電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている事業者
上記(1)または(2)に該当する事業者は、税務調査等の際に税務職員による電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、検索要件の確保は不要となります。
スキャナ保存(任意)
対象紙で受領した領収書やレシート、または自己が作成したこれらの控え。
対応任意(従来通り紙での保存も可能)。
紙の領収書等をスキャンして電子データで保存(スキャナ保存)する場合は、以下の主要な要件を満たす必要があります。
・ 入力期間の制限:受領後「速やか(原則7営業日以内)」または「業務処理サイクルに基づき、速やかに(最長2か月及び概ね7営業日以内)」に入力する。
・ 一定の解像度・階調:解像度200dpi以上、24ビットカラー(またはグレースケール)で読み取る。
・ タイムスタンプの付与等(真実性の確保):認定タイムスタンプを付与するか、訂正削除履歴が残る(または訂正削除できない)システムで保存する。
・ ヴァージョン管理:訂正・削除した場合にその事実と内容を確認できること(タイムスタンプを利用しない場合)。
・ 帳簿との相互関連性:帳簿データとスキャンデータの関連性を確認できるようにする。
・ 見読可能性の確保:ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、速やかに出力できるようにする。
・ 検索機能の確保:「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにする。
近年では、スマートフォンで撮影した画像データによるスキャナ保存も、一定の要件(解像度、タイムスタンプ等)を満たせば認められています。経費精算システム等と連携することで、従業員が外出先で受け取ったレシートをスマホで撮影し、そのまま電子保存・経費申請を行うといった運用も可能です。
【補足】インボイス制度「少額特例」との関連
領収書・レシート管理においては、2023年10月から始まったインボイス制度の「少額特例」も理解しておくことが重要です。
この特例により、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイス(適格請求書または適格簡易請求書)の保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
これは、日々の少額なレシート(コンビニでの購入、タクシー代など)の管理に大きく影響します。この特例の対象となる取引であれば、
・ 受け取ったレシートがインボイスの要件を満たしているか細かく確認する必要がない。
・ 電帳法のスキャナ保存(任意)を行う場合でも、インボイスとしての要件を気にする必要性が減る。
・ 電子取引で1万円未満の領収書データを受け取った場合も、インボイスとしての保存は不要(ただし、電子取引データとしての電子保存義務はあります)。
といったメリットがあり、経理処理や従業員の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、注意点として、この少額特例を適用できるのは、原則として基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者、または特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者などに限られます。自社が対象となるか確認が必要です。
領収書・レシート管理の電子化による5つのメリット
領収書・レシート管理を電子化し、電帳法に対応することで、多くのメリットが生まれます。
1. 業務効率の大幅な向上
・ 糊付けやファイリング、保管といった物理的な作業が不要に。
・ 検索機能で必要なデータを瞬時に検索・抽出可能。
・ OCR機能付きシステムなら、手入力の手間と時間を大幅に削減。
・ ワークフロー連携で申請・承認プロセスをスピードアップ。
2. コスト削減
・ 用紙代、印刷代、ファイル代、保管スペース費用などの直接コストを削減。
・ 上記の業務効率化による人件費(間接コスト)を削減。
・ 郵送費や交通費(経費精算のための出社など)の削減。
3. 入力ミス・不正の防止による精度向上
・ OCRによる自動入力で転記ミスを削減。
・ システムによる自動チェック機能(重複申請防止など)で不正を抑止。
・ 申請・承認履歴の可視化により、プロセスの透明性を向上。
4. ガバナンス・コンプライアンス強化
・ 電帳法やインボイス制度などの法的要件への対応が容易に。
・ アクセス権限設定やログ管理によるセキュリティ強化。
・ 監査対応の効率化(データの迅速な検索・提出)。
5. 多様な働き方への対応
・ テレワークやリモートワーク環境でも、領収書・レシートの提出や経費精算が可能に。
・ ペーパーレス化によるオフィススペースの有効活用。
・ 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を支援。
領収書・レシート管理の効率化:7つの実践ステップ
領収書・レシート管理の電子化・効率化を成功させるためには、計画的なアプローチが重要です。
ステップ1:現状分析と課題の明確化
・ 現在の領収書・レシートの処理フロー(受領→申請→承認→保管→廃棄)を可視化する。
・ 各プロセスにかかる時間、コスト、課題(紛失が多い、検索が大変など)を洗い出す。
・ 関与する従業員(営業、経理など)へのヒアリングを行う。
ステップ2:目標設定とスコープ定義
・ 「経費精算にかかる時間を〇%削減」「紙の保管量をゼロにする」「電帳法(電子取引)に完全対応する」など、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定する。
・ まずは特定の部署や種類の領収書から始めるなど、導入範囲(スコープ)を決定する(スモールスタート)。
ステップ3:社内規程の整備・見直し
・ 電子帳簿保存法に対応した運用ルール(事務処理規程を含む)を整備する。
・ 対象となる書類(電子取引データ、スキャンする書類)
・ 電子データの保存方法・場所・ファイル名規則
・ タイムスタンプや訂正削除履歴に関するルール
・ 検索要件への対応方法
・ 従業員の経費精算プロセス(申請期限、電子化手順など)
・ 既存の経費精算規程なども見直し、電子化後のフローに合わせる。
ステップ4:システム・ツールの選定
・ ステップ2で設定した目標とステップ3で整備した規程に基づき、必要な機能(電帳法対応、OCR精度、会計ソフト連携、スマホアプリ対応など)を洗い出す。
・ 複数のシステム・ツールを比較検討し、自社の要件に最も合うものを選定する(詳細は後述)。
ステップ5:導入準備とテスト運用
・ 選定したシステムの導入・設定を行う(アカウント設定、権限設定、ワークフロー構築など)。
・ 既存の会計ソフト等との連携設定を行う。
・ 一部の部署や担当者でテスト運用を実施し、操作性や課題点を洗い出す。フィードバックを元に設定や規程を修正する。
ステップ6:従業員への教育と本格導入
・ 新しいシステムの使い方や運用ルールについて、全従業員または対象者向けに説明会や研修を実施する。
・ 分かりやすいマニュアルやFAQを作成・配布する。
・ 問い合わせ対応窓口(ヘルプデスク)を設置する。
・ テスト運用の結果を踏まえ、本格的に導入・展開する。
ステップ7:効果測定と継続的な改善
・ 導入前に設定したKPIに基づき、導入後の効果(処理時間、コスト、エラー率など)を定期的に測定・評価する。
・ 従業員からのフィードバックを収集し、運用上の課題や改善点を洗い出す。
・ システム設定の見直し、運用ルールの改善、追加機能の検討など、継続的に改善を行う(PDCAサイクル)。
領収書・レシート管理システムの選定ポイント
自社に最適なシステムを選定することが、効率化成功の鍵となります。以下のポイントを比較検討しましょう。
1. 電子帳簿保存法への対応
・ 電子取引データ保存、スキャナ保存の最新要件(真実性・可視性確保、検索機能など)に対応しているか。JIIMA認証の有無も参考になる。
2. 操作性(UI/UX)
・ 従業員(特に申請者や承認者)が直感的で簡単に使えるか。モバイルアプリの使いやすさも重要。
3. OCR(光学文字認識)の精度
・ レシートの読み取り精度(日付、金額、店名など)は高いか。手書き領収書への対応はどうか。読み取り後の修正は容易か。
4. 他システムとの連携
・ 利用中の会計ソフト、給与計算ソフト、ERP、グループウェアなどとスムーズに連携できるか(API連携、CSV連携など)。
5. セキュリティ
・ データ暗号化、アクセス制御、ログ管理、不正検知など、セキュリティ対策は十分か。信頼できるデータセンターを利用しているか。
6. サポート体制
・ 導入支援、操作方法の問い合わせ、トラブルシューティングなど、ベンダーのサポート体制は充実しているか。レスポンスは早いか。
7. 費用対効果
・ 初期費用、月額(年額)利用料、オプション費用などを考慮し、導入効果(コスト削減、効率化)に見合うか。料金体系は分かりやすいか。
無料トライアルやデモンストレーションを活用し、実際の操作感や機能を試してから決定することをお勧めします。
よくある失敗ケースと対策
領収書・レシート管理の電子化プロジェクトで陥りやすい失敗ケースとその対策を知っておきましょう。
失敗ケース1導入目的が曖昧
・ 対策現状分析に基づき、具体的な課題と導入目的(KPI)を明確にする。
失敗ケース2現場の従業員が使ってくれない
・ 対策計画段階から現場の意見を聞く、操作性の良いシステムを選ぶ、導入メリットを丁寧に説明し教育を行う、導入後のサポート体制を整える。
失敗ケース3運用ルールが複雑すぎる・徹底されない
・ 対策シンプルで分かりやすいルールを策定する、マニュアルを整備し周知徹底する、定期的な研修やチェックを行う。
失敗ケース4法的要件を満たしていない
・ 対策導入前に電帳法の要件を正確に理解する、要件対応を謳うシステムでも詳細機能を確認する、必要に応じて専門家(税理士等)に相談する、定期的な監査を行う。
失敗ケース5既存システムとの連携がうまくいかない
・ 対策導入前に連携仕様や互換性を十分に確認する、連携テストを入念に行う、段階的な連携も検討する、ベンダーのサポートを活用する。
これらの失敗ケースを事前に想定し、適切な対策を講じることで、電子化プロジェクトの成功確率を高めることができます。
まとめ:領収書・レシート管理の電子化で実現する業務変革
領収書・レシート管理の電子化は、単なる紙の削減や保管スペースの節約にとどまらず、企業の業務プロセス全体を変革する可能性を秘めています。本記事のポイントを整理すると、以下のようになります。
電子化のメリットを最大化するために
1. 法令遵守と業務効率化の両立電子帳簿保存法(特に電子取引の義務化、検索要件緩和の理解)やインボイス制度(特に少額特例の活用)の要件を正しく理解し遵守しながら、業務効率化を実現することが重要です。適切なシステムの選定と業務フローの見直しにより、両立が可能になります。
2. 段階的なアプローチ一度にすべてを変えるのではなく、目的と範囲を明確にし、段階的に導入することで、混乱を最小限に抑え、成功確率を高めることができます。
3. 全社的な取り組み経理部門だけでなく、領収書・レシートを扱う全従業員を巻き込み、全社的な取り組みとして推進することで、真の業務変革を実現できます。経営層のコミットメントと社員の理解・協力が不可欠です。
領収書・レシート管理の電子化は、コスト削減や生産性向上はもちろん、ガバナンス強化や多様な働き方の実現にも貢献します。このガイドを参考に、自社に最適な方法で電子化・効率化を進め、より競争力のある経営基盤を構築してください。
参考情報(公的リンク)
・ 国税庁 電子帳簿保存法関係
電子帳簿保存法の概要、Q&A(一問一答)、パンフレットなどが掲載されています。(電子取引の検索要件緩和についてもQ&A等で確認できます)
・ 国税庁 インボイス制度 特設サイト
・ 国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧
「問108(少額特例)」などで詳細を確認できます。
・ 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
電帳法ソフト法的要件認証制度などの情報が掲載されています。
—–
免責事項本記事は、2025年4月時点の情報に基づき一般的な情報提供を目的として作成されており、特定の状況に対する税務アドバイスを提供するものではありません。税法や関連する制度は改正される可能性があります。具体的な税務処理や判断については、必ず最新の法令や国税庁の情報を確認するか、税理士等の専門家にご相談ください。